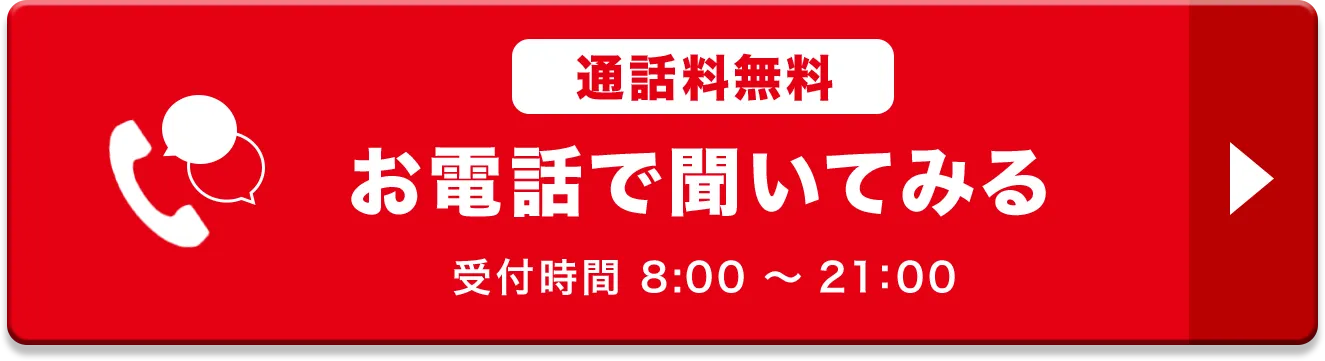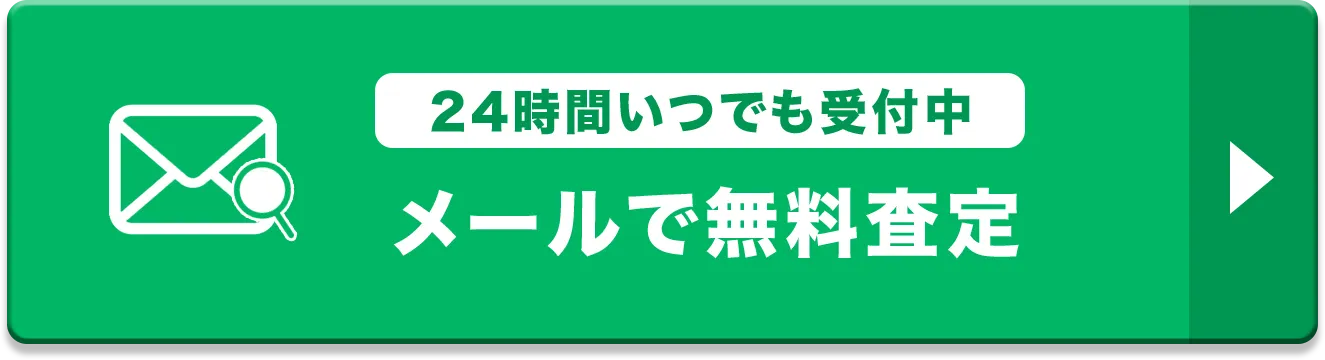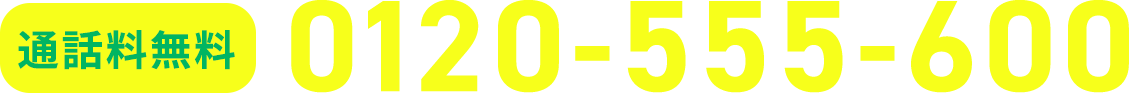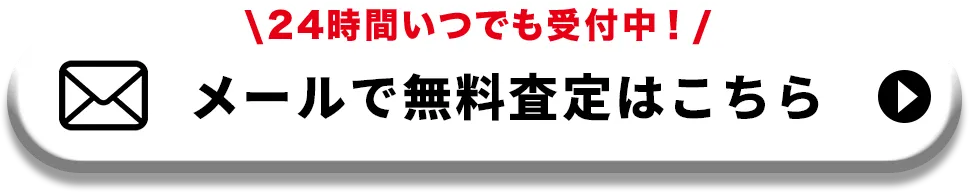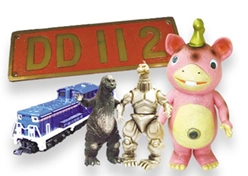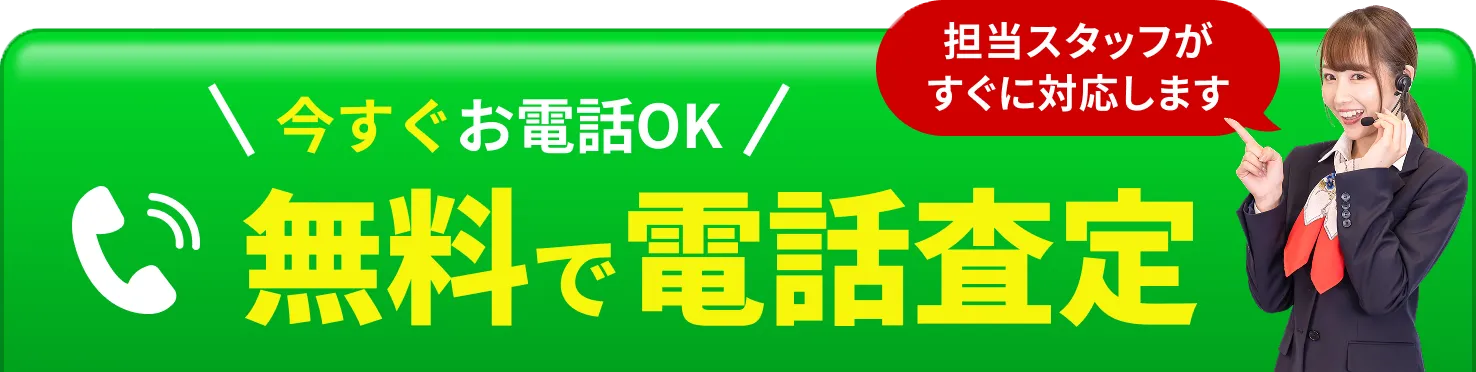スタグフレーションとは?円安・インフレ・物価高との違いと日本への影響を徹底解説

※下記の画像は全てイメージです
最近ニュースでよく耳にする「スタグフレーション」という言葉。これは景気が停滞しているにもかかわらず、物価が上昇するという異常な経済現象を指します。
「円安や物価高が続いている今、日本はスタグフレーションに陥っているのでは?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、スタグフレーションの定義から原因、日本経済との関係、そして生活への影響や対策までをわかりやすく解説します。
正しく理解することで、将来への備え方が見えてきます。複雑な経済の動きを、今ここで一緒に整理してみましょう。
2026年01月26日14:00更新
今日の金1gあたりの買取価格相場表
| 金のレート(1gあたり) | ||
|---|---|---|
| インゴット(金)27,516円 -166円 |
24金(K24・純金)27,296円 -165円 |
23金(K23)26,250円 -159円 |
| 22金(K22)25,095円 -151円 |
21.6金(K21.6)24,489円 -148円 |
20金(K20)22,398円 -135円 |
| 18金(K18)20,609円 -125円 |
14金(K14)15,959円 -97円 |
12金(K12)12,382円 -75円 |
| 10金(K10)11,061円 -67円 |
9金(K9)9,933円 -60円 |
8金(K8)7,374円 -45円 |
| 5金(K5)3,577円 -22円 |
||
※上記の買取価格はあくまで参考価格であり、市場の動向、
付属品の有無などによって実際の査定額が変動する場合があります。
Contents
スタグフレーションとは?意味と他の経済用語との違い
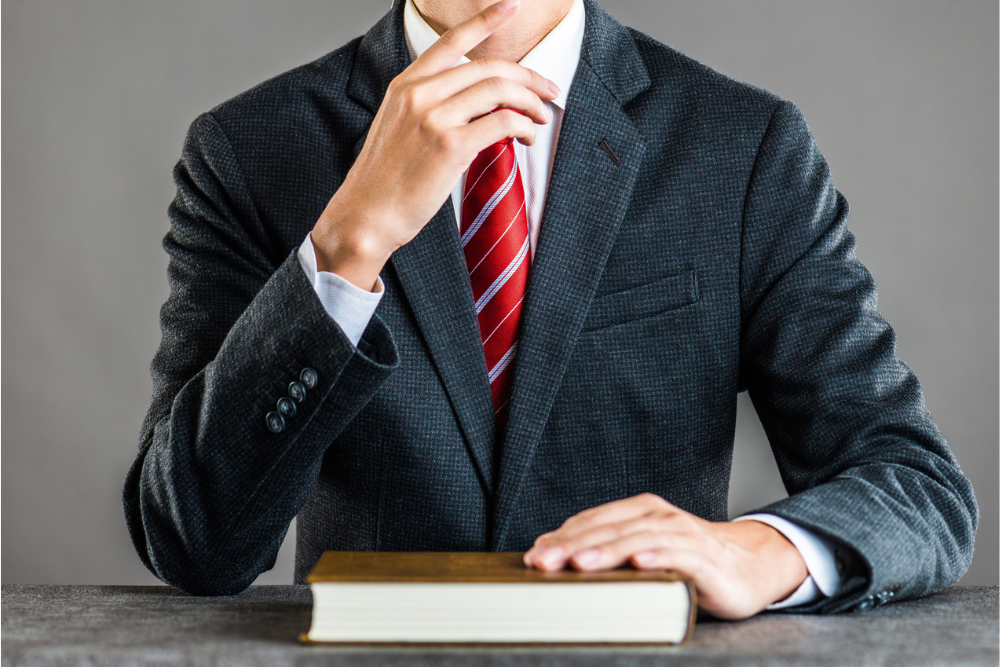
スタグフレーションは「景気停滞」と「物価上昇」が同時に起きる異常な経済現象です。通常、不況期には需要が減少して物価が下がり(デフレ)、好況期には需要増加によって物価が上がる(インフレ)ものですが、スタグフレーションでは不況にもかかわらず物価が上昇し続けます。
これはインフレーション(物価上昇)とデフレーション(物価下落)の悪い面を合わせ持つ状況であり、「最悪の経済状況」とも呼ばれます。
スタグフレーションの定義と「インフレ・デフレ・不況」との違い
スタグフレーションは、「スタグネーション(景気停滞)」と「インフレーション(物価上昇)」からなる造語で、景気が低迷し、失業率が高止まりしている中で物価だけが継続的に上がる状態を指します。一方、インフレは景気拡大に伴う物価上昇、デフレは景気後退に伴う物価下落を意味します。スタグフレーションでは景気後退(不況)にもかかわらず物価が上がり続ける点で、通常の関係から外れています 。
また、不況は経済活動が縮小する状態で、通常はデフレを伴います。しかしスタグフレーションは、不況に加えてインフレが並行するため、単なる不況より厄介です。つまり「不況下のインフレ」と表現されることもあります 。このような状況では失業率の高さと物価高騰が同時進行し、経済に二重の打撃を与えるのです。
- 関連記事はこちら
・インフレが金価格に関係する理由は?インフレヘッジや仕組みについても解説
・デフレ対策には金が最適?その理由とは
なぜ「最悪の経済状況」と呼ばれるのか
スタグフレーションが「最悪」と評されるのは、物価高と景気悪化という二つの苦境が重なるからです。まず家計では、収入が増えない中で生活必需品の値上げが続くため購買力が低下し、暮らしが厳しくなります。同時に企業も売上不振とコスト高に直面し、景気は冷え込みます。
さらに問題なのは政策対応の難しさです。通常、インフレ対策には利上げ、不況対策には緩和が有効ですが、スタグフレーション下ではそのどちらも副作用が大きく、ジレンマに陥ります1970年代には各国で対応策が見いだせず、「根本的な解消のめどが立たない」とされました。金融政策も財政政策も効果が相殺され、対応を誤ると事態が長期化します。
このようにスタグフレーションは、暮らしへの打撃と政策の困難さを併せ持つため、経済における最悪のシナリオの一つと位置づけられています。
なぜスタグフレーションは起こるのか?原因と過去の実例
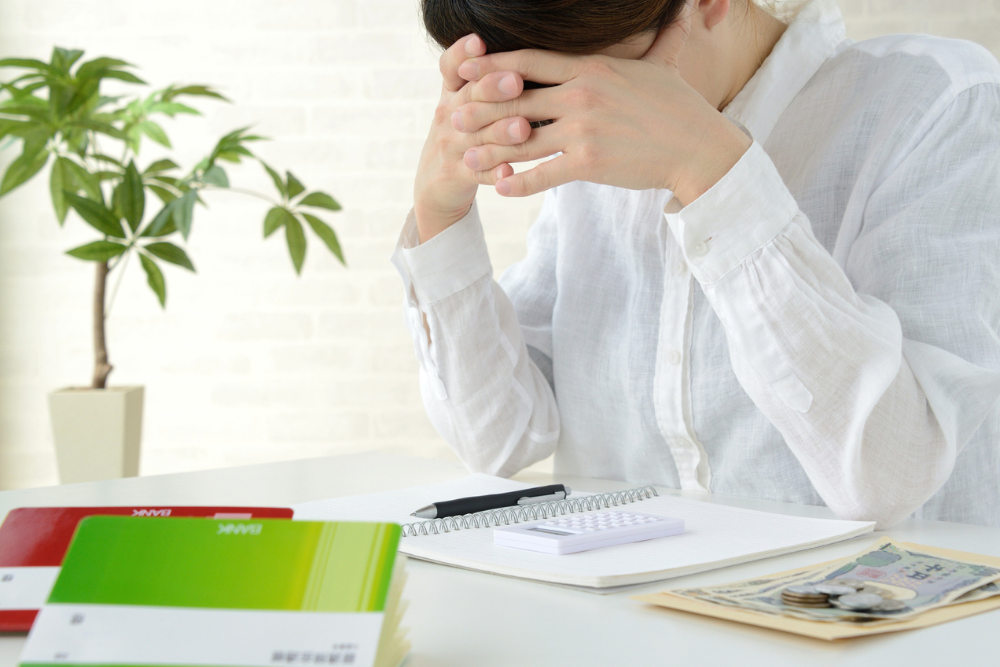
スタグフレーションが起こる主な原因は、供給ショック、政策運営の失敗、そして物価と賃金の悪循環(期待インフレ)の3つです。歴史的には、原油などの供給制約によるコスト高に、金融・財政政策の対応ミスやインフレ期待が重なり発生しました。
代表例が1970年代のオイルショックで、世界的な供給混乱と政策の遅れが同時に進行し、多くの国が深刻なスタグフレーションに見舞われました。
主な原因|供給ショック・政策ミス・期待インフレの影響
- 供給ショック(コストプッシュ型インフレ):
戦争や資源枯渇、災害などで原材料やエネルギーの供給が減少し、価格が急騰する現象です。需要は変わらなくても生産コストが上がり、物価が上昇します。企業はコスト高で活動が停滞し、景気が悪化。不況下の物価高=スタグフレーションを招きます。典型例は原油高で、製造・物流コストを押し上げ、不景気でも物価が上がる原因となります。 - 政策ミス(不適切な金融・財政運営):
政府や中央銀行の政策が状況に合わないと、景気と物価の両方が悪化します。例えば、景気が悪いのに緩和策を続ければ通貨安が進み、輸入物価が上昇します。逆に引き締めすぎると景気がさらに冷えます。1970年代には多くの国が物価上昇を許容し、結果としてスタグフレーションを悪化させました。供給ショックと政策ミスが重なると影響は深刻になります。 - 期待インフレと賃金・物価スパイラル:
「物価が今後も上がる」という予想が現実のインフレを長引かせます。労働組合や従業員が賃上げを要求し、企業が価格転嫁することで、賃金と物価が連鎖的に上昇します。1970年代の欧米や日本ではこのスパイラルが加速し、インフレが固定化しました。不況でも物価が下がらない状況が続き、スタグフレーションが慢性化しました。
以上の要因は単独ではなく、複合的に絡み合う点がスタグフレーションの特徴です。特に供給ショックが引き金となり、政策対応の遅れや誤りでインフレを抑えられず、さらには人々のインフレマインドが変化して賃金・物価の悪循環に陥ります。これが典型的な発生メカニズムといえます。
他国の事例|アメリカや新興国では何が起きたか?
スタグフレーションは日本だけでなく、アメリカや一部の新興国でも発生した歴史があります。
まずアメリカでは、1970年代のオイルショックがきっかけとなり、インフレ率が年10%を超える一方、失業率も上昇するスタグフレーションに陥りました。FRBは1980年代初頭、政策金利を20%近くまで引き上げてインフレを抑制しましたが、景気は大きく後退し、失業率も10%を超える事態となりました。この経験から、スタグフレーションの脱却には強力な金融引き締めが必要だが、同時に痛みも伴うことが明らかになりました。
また、近年ではブラジルが注目されました。コロナ禍の経済低迷に加え、干ばつの影響で食料や電力価格が上昇し、インフレと成長鈍化が同時進行。政策金利の引き上げで物価対策を行ったものの、景気の回復は遅れました。
こうした他国の事例からは、スタグフレーションは世界的に起こりうる現象であり、対応を誤れば長期的な停滞を招くことが読み取れます。経済構造や政策対応によって、国ごとの影響や回復の道筋は異なるものの、共通していえるのは「早期対応と的確な政策」が鍵になるということです。
日本経済とスタグフレーションの関係|今後の見通しは?

近年の日本では円安・輸入物価高・低成長が同時進行し、「スタグフレーション予備軍ではないか」との懸念が高まっています。 もっとも政府の公式見解では「現時点で日本はスタグフレーション状況にはない」とされ、将来それに陥らないよう警戒が呼びかけられています。
ここでは、足元の日本経済の状況とスタグフレーションとの関係、専門家の見解や注意点について見ていきます。
円安・物価高・低成長が同時に進行する今の日本経済
近年の日本では円安・輸入物価高・低成長が同時に進行し、「スタグフレーションの兆候が見られるのではないか」との懸念が高まっています。
2022年以降、ウクライナ情勢などの影響でエネルギーや食料価格が世界的に高騰しました。これに加えて急激な円安が進み、日本では輸入品の価格が上昇しました。その結果、消費者物価指数(CPI)は40年ぶりの水準に達し、物価上昇が家計を圧迫しています。
一方で、賃金の上昇は物価上昇に追いつかず、実質賃金の低下が続いています。実際に、2025年初頭時点でも前年同月比でマイナスが続いており、多くの家庭が生活の厳しさを実感しています。
政府は現状について「日本はスタグフレーションではない」との見解を示しています。理由は、欧米のような賃金・物価スパイラルは見られず、企業の業績や雇用環境も一定の安定が保たれているためです。しかし、物価上昇が長引く一方で賃金が伸び悩めば、スタグフレーションに陥るリスクが高まります。
今後も円安基調や資源価格の変動が続けば、物価高と景気低迷が固定化する可能性があり、専門家も「日本型スタグフレーション」への警戒を呼びかけています。
ニュースやデータから見る判断ポイント|誤解されがちな要素とは?
スタグフレーションかどうかを判断するには、いくつかの経済指標を総合的に見ることが重要です。まず注目すべきは物価上昇の持続性と景気の停滞度合いです。一時的な価格変動と長期的なインフレは異なります。消費者物価指数(CPI)の推移に加え、需給ギャップや失業率の動向も参考になります。
また、「物価が上がっている=スタグフレーション」とは限らず、賃金が上昇していれば実質所得は維持されるため問題が深刻化しにくい点もあります。賃金と物価の動きのバランスを見ることが大切です。
さらに、経済危機時にはデマや不安をあおる情報が出回るため、信頼できるデータや公的な発表に基づいて冷静に判断する必要があります。過去には誤情報によって買いだめが発生した例もあるため、情報リテラシーの高さが問われる場面です。
こうした観点から、自分自身で状況を整理し、経済報道を正しく読み解く姿勢が求められます。
スタグフレーションが生活・雇用・消費に与える影響

景気停滞と物価高騰が同時に進行すると、家計や企業の経済状況に深刻な悪影響を及ぼします。 まず家計では物価だけが上昇して実質賃金が低下するため生活水準が下がり、企業では原材料費や人件費の負担増で収益が圧迫されます。
その結果、人々の消費行動も変化し、節約志向が強まり買い控えが広がるなど、経済全体の需要縮小につながります。ここではスタグフレーション期における家計・企業への影響と消費者行動の変化について具体的に見てみましょう。
家計や企業への影響|実質賃金の低下とコスト上昇
スタグフレーション下では、賃金が伸び悩む中で物価だけが上がるため、家計の実質所得が減少します。たとえば、生活費が月5万円増えても収入が変わらなければ、貯蓄を取り崩すか支出を削る必要が出てきます。特に食品や光熱費、ガソリン代など生活必需品の値上がりは負担が大きく、家計のやりくりが厳しくなります。
企業にとっても影響は深刻です。売上が伸びない中で原材料費や人件費が増加すれば、収益が圧迫されやすくなります。特に中小企業や輸入原材料に依存する業種では打撃が大きく、コスト増を価格に転嫁できない場合、赤字に転落する可能性もあります。企業が支出を抑えると、人件費削減や雇用抑制が進み、労働市場も不安定になります。
こうした流れが続くと、消費がさらに冷え込み、景気の悪化を加速させるという負のスパイラルに陥ることになります。家計、企業、そして国家財政にまで影響が波及し、経済全体に広がるのがスタグフレーションの怖さです。
消費者行動の変化|節約志向・買い控え・市場トレンドの移行
スタグフレーション下では、消費者の支出行動に大きな変化が生まれます。特に目立つのが、節約志向の強まりです。物価上昇により家計が圧迫されると、日常的な買い物でも価格を重視するようになります。ブランド品をやめて安価な代替商品を選ぶ、特売日を狙って購入するなど、実利重視の行動が一般化します。
また、将来への不安から買い控えも進みます。耐久消費財や娯楽支出などの大きな出費を避け、支出に優先順位をつける「メリハリ消費」が浸透します。その結果、市場では高価格帯商品の売上が落ち込み、価格と質のバランスが取れた商品に人気が集まる傾向が見られます。
こうした行動変化に対応するため、企業も価格戦略や商品開発の見直しを迫られます。スタグフレーション期には、コストパフォーマンスの高さや生活に密着した価値提供が重視される傾向が強まり、消費の流れ全体がシフトしていきます。
スタグフレーションに備えるには?暮らしと資産を守るために

スタグフレーションのリスクに備えて、私たち一人ひとりができる対策があります。 物価高と不況のダブルパンチに耐えるには、日頃から家計を引き締めつつ、公的支援策を活用し、収入源を多様化することが有効です。
また、資産運用面ではインフレに強い資産を組み入れてリスク分散を図り、資産の目減りを防ぐ戦略が求められます。さらに、経済や政策に関する正しい情報を収集し、自らの判断力(経済リテラシー)を高めておくことで、不安定な局面でも冷静に対処できるでしょう。
以下では、個人でできる現実的な備え、資産防衛の考え方、情報収集とリテラシー向上のポイントを解説します。
個人でできる現実的な備え|節約・支援制度・収入の複線化
スタグフレーションに備えるには、日常生活の見直しと経済的な基盤づくりが大切です。まずは支出の最適化が基本です。光熱費の節約や固定費の見直し、特売活用や安価な代替商品の購入など、小さな工夫が家計の負担を和らげます。
また、政府や自治体が実施する支援制度の活用も重要です。低所得世帯や子育て世帯を対象とした給付金、公共料金の減免など、利用できる制度を把握しておくことで家計の安定につながります。最新情報は自治体の公式サイトや広報紙で確認できます。
さらに、収入源を複数持つ意識も必要です。副業や在宅ワーク、スキルを活かした小規模な収入活動を通じて、本業以外からも収入を得ることが、経済的リスクの分散になります。小さな副収入でも、家計の安心材料となるでしょう。
このように、節約・支援・複線化の3点を意識することが、先行き不透明な経済環境を乗り切る現実的な備えになります。
スタグフレーションで注目される「金」現物資産としての強みと活用法
スタグフレーションのように、物価が上昇しながら景気が悪化する局面では、「金」が資産防衛の手段として注目されます。金は中央銀行や企業の信用に依存しない実物資産であり、通貨の価値が下がっても一定の価値を保ちやすいのが最大の特徴です。特に円安やインフレが進行する中では、金の価値が相対的に高まる傾向があり、資産の目減りを防ぐヘッジ手段として有効です。
また、金は世界中で取引されており、流動性が高く、インゴットやジュエリーなど様々な形で保有できます。少額から購入可能な純金積立などを利用すれば、分散投資の一部としても組み込みやすくなります。将来の不確実性に備える手段として、「金」を取り入れることは、家計の安定にもつながります。
- 関連記事はこちら
・【2026年最新】今後の金相場の予想!高騰の理由といつまで上昇するのか見通しは?
まとめ
スタグフレーションとは、景気が停滞する中で物価が上昇する、通常とは異なる経済現象です。通常の不況やインフレとは異なり、政策対応が難しく、家計や企業への影響も深刻です。特に現在の日本では、円安や物価高の影響で、その兆候が見られ始めています。
このような局面では、生活防衛とともに、資産価値を守る対策も重要です。なかでも「金」は、通貨に左右されない現物資産としてインフレ耐性が高く、注目を集めています。不安定な経済環境の中で、まずは自身の資産状況を見直し、堅実な備えを始めてみませんか?
- おたからや査定員のコメント
金の買取においては、純度と重量が査定額の大部分を決定づけますが、状態や相場のタイミングも大切です。当店では、地金はもちろん、ジュエリーなどの加工品も正確に評価いたします。インゴット証明書がないお品でもご安心ください。
最新の市場価格に基づき、一点一点丁寧に査定を行い、ご納得いただける価格を提示できるよう努めています。ご自宅にある眠ったままの金製品が、思わぬ価値になることも。まずはお気軽にご相談ください。

「おたからや」での金の参考買取価格
ここでは、「おたからや」での「金」の参考買取価格の一部を紹介します。
| 画像 | 商品情報 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
 |
22金(K22) 千足金ネックレス | 1,304,800円 |
 |
21.6金(K21.6) クルーガーランド金貨まとめ | 1,235,300円 |
 |
18金(K18) ダイヤ付きペンダントトップ | 445,220円 |
 |
18金(K18) ヤングインディアン10ドル ペンダントトップ | 321,100円 |
 |
14金(K14) ブレスレット | 256,500円 |
 |
22金(K22) ネックレス | 247,300円 |
※状態や付属品の有無、時期によって買取価格が異なりますので詳細はお問い合わせください。
2026年01月26日14:00更新
今日の金1gあたりの買取価格相場表
| 金のレート(1gあたり) | ||
|---|---|---|
| インゴット(金)27,516円 -166円 |
24金(K24・純金)27,296円 -165円 |
23金(K23)26,250円 -159円 |
| 22金(K22)25,095円 -151円 |
21.6金(K21.6)24,489円 -148円 |
20金(K20)22,398円 -135円 |
| 18金(K18)20,609円 -125円 |
14金(K14)15,959円 -97円 |
12金(K12)12,382円 -75円 |
| 10金(K10)11,061円 -67円 |
9金(K9)9,933円 -60円 |
8金(K8)7,374円 -45円 |
| 5金(K5)3,577円 -22円 |
||
※上記の買取価格はあくまで参考価格であり、市場の動向、
付属品の有無などによって実際の査定額が変動する場合があります。
金の査定額は、市場での需要と供給バランスによって日々変動しますが、特に純度の高いインゴットや地金タイプは安定した人気があります。査定額を左右する最も重要なポイントは「純度(K24・K18など)」で、純度が高いほど1グラムあたりの買取価格も上昇します。
次に重要なのが「重さ(グラム数)」で、まとまった重量があるほど単価に加えて総額も高く評価されやすい傾向があります。そのほか、傷や変形の有無、刻印の明確さ、付属書類の有無(インゴット証明書など)も影響を与えます。買取を検討する際は、相場が高いタイミングを見計らうこともポイントです。
金の買取なら「おたからや」
金の価格が高騰する今、手元のジュエリーやインゴットを売却するなら、信頼と実績のある「おたからや」がおすすめです。
おたからやでは、国際基準に基づいた精度の高い査定が可能です。鑑定書がない金製品でも、素材の純度や重量を正確に見極めて、最新相場をふまえた適正価格をご提示します。たとえキズや変形があっても査定対象となり、インゴットはもちろん、ネックレスやブレスレットといった装飾品も高価買取のチャンスがあります。
出張やオンライン査定にも対応しているため、遠方の方や忙しい方も気軽にご相談いただけます。国内外44カ国の取引ネットワークと全国約1,630店舗のスケールを活かし、他店にはない高水準な買取価格を実現しています。
金の買取情報をチェックする24金(K24・純金)の買取情報をチェックする金のインゴットの買取情報をチェックする貴金属の買取情報をチェックする
おたからやの金買取
査定員の紹介
伊東 査定員

-
趣味
ショッピング
-
好きな言葉
有言実行
-
好きなブランド
ハリーウィンストン
-
過去の買取品例
おりん、インゴット
初めまして。査定員の伊東と申します。 おたからやでは金の買取をする際に、今日の金の1gの買取相場を基に、デザイン性などをプラスで評価して高価買取を行っております。過去に1万点以上の査定をさせていただきましたが、とても多くのお客様に想像以上の金額になったと喜んでいただきました。また、おたからやでは、すべての店舗に比重計を完備しているため、金の含有量を正確に測定することができます。 金額はもちろんのこと、接客も最高のおもてなしができるように心がけております。私共はお品物だけではなくお客様一人ひとりの思いに寄り添い満足して帰っていただけるように丁寧な説明を致します。誠心誠意対応させていただきますので、是非おたからやのご利用をお待ちしております。
その他の査定員紹介はこちら金を高く売るためのコツは、「金の価格が高いときに売ること」と「高値で買い取ってくれる専門店に売ること」です。金の価格は現在非常に高騰しているため、売却にはベストなタイミングといえます。
金の高価買取はおたからやにお任せください。
関連記事
タグ一覧
- #4℃
- #A.ランゲ&ゾーネ
- #GMTマスター
- #IWC
- #K10(10金)
- #K14(14金)
- #K22(22金)
- #K24(純金)
- #MCM
- #Van Cleef & Arpels
- #アクアノート
- #アクアマリン
- #アメジスト
- #アルハンブラ
- #アルマーニ
- #アンティーク時計
- #イエローゴールド
- #インカローズ
- #ヴァシュロンコンスタンタン
- #ヴァレンティノ
- #ヴァンクリーフ&アーペル
- #エアキング
- #エクスプローラー
- #エメラルド
- #エルメス
- #エルメス(時計)
- #オーデマ ピゲ
- #オパール
- #オメガ
- #お酒
- #ガーネット
- #カイヤナイト
- #カルティエ
- #カルティエ(時計)
- #グッチ
- #グリーンゴールド
- #クロエ
- #クロムハーツ
- #クンツァイト
- #ケイトスペード
- #ケリー
- #コーチ
- #ゴヤール
- #サファイア
- #サブマリーナー
- #サマンサタバサ
- #サンローラン
- #シードゥエラー
- #ジェイコブ
- #シチズン
- #シトリン
- #ジバンシィ
- #ジミーチュウ
- #ジャガールクルト
- #シャネル
- #シャネル(時計)
- #ジュエリー
- #ジュエリー買取
- #ショーメ
- #ショパール(時計)
- #スカイドゥエラー
- #スピネル
- #スフェーン
- #セイコー
- #ゼニス
- #セリーヌ
- #その他
- #ターコイズ
- #ターノグラフ
- #ダイヤモンド
- #タグ・ホイヤー
- #タンザナイト
- #チェリーニ
- #チューダー
- #ディオール
- #ティソ
- #デイデイト
- #デイトジャスト
- #デイトナ
- #ティファニー
- #ティファニー
- #トリーバーチ
- #トルマリン
- #ノーチラス
- #バーキン
- #バーバリー
- #パテック フィリップ
- #パネライ
- #ハミルトン
- #ハリーウィンストン
- #ハリーウィンストン(時計)
- #バレンシアガ
- #ピーカブー
- #ピアジェ
- #ピコタン
- #ピンクゴールド
- #フェンディ
- #ブライトリング
- #プラダ
- #プラチナ
- #フランクミュラー
- #ブランド品
- #ブランド品買取
- #ブランド時計
- #ブランパン
- #ブルガリ
- #ブルガリ(時計)
- #ブレゲ
- #ペリドット
- #ボーム&メルシェ
- #ボッテガヴェネタ
- #ポメラート
- #ホワイトゴールド
- #マークジェイコブス
- #マトラッセ
- #ミュウミュウ
- #ミルガウス
- #メイプルリーフ金貨
- #モーブッサン
- #ヨットマスター
- #リシャールミル
- #ルイ・ヴィトン
- #ルビー
- #レッドゴールド
- #ロエベ
- #ロレックス
- #ロンシャン
- #ロンジン
- #出張買取
- #地金
- #宝石・ジュエリー
- #宝石買取
- #時計
- #珊瑚(サンゴ)
- #相続・遺品
- #真珠・パール
- #色石
- #財布
- #金
- #金・プラチナ・貴金属
- #金アクセサリー
- #金インゴット
- #金の純度
- #金価格・相場
- #金歯
- #金縁メガネ
- #金貨
- #金買取
- #銀
- #銀貨
- #香水

知りたくありませんか?
「おたからや」が

写真1枚で査定できます!ご相談だけでも大歓迎!





































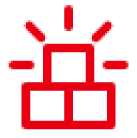

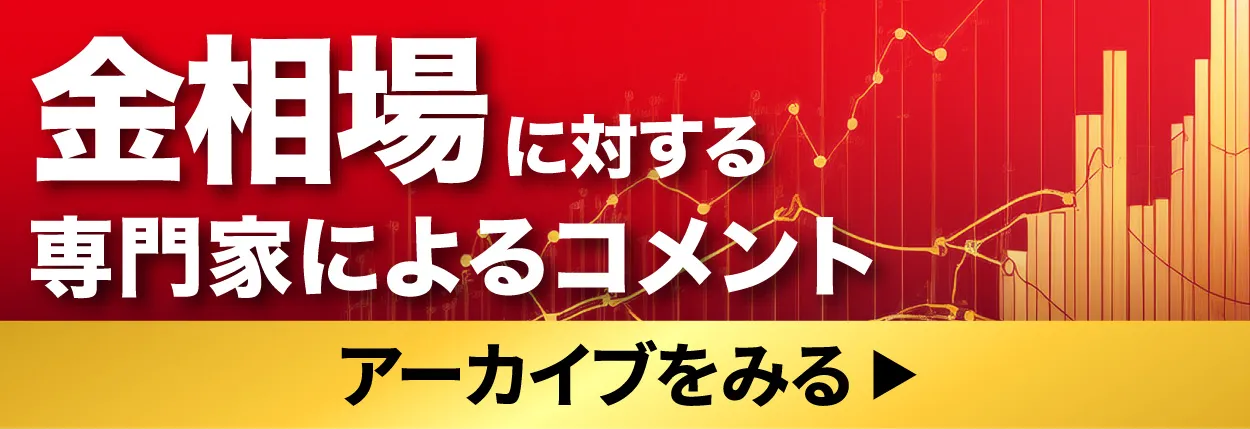
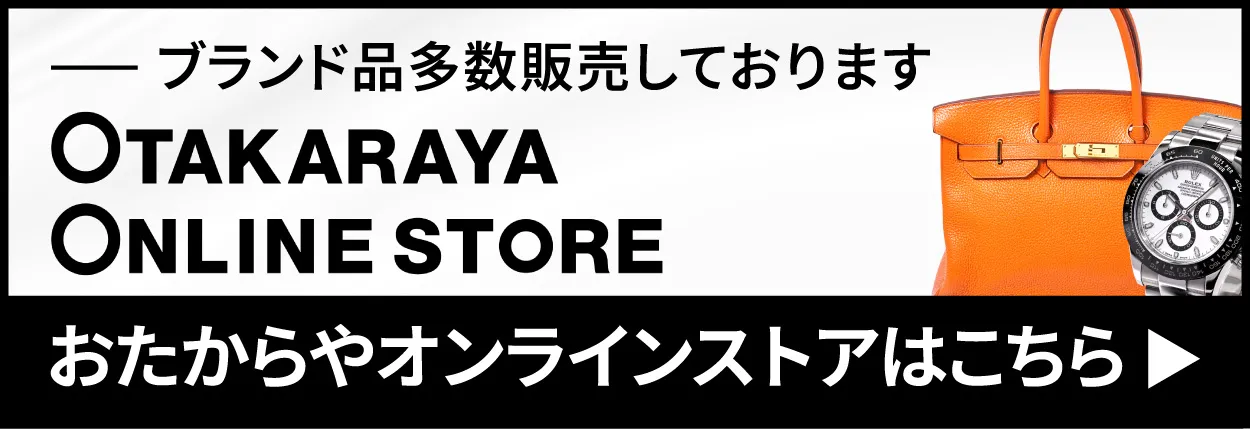
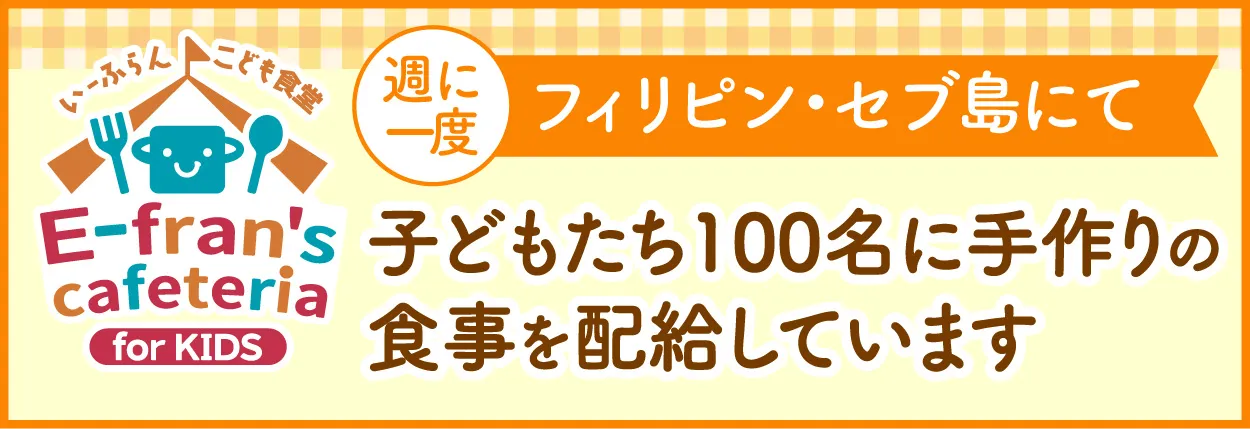

 金・インゴット買取
金・インゴット買取 プラチナ買取
プラチナ買取 金のインゴット買取
金のインゴット買取 24K(24金)買取
24K(24金)買取 18金(18K)買取
18金(18K)買取 バッグ・ブランド品買取
バッグ・ブランド品買取 時計買取
時計買取 宝石・ジュエリー買取
宝石・ジュエリー買取 ダイヤモンド買取
ダイヤモンド買取 真珠・パール買取
真珠・パール買取 サファイア買取
サファイア買取 エメラルド買取
エメラルド買取 ルビー買取
ルビー買取 喜平買取
喜平買取 メイプルリーフ金貨買取
メイプルリーフ金貨買取 金貨・銀貨買取
金貨・銀貨買取 大判・小判買取
大判・小判買取 硬貨・紙幣買取
硬貨・紙幣買取 切手買取
切手買取 カメラ買取
カメラ買取 着物買取
着物買取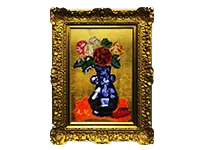 絵画・掛け軸・美術品買取
絵画・掛け軸・美術品買取 香木買取
香木買取 車買取
車買取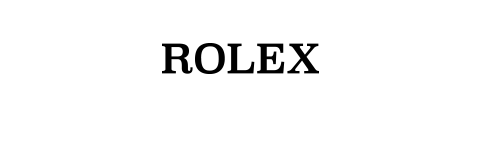 ロレックス買取
ロレックス買取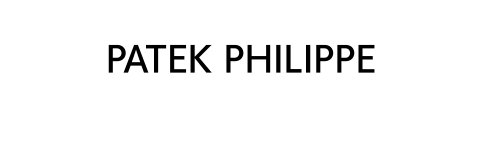 パテックフィリップ買取
パテックフィリップ買取 オーデマピゲ買取
オーデマピゲ買取 ヴァシュロン コンスタンタン買取
ヴァシュロン コンスタンタン買取 オメガ買取
オメガ買取 ブレゲ買取
ブレゲ買取 エルメス買取
エルメス買取 ルイ・ヴィトン買取
ルイ・ヴィトン買取 シャネル買取
シャネル買取 セリーヌ買取
セリーヌ買取 カルティエ買取
カルティエ買取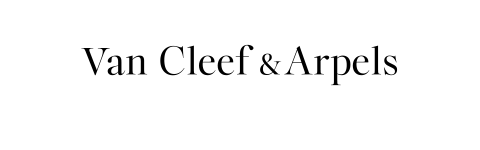 ヴァンクリーフ&アーペル買取
ヴァンクリーフ&アーペル買取 ティファニー買取
ティファニー買取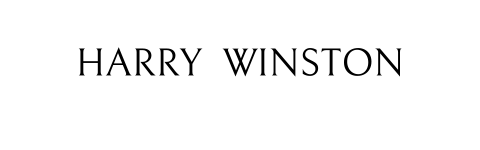 ハリー・ウィンストン買取
ハリー・ウィンストン買取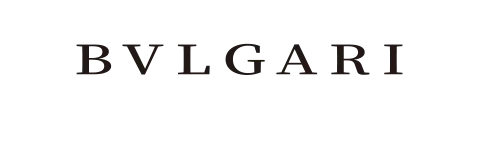 ブルガリ買取
ブルガリ買取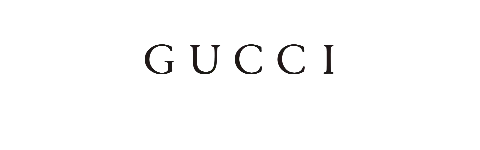 グッチ買取
グッチ買取
 ご相談・お申込みはこちら
ご相談・お申込みはこちら