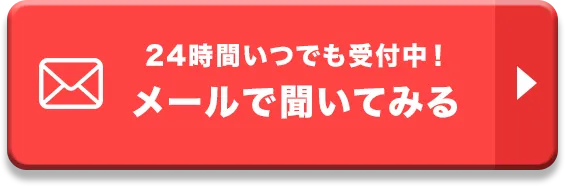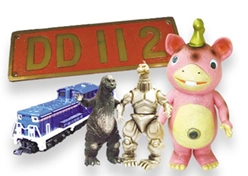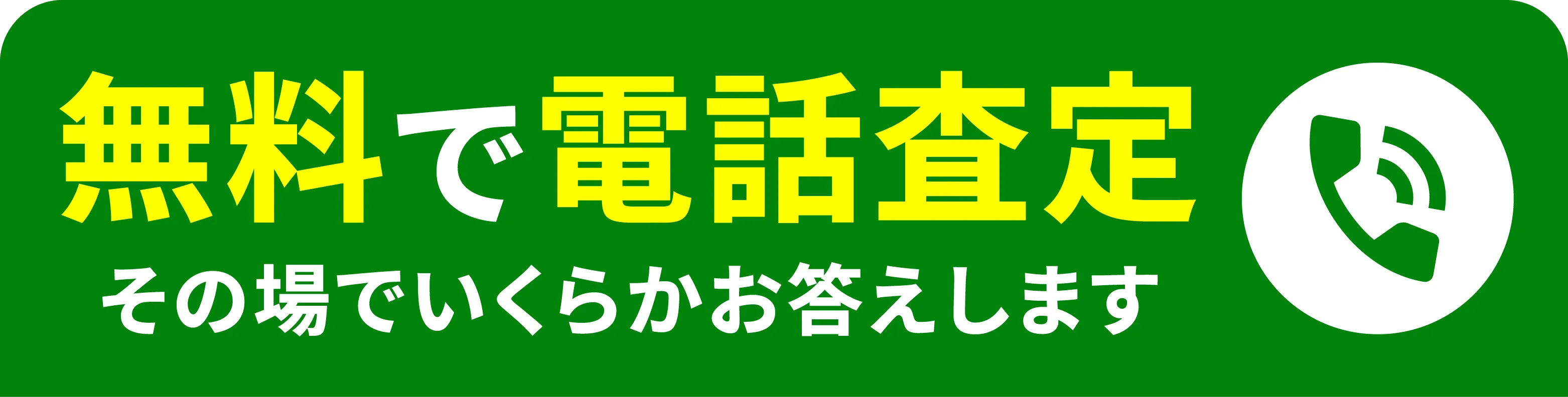金はどのように採掘される?
金鉱石の採掘方法や
製錬・精錬方法を解説

※下記の画像は全てイメージです
滑らかに光り輝くイメージのある金は、最初に金鉱石という形で採掘されます。
さまざまな方法で採掘された金鉱石は、製錬・精錬といった過程を経て市場に出回る姿へと変わっていくのです。
この記事では、金鉱脈の発見方法から金鉱石の採掘方法、そして金を取り出す方法までを紹介します。
金の産出量や埋蔵量、相場の動向など、金に関する気になるデータも紹介するので参考にしてください。
Contents
そもそも金鉱脈は
どのようにして発見される?
金を発掘するには、まず金鉱脈を発見する必要があります。先人たちはどのようにして金の眠る鉱山を発見してきたのでしょうか。
金鉱脈が見つかるパターンには、おもに「砂金のある河川を辿って発見されるケース」と「温泉地で発見されるケース」の2つがあります。
ここからは、それぞれのケースについて解説します。
砂金のある河川を辿って発見されるケース
1つ目は河川をさかのぼって発見されるケースです。
河川では、砂金、すなわち微小な金の粒が発見されることがあります。これは、上流にある金鉱脈の一部が川の流れや雨風によって少しずつ削られて、川底にたまることで起こる現象です。
つまり、砂金が見つかった河川の上流には、金鉱脈がある可能性が高いといえます。
闇雲に山を探すのではなく、河川の下流で砂金の有無を確認することで、効率よく金鉱脈を見つけられるのです。
実際に、これまでも河川をさかのぼる方法で多くの金山が見つかってきました。
川で採掘する金は「川金」と呼ばれており、有名な採掘場所には東京の多摩川や金沢の犀川、北海道のウソタンナイ川などがあります。
川金の採掘では、川底の砂から軽い砂利を取り除き、比重の重い金をえり分ける方法が採用されます。
温泉地で発見されるケース
2つ目は温泉地で金鉱脈が見つかるケースです。
日本には数多くの温泉地がありますが、すべての温泉地に金が眠っているわけではありません。
金鉱脈があるかどうかを見極めるうえで重要な判断材料となるのが、温泉に含まれる塩素の量です。
塩素を含む温泉の出る地域では「浅熱水性金銀鉱床」が見つかりやすいことがわかっています。
浅熱水性金銀鉱床とは、火山帯で上昇したマグマの中から溶けだした金や銀が、温度の急激な変化によって、地表近くで固まってできる鉱脈のことです。
しかし、塩素を含む温泉地に必ず浅熱水性金銀鉱床があるわけではなく、地下を掘ることで金鉱脈が本当にあるかどうかを確かめなくてはなりません。
そのため、温泉地で金鉱脈を発見するためには、忍耐強く調査を続ける必要があります。
山で採掘する金は「山金」と呼ばれており、国内の有名な採掘場所としては、新潟県の佐渡金山や鹿児島県の菱刈鉱山、北海道の鴻之舞金山などがあります。
有名な佐渡金山は資源が枯渇したため現在閉山されていますが、1601~1989年の長きにわたって金の採掘が行なわれていました。
なお、山金の採掘では、もともと山の露出部分を採掘する「露天掘り」(露頭掘り)が採用されていました。
しかし、技術革新にともなって現在では、坑道を掘る方法や爆薬を使う方法へと移行しています。
金鉱石を採掘する7つの方法
金鉱石の採掘方法は時代とともに進化してきました。ここでは、金鉱石を採掘する7つの方法を紹介します。
1.選鉱鍋
選鉱鍋は古代エジプト時代より用いられてきた方法です。
川金の採掘法として知られており、パンニング皿と呼ばれる選鉱鍋を使って砂金を選別します。
パンニング皿の多くは直径25~40cmの大きさで、砂金選別のために設けられた内側の段差が特徴です。
渦巻き状の段差が設けられているものもあり、中央に砂金がたまるので効率的に金を集められます。
2.選鉱台
選鉱鍋と同じように、川金の採取に用いられるのが選鉱台です。
一度に少量の砂金しか取れない選鉱鍋に比べて規模が大きいため、より効率的に砂金を採取できます。
選鉱台上部のザルのような入り口から砂金を含む土砂を注ぎ、水で洗い流すと箱の底に砂金がたまる仕組みです。
カリフォルニアやオーストラリアの鉱山ではかつて、木製の選鉱台が活用されていました。
3.露天掘り(露頭掘り)
地表から鉱脈に向かって渦巻き状に土を掘っていく方法で、おもに鉱床が地表から近い場合に採用されます。
穴の掘り進め方によって採掘できる鉱石の量が変わるのが特徴です。
坑道がなく落石の心配などは少ないものの、大量の鉱山廃棄物が出るデメリットがあります。
また、広い面積を掘り起こすことから、山の景観を大きく変えてしまう点も問題視されています。
4.水圧掘削法
水圧掘削法は「水力採鉱」とも呼ばれ、19世紀半ばのゴールドラッシュに沸くカリフォルニアで開発されました。
金鉱脈の側面や崖に高圧水などをかけ、崩した土砂を水路に落として金を採取する方法です。
土砂が水に流されるときに金を含んだ部分が自然に沈殿するため、効率よく金を集められます。
5.坑内採鉱法
坑内採鉱法は「コヨーティング」とも呼ばれ、地表から縦に穴を掘ったうえで横に坑道を伸ばしていく方法です。
鉱床が地下深いケースや、鉱床の幅が狭いケースでおもに採用されます。
地下深くの鉱脈からも金を採取できますが、作業中に落盤事故などが起こるリスクがあります。
6.硬岩探鉱法
金を含有する石英の岩を爆破してから掘削し、大量の流水を利用して金を選鉱する方法です。
最も多くの金を採掘できる方法とされていますが、環境や人体に与える悪影響が頻繁に取り沙汰されています。
金を選鉱するための流水が確保できない場合は水銀やヒ素が用いられ、それが大気汚染や健康被害の原因となっています。
7.含水爆薬
採掘場にいくつも開けた数メートルの穴に含水爆薬をセットしたあと、爆破で砕いた鉱石を回収する方法です。
回収した鉱石から金鉱石のみを選別して加工工場に運び、純度の高い金を取り出します。
含水爆薬は、ほかの方法よりも安全性の高い採掘方法として知られています。
国内で唯一金の採掘を続けている菱刈鉱山で採用されているのも、この含水爆薬を用いた方法です。
金鉱石に含まれる金はわずか
金を含有している鉱石全般を金鉱石といいます。
金鉱石にはさまざまな種類の金属が混ざっており、一般的に金は金鉱石1トンにつき2~10g程度しか含まれていません。
1トンの金鉱石からリング1つ分の金しか抽出できないと考えれば、金鉱石に含まれている金の少なさがわかるでしょう。
なお、金鉱石の中に含まれる金の量は一定ではなく、採掘する場所や鉱石によって異なります。
なかでも、1トンあたり10g以上の金を含有する金鉱石は「高品位鉱石」と呼ばれます。
金鉱石から金を取り出す製錬・精錬方法
採掘した金鉱石にはわずかな量の金しか含まれていないため、特殊な方法で純度の高い金を取り出す必要があります。
ここで重要になるのが「製錬」および「精錬」と呼ばれる工程です。
鉱石の中から貴金属を取り出す過程を「製錬」、取り出された金属塊からさらに高純度の金属を取り出す過程を「精錬」といいます。
どちらも読み方は同じですが、その意味は異なります。
ここからは、4種類の製錬・精錬方法を紹介します。
製錬方法1.「青化法」
青化法は、青化カリや青化ソーダの溶液を使って金を製錬する方法です。
金鉱石を砕き、さらに水を加えて泥状にしたものに青化ソーダ溶液を加えると、溶液中に金と銀が溶けだします。
これをろ過して回収した溶液に亜鉛粉末を加えれば、金と銀が分離して金を取り出せるようになるのです。
ちなみに、金と銀が溶けだしたこの溶液を「貴液(きえき)」と呼びます。
青化法は金が多く含まれる鉱石に有効とされています。誕生したのはイギリスで、1888年に特許製法として発表されました。
製錬方法2.「灰吹法」
粉々にした金鉱石を、鉛に入れて溶かすことで金を取り出すのが灰吹法です。
最初に、細かく砕いた金鉱石を鉛と一緒に炭火で溶かし、「貴鉛(きえん)」と呼ばれる金銀を含む鉛合金を作ります。
次に、灰が敷き詰められた皿状の容器に貴鉛を乗せ、空気を送りながら約1,000度まで加熱します。
その結果、鉛がほかの卑金属とともに酸化して灰に染み込み、金銀だけが残る仕組みです。
金と銀を取り出したあとは、金銀吹き分け法や焼金法といった手法によって金と銀を分け、さらに金の純度を高めていきます。
旧約聖書にも記載があるほど古くから行なわれてきた方法で、日本では江戸時代に用いられていました。
製錬方法3.「水銀アマルガム法」
水銀に溶けやすい金の性質を利用して製錬を行なうのが、水銀アマルガム法です。
まず、金鉱石を水銀と合わせて細かく砕き、「アマルガム」と呼ばれる合金にします。
このアマルガムを加熱して水銀を蒸発させることで、金や銀だけを取り出します。
水銀アマルガム法を採用すれば、比較的規模の小さい工場でも費用を抑えて金を取り出せます。
しかし、水銀は人体や地球環境に与える影響が大きいため、現在は南アフリカなどのごく一部の地域でしか行なわれていません。
精錬方法「電解精錬」
銅の溶鉱炉を利用した電解精錬は、現在主流となっている精錬方法です。
金鉱石と銅鉱石を一緒に溶鉱炉に入れると各種金属が混ざり、最初に銅のみが取り出されます。
銅がすべて取り除かれてから再び溶鉱炉を熱し、続いて銀を取り除きます。最後に、残った金属に電気分解処理を施して金を取り出す流れです。
電解精錬は、人体や地球環境への影響を心配する必要がありません。
ただし、大規模設備を要するので、地域によっては導入が難しいというデメリットもあります。
データで見る!金に関して
知っておきたい基礎知識
ここからは、金の埋蔵量や産出量、相場の変動など、金に関する基礎知識を4つの観点から紹介します。
金の採掘量は約18万~20万トン
地球上でこれまでに採掘された金の量は約18万~20万トンといわれています。
近年も中国やオーストラリアなどを中心に年間3,000トン程度の金が採掘されており、今後も採掘量は増えていく見込みです。
金の埋蔵量が多い国はオーストラリア
USGS(アメリカ地質調査所)の報告によると、世界で最も金の埋蔵量が多い国はオーストラリアで約8,400トンです。
金の埋蔵量の多い国
| 順位 | 国名 | 埋蔵量(トン) |
|---|---|---|
| 1 | オーストラリア | 約8,400 |
| 2 | ロシア | 約6,800 |
| 3 | 南アフリカ | 約5,000 |
| 4 | アメリカ | 約3,000 |
| 5 | ペルー | 約2,900 |
出典:U.S. Geological Survey「Mineral Commodity Summaries 2023」
次いで約6,800トンのロシアや、約5,000トンの南アフリカが埋蔵量の多い国として挙げられています。世界全体の埋蔵量は約5万2,000トンと推計されており、上位5ヵ国で世界全体の約半分を占めている計算になります。
金の年間産出量が多いのは中国
USGS(アメリカ地質調査所)の報告によると、2022年における金の年間産出量のトップは中国で、僅差でオーストラリアとロシアが続いています。世界全体では約3,100トンの金が産出されています。
金の年間産出量の多い国(2022年)
| 順位 | 国名 | 産出量(トン) |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 330 |
| 2 | オーストラリア/ロシア | 320 |
| 4 | カナダ | 220 |
| 5 | アメリカ | 170 |
| 6 | カザフスタン/メキシコ | 120 |
| 8 | 南アフリカ | 110 |
| 9 | ペルー/ウズベキスタン | 100 |
出典:U.S. Geological Survey「Mineral Commodity Summaries 2023」
日本の場合、国内で唯一商業規模での稼働を続けているのが鹿児島県の菱刈鉱山です。この鉱山では、1トンあたりおよそ20gの金を含む高品位鉱石が採掘されています。
金相場は上昇している
過去10年の金の買取相場を見ると、細かく変動しながらも全体としては上昇し続けていることがわかります。
2013年に4,000円台だった金の買取価格は、2023年には2倍超の1万円台まで上がっているのです。
2025年06月16日には過去最高値の17,508円を記録しました。
金を売るなら相場が高いときがベストといわれています。
日ごとの変動幅はそれほど大きくないため、高値を付けているタイミングで売却するとよいでしょう。
金を売るタイミングについては以下の記事でも解説しているので、ぜひ参考にしてください。
<関連記事>金の売り時はいつ?売却のタイミングを見極めるには相場を知ろう
まとめ
金鉱石の採掘方法は時代とともに変遷し、選鉱鍋を用いた原始的な方法から、含水爆薬を活用する安全性の高い方法まで幅広くあります。
また、金鉱石にはわずかな量の金しか含まれていないため、製錬・精錬を行ない、純度を高める必要があります。
現在市場に流通している金は、このように長い道のりを経て製品化されています。金が採掘されてから人の手に渡るまでの工程を知ることで、あらためて金の価値を実感できるのではないでしょうか。
金を高く売るためのコツは、「金の価格が高いときに売ること」と「高値で買い取ってくれる専門店に売ること」です。金の価格は現在非常に高騰しているため、売却にはベストなタイミングといえます。
金の高価買取はおたからやにお任せください。
関連記事
タグ一覧
- #出張買取
- #香水
- #4℃
- #A.ランゲ&ゾーネ
- #GMTマスター
- #ノーチラス
- #IWC
- #K10(10金)
- #K14(14金)
- #K22(22金)
- #K24(純金)
- #MCM
- #Van Cleef & Arpels
- #アクアノート
- #アクアマリン
- #アメジスト
- #アルハンブラ
- #アルマーニ
- #アンティーク時計
- #イエローゴールド
- #ピンクゴールド
- #インカローズ
- #ヴァシュロンコンスタンタン
- #ヴァンクリーフ&アーペル
- #エクスプローラー
- #エメラルド
- #エルメス
- #プラチナ
- #エルメス(時計)
- #オーデマ ピゲ
- #オパール
- #オメガ
- #ガーネット
- #カイヤナイト
- #カルティエ
- #カルティエ(時計)
- #ルビー
- #グッチ
- #グリーンゴールド
- #珊瑚(サンゴ)
- #クロエ
- #真珠・パール
- #ハリーウィンストン
- #クロムハーツ
- #クンツァイト
- #ケイトスペード
- #ケリー
- #ブルガリ
- #コーチ
- #モーブッサン
- #ゴヤール
- #サファイア
- #サブマリーナー
- #サマンサタバサ
- #ブランド品
- #サンローラン
- #ブランド品買取
- #シードゥエラー
- #財布
- #シチズン
- #シトリン
- #バーキン
- #ジバンシィ
- #ジミーチュウ
- #マトラッセ
- #ピーカブー
- #ルイ・ヴィトン
- #ピコタン
- #シャネル
- #バレンシアガ
- #シャネル(時計)
- #バーバリー
- #ボッテガヴェネタ
- #ジュエリー
- #ジュエリー買取
- #ショパール(時計)
- #スカイドゥエラー
- #スピネル
- #スフェーン
- #セイコー
- #ゼニス
- #ペリドット
- #ロエベ
- #セリーヌ
- #フェンディ
- #ターコイズ
- #ホワイトゴールド
- #ターノグラフ
- #ダイヤモンド
- #タグ・ホイヤー
- #マークジェイコブス
- #タンザナイト
- #チェリーニ
- #メイプルリーフ金貨
- #ロンシャン
- #チューダー
- #ディオール
- #リシャールミル
- #プラダ
- #デイデイト
- #レッドゴールド
- #ミュウミュウ
- #デイトジャスト
- #デイトナ
- #ティファニー
- #ティファニー
- #地金
- #トリーバーチ
- #宝石・ジュエリー
- #ブランド時計
- #宝石買取
- #トルマリン
- #時計
- #ロレックス
- #ヨットマスター
- #色石
- #ミルガウス
- #パテック フィリップ
- #金
- #ブレゲ
- #金・プラチナ・貴金属
- #ハミルトン
- #金アクセサリー
- #ブルガリ(時計)
- #金インゴット
- #ブライトリング
- #金の純度
- #フランクミュラー
- #金価格・相場
- #金歯
- #金縁メガネ
- #パネライ
- #金貨
- #ピアジェ
- #金買取
- #銀
- #ブランパン
- #銀貨
お持ちの金・貴金属のお値段、知りたくありませんか?
高価買取のプロ「おたからや」が
無料でお答えします!


-

店頭買取
-
査定だけでもOK!
買取店舗数は業界最多の
約1,450店舗以上!おたからやの店舗数は全国 約1,450店舗以上(待機店舗を含む)。これは、数ある買取店の中で最多を誇ります。日本全国津々浦々にて、地域密着でお買取りを承っております。
-

出張買取
-
査定だけでもOK!
買取専門店おたからやの
無料出張買取。買取専門店おたからやの無料出張買取です。出張料・査定料・買取手数料は全て無料、査定は最短5分です。随時キャンペーンを実施をしております!まずはお気軽にご相談ください!































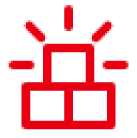

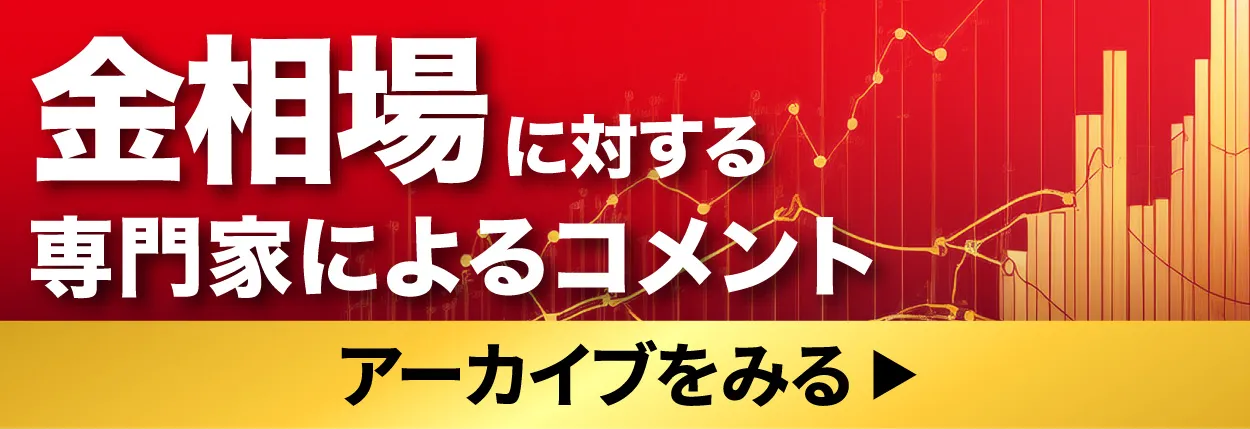
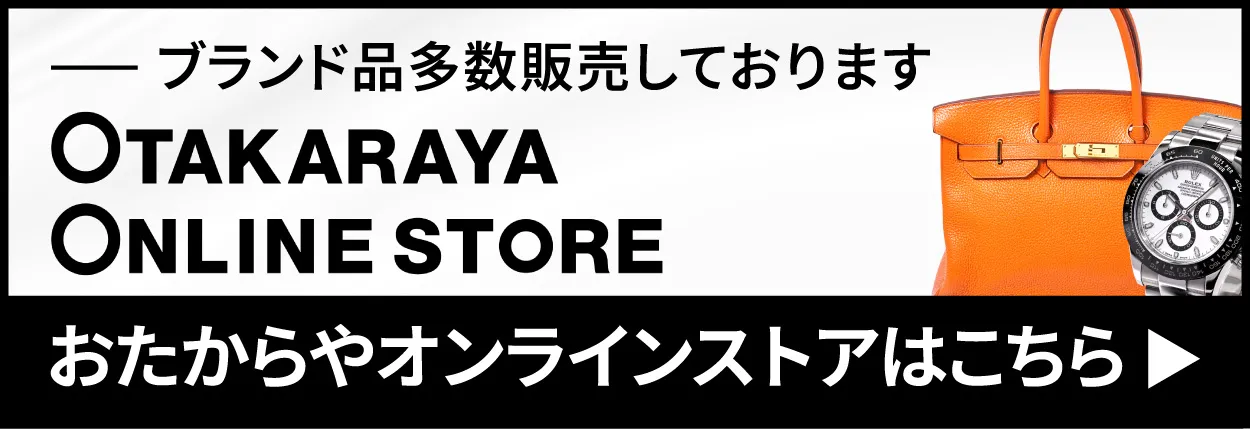
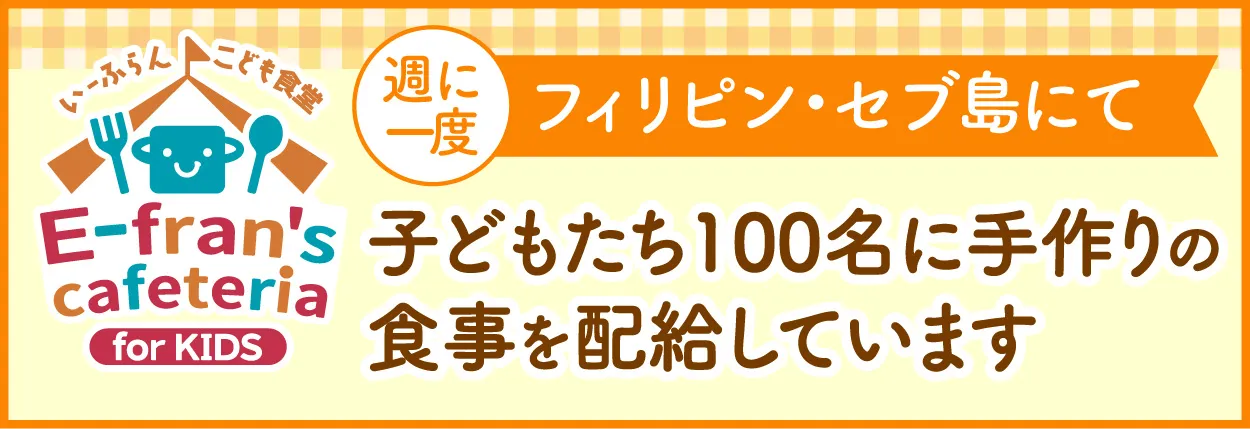


 金・インゴット買取
金・インゴット買取 プラチナ買取
プラチナ買取 金のインゴット買取
金のインゴット買取 24K(24金)買取
24K(24金)買取 18金(18K)買取
18金(18K)買取 バッグ・ブランド品買取
バッグ・ブランド品買取 時計買取
時計買取 宝石・ジュエリー買取
宝石・ジュエリー買取 ダイヤモンド買取
ダイヤモンド買取 サファイア買取
サファイア買取 エメラルド買取
エメラルド買取 ルビー買取
ルビー買取 喜平買取
喜平買取 メイプルリーフ金貨買取
メイプルリーフ金貨買取 シルバー買取
シルバー買取 金貨・銀貨買取
金貨・銀貨買取 大判・小判買取
大判・小判買取 硬貨・紙幣買取
硬貨・紙幣買取 切手買取
切手買取 カメラ買取
カメラ買取 着物買取
着物買取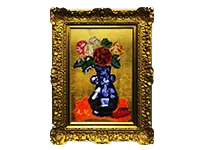 絵画・掛け軸・美術品買取
絵画・掛け軸・美術品買取 香木買取
香木買取 車買取
車買取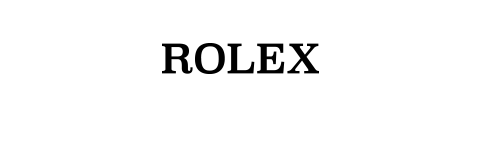 ロレックス買取
ロレックス買取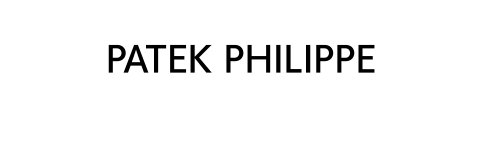 パテックフィリップ買取
パテックフィリップ買取 オーデマピゲ買取
オーデマピゲ買取 ヴァシュロン コンスタンタン買取
ヴァシュロン コンスタンタン買取 オメガ買取
オメガ買取 ブレゲ買取
ブレゲ買取 エルメス買取
エルメス買取 ルイ・ヴィトン買取
ルイ・ヴィトン買取 シャネル買取
シャネル買取 セリーヌ買取
セリーヌ買取 カルティエ買取
カルティエ買取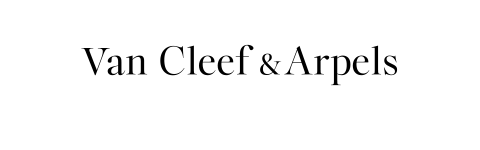 ヴァンクリーフ&アーペル買取
ヴァンクリーフ&アーペル買取 ティファニー買取
ティファニー買取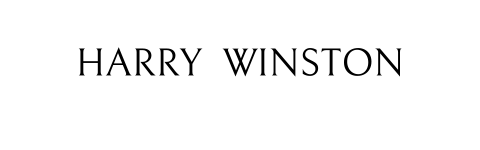 ハリー・ウィンストン買取
ハリー・ウィンストン買取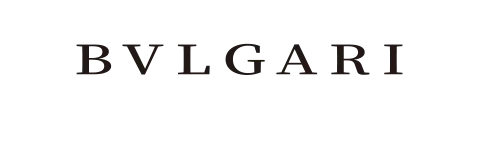 ブルガリ買取
ブルガリ買取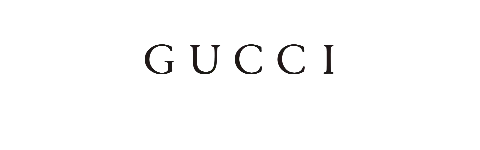 グッチ買取
グッチ買取
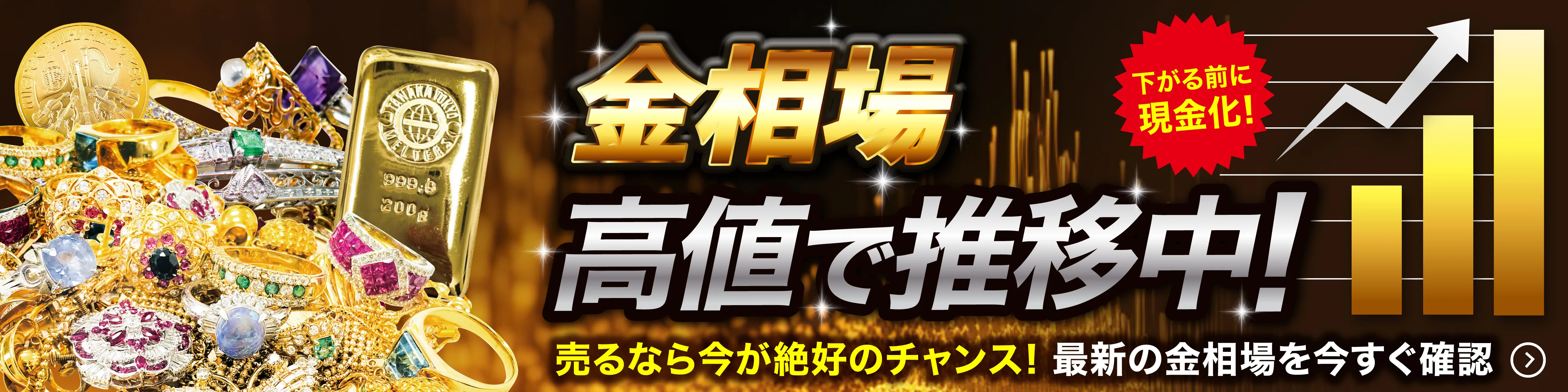



 ご相談・お申込みはこちら
ご相談・お申込みはこちら
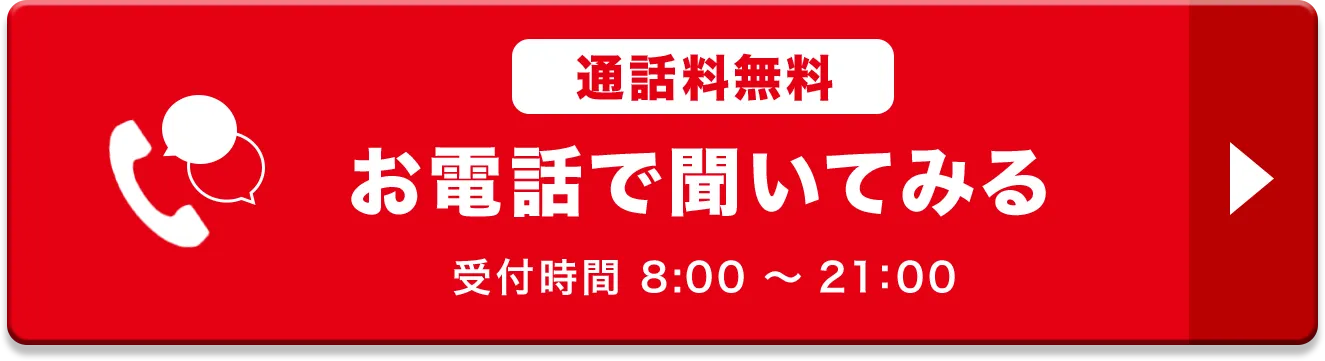
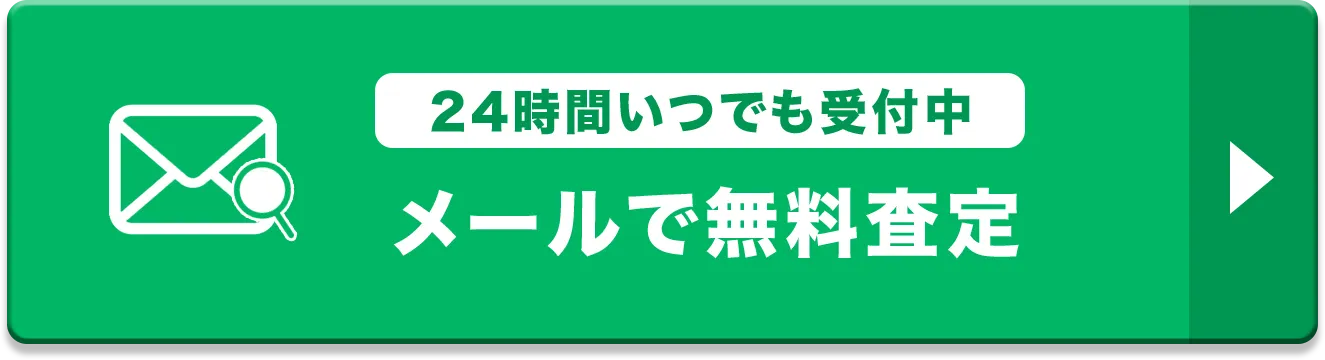

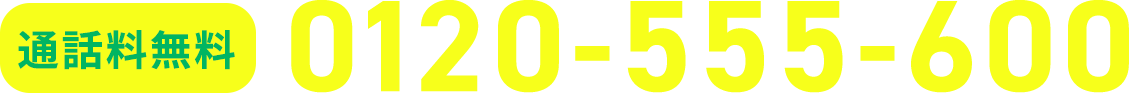
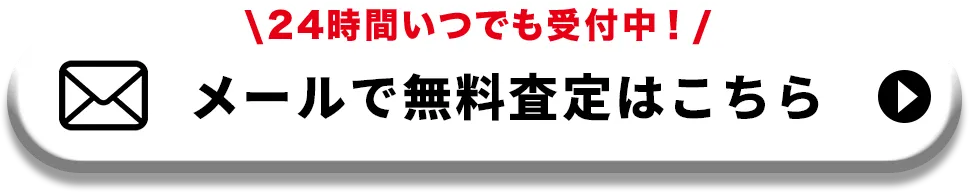
![【[current_year]最新】貴金属買取業者おすすめランキング17選!高く売るコツと選び方のポイントもご紹介](https://www.otakaraya.jp/app/wp-content/uploads/2025/06/0-Photoroom-7.webp)