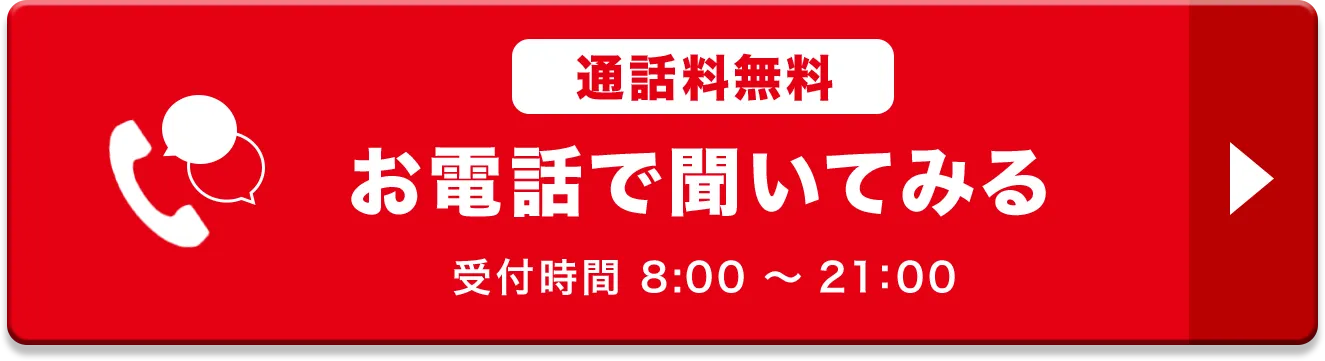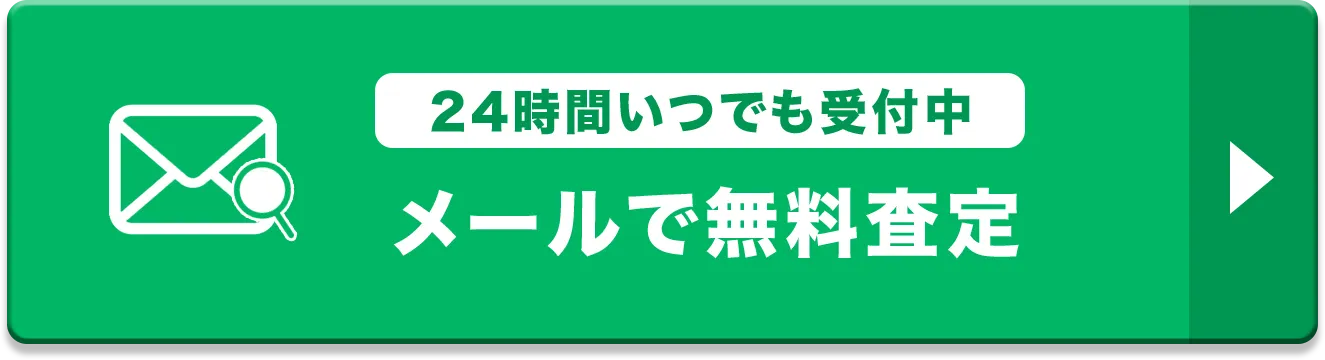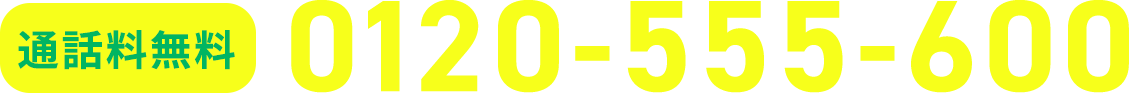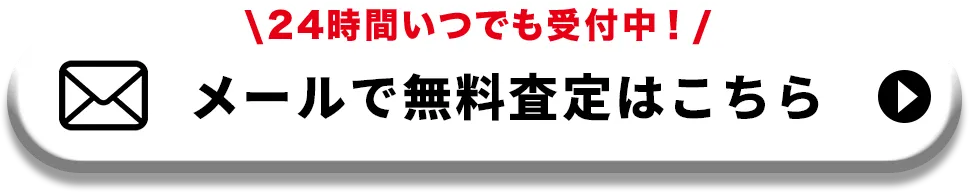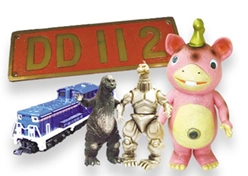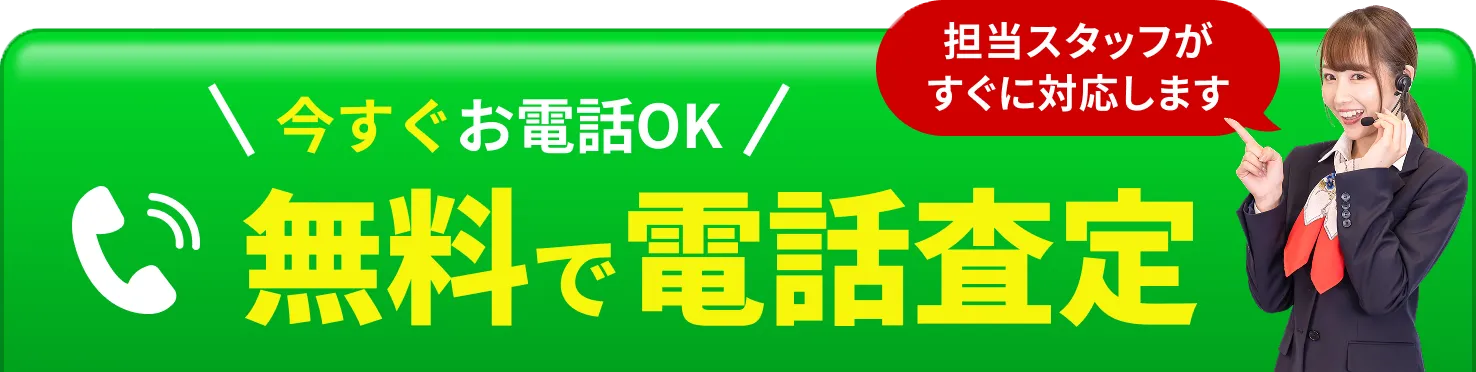日本の埋蔵金伝説ランキング!発見事例から有名スポットまで徹底解説

※下記の画像は全てイメージです
「日本には本当に埋蔵金があるの?」
「実際に発見された埋蔵金ってあるの?」
そんな疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。
戦国時代の武将が隠した軍資金から、幕末の徳川埋蔵金まで、日本各地には数々の埋蔵金伝説が語り継がれています。
テレビ番組で話題になることも多く、ロマンあふれる宝探しに心を躍らせる人も少なくありません。
この記事では、日本の有名な埋蔵金伝説から実際の発見事例まで詳しく解説し、埋蔵金にまつわる真実と伝説の境界線に迫ります。
Contents
日本の埋蔵金とは?歴史的背景と現代の定義

日本の埋蔵金は、単なる宝探しのロマンを超えて、歴史や文化と深く結びついています。
その背景と現代における意味を理解することで、埋蔵金の本質が見えてくるでしょう。
埋蔵金が生まれた歴史的背景
日本で埋蔵金が生まれた背景には、戦乱の時代が大きく関わっています。戦国時代から江戸時代にかけて、武将たちは軍資金や財産を守るため、秘密の場所に金銀財宝を隠したとされています。
当時は銀行のような金融機関が存在せず、財産を守る手段が限られていました。敗戦や落城の際に、再起を期して財宝を地中に埋めることは、理にかなった選択だったといえるでしょう。
また、江戸時代の商人たちも、火事や盗難から財産を守るため土蔵の床下や屋敷の庭に金貨を埋めることがあり、こういった習慣が今日の埋蔵金伝説の土台となっています。
現代における埋蔵金の定義
現代において埋蔵金とは、過去に何らかの理由で地中に埋められ、現在まで発見されていない財宝を指します。
主に金貨、銀貨、貴金属類が該当し、歴史的価値も含めて評価されることが多いでしょう。
埋蔵金には、意図的に隠されたものと偶然埋もれたものと2種類があります。前者は戦国武将の軍資金や商人の蓄財、後者は天災や事故によって埋没した財産などが含まれます。
ただし、すべての地中の財宝が埋蔵金というわけではありません。長期間放置され、所有者不明となったものが埋蔵金と呼ばれるのです。
埋蔵金と埋蔵文化財の違い
埋蔵金と混同されやすいのが埋蔵文化財ですが、両者には明確な違いがあり、埋蔵文化財は、土地に埋蔵されている文化財全般を指し、土器や石器なども含まれます。
法的な扱いも異なり、埋蔵文化財は文化財保護法によって保護され、発見した場合は教育委員会への届出が義務付けられ、学術的な調査が行われることになります。
一方、埋蔵金は主に経済的価値に焦点が当てられ、遺失物法の適用を受けることが多い傾向にあります。
ただし、歴史的価値が高い場合は、文化財として扱われることもあるため判断が難しいケースもあるでしょう。
日本の有名な埋蔵金伝説ランキングTOP5

日本各地に伝わる埋蔵金伝説の中から、特に有名で多くの人々を魅了してきた5つをランキング形式でご紹介します。
1位:徳川埋蔵金
徳川埋蔵金は、日本で最も有名な埋蔵金伝説といえるでしょう。幕末の1868年、江戸城が無血開城された際、徳川幕府の御用金360万両が消えたとされています。
伝説によると、勘定奉行の小栗上野介が幕府再興のために群馬県の赤城山麓に埋めたといわれています。
現在の価値に換算すると、数千億円から数兆円という途方もない金額になり、テレビ番組でも何度も取り上げられ大規模な発掘調査が行われてきました。
しかし、決定的な発見には至っておらず、今なお多くの人々のロマンをかき立てています。
赤城山の地形や地質から、本当に埋蔵可能かという議論も続いているのが現状です。
2位:武田信玄の軍資金
戦国最強と謳われた武田信玄の軍資金も埋蔵金伝説として度々話題に上がるといえるでしょう。
武田信玄は甲斐の金山から産出される豊富な金を軍資金として蓄えていたとされ、その一部が今も眠っているといわれています。
特に有名なのが、山梨県の「武田の埋蔵金」です。
武田家滅亡の際、家臣たちが再起を期して金銀を各地に分散して埋めたという言い伝えがあり、現在では甲府盆地周辺や富士山麓が有力な候補地とされています。
信玄堤と呼ばれる治水工事の際にも大量の金が使われたという記録があり、その残りがどこかに隠されているのではないかと考える研究者もいますが、現在でも埋蔵金は見つかっていません。
3位:豊臣秀吉の黄金
天下人となった豊臣秀吉は、莫大な富を蓄えていたことで知られ、大坂城の金蔵には日本中から集められた金銀財宝が山のように積まれていたといわれています。
特に有名なのが、兵庫県猪名川町の多田銀山跡に眠っているとされる「多田銀山の埋蔵金」でしょう。
大坂の陣で豊臣家が滅亡する際、これらの財宝の一部が持ち出され、各地に埋められたという伝説があります。
また、秀吉の朝鮮出兵の際に用意された軍資金の一部も、行方不明になっているという説があるなど、秀吉の財宝を求めて今も探索が続けられています。
4位:結城家の埋蔵金
結城家は、関東の名門武家として知られ、埋蔵金伝説も語り継がれています。
特に有名なのが、茨城県結城市に伝わる「結城家の埋蔵金」といえるでしょう。
戦国時代末期、結城秀康が越前に移封される際、それまでに蓄えた財宝を結城の地に埋めたという伝説があり、結城城跡周辺や市内の古い寺社の境内が有力な埋蔵場所として挙げられています。
実際に明治時代には、農作業中に古い金貨が発見されたという記録も残っており、伝説に現実味を与えている埋蔵金といえるでしょう。
5位:山下財宝
山下財宝は、第二次世界大戦末期に日本軍がフィリピンから持ち帰ったとされる財宝です。
山下奉文大将の名前から「山下財宝」と呼ばれていますが、日本国内にも一部が隠されたという説があります。
特に九州や四国の山中に埋められたという噂が根強く、戦後まもなくから探索が行われてきました。
旧日本軍の関係者による証言もあるなど、山下財宝の埋蔵金伝説には他の埋蔵金伝説とは異なり、比較的現実味があるといえるでしょう。
- おたからや査定員のコメント
ただし、この財宝については国際的な問題も含んでいます。単純な宝探しとは言えない側面がありますが、戦争の記憶とともに語り継がれる埋蔵金伝説として、多くの人々の関心を集め続けているのは事実でしょう。

実際に発見された日本の埋蔵金事例とは

伝説として語り継がれる埋蔵金ですが、実際に発見された事例も存在します。
これらの発見は偶然によるものですが、日本の地下にはまだ多くの埋蔵金が眠っている可能性を示唆しているでしょう。
戦後最大規模の埋蔵金の発見
1963年に東京都中央区新川の日清製油本社ビル改築工事現場から、天保小判1,900枚と天保二朱金約78,000枚が発見された事例が実際にあります。
これは戦後日本で発見された埋蔵金としては過去最大規模とされており、当時の時価で約6,000万円に相当し、戦後日本で発見された埋蔵金としては最大の発見と言われています。
埋蔵金の発見後、調査が行われ、江戸時代に酒問屋を営んでいた鹿島屋の9代目が埋めたものと判明しその子孫に返還されました。
工事中の作業員が埋蔵金を発見
1956年、銀座6丁目に位置する小松ストアー(現ギンザコマツ)の本館改装工事中に埋蔵金が発見されました。
工事現場から出た土が江東区深川の埋立地へ運ばれ、その土を整地していた作業員が小判を見つけたのです。
発見された宝物は、慶長小判・正徳小判・享保小判の3種類、合計208枚と、慶長・正徳・乾字・享保の一分金60枚。これらは江戸期の小判の中でも金純度80%以上という非常に貴重なものといえるでしょう。
当時の小松ストアー創業者・小坂武雄氏は迅速に所有権を放棄し、これらの小判は「埋蔵文化財」として国へ寄贈。現在も東京国立博物館(上野)にて保管されています。
武田家の財宝を発見
1971年、山梨県勝沼町(現甲州市)において、ぶどう栽培用の穴掘り作業中に、多数の古銭と金塊が掘り出されました。
この発見場所は甲府盆地東端の交通の要所で、武田信玄の弟・信友の館跡が近隣にあったと伝えられています。
発掘された財宝は、浮草の葉のような細長い形をした蛭藻金2点、碁石金18点、そして中国からの渡来銅銭約5,000点以上。これらの金貨は戦国時代の甲州金と特定され、15世紀後半に埋められたものと推測されています。
この貴重な埋蔵金は長らく個人が所有していましたが、2011年(平成23年)に甲州金および埋蔵銭貨2,953点が山梨県立博物館に寄贈されています。
政府と埋蔵金が結びつけられる理由とは

埋蔵金という言葉は、地中の財宝だけでなく、政府の財政に関する文脈でも使われることがあります。
霞が関埋蔵金とは
霞が関埋蔵金とは、政府の特別会計に蓄積された余剰金を指す俗称です。2000年代後半に政治的な議論の中で注目され、一般的にも知られるようになりました。
各省庁が管理する特別会計には、使われずに積み上がった資金があるとされています。これを一般会計に繰り入れることで、財政再建や政策実現の財源にできるという主張がありました。
ただし、これらの資金の多くは将来の支出に備えたものであり、自由に使えるわけではないという反論もあります。
埋蔵金という表現は適切ではないかもしれませんが、より効率的な財政運営の余地があると考える人々が霞が関埋蔵金と呼ぶようになったといえるでしょう。
政府の公式見解
政府は「年金積立金などは将来の給付に備えたものであり、特別会計の剰余金は既に使途が決まっているものが多い」という見解を示しています。
ただし、無駄な積立金や不要な剰余金については適切に一般会計に繰り入れる方針も示しており、実際に毎年、特別会計から一般会計への繰入れは行われています。
埋蔵金という言葉が独り歩きしている面もありますが、財政の透明性向上と効率化は重要な課題として認識されている側面もあるといえるでしょう。
まとめ
日本の埋蔵金は、歴史のロマンと現実が交錯する魅力的なテーマです。
徳川埋蔵金をはじめとする有名な伝説は、今なお多くの人々を魅了し続けています。実際に小判や古銭が発見される事例もあり、地中に眠る財宝への期待は決して幻想ではありません。
伝説と現実、ロマンと実益が入り混じる埋蔵金の世界は、これからも人々の関心を集め続けることでしょう。
- 関連記事はこちら
・金価格が2倍になる?今後の相場予想や売り・買い時まで徹底解説
「おたからや」での「大判・小判」の参考買取価格
「おたからや」での「大判・小判」の参考買取価格は下記の通りです。
| 画像 | 商品名 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
 |
20金(K20)慶長小判 みちのく銀行 西暦2000年記念 | 253,200円 |
 |
24金(K24)小判 | 1,722,200円 |
 |
24金(K24)純金大判 | 2,576,400円 |
 |
24金 (K24) 伊勢神宮第六十回御遷宮記念公式小判 | 1,546,900円 |
※状態や付属品の有無、時期によって買取価格が異なるため、詳細はお問い合わせください。
「おたからや」では、金の買取価格を変動する相場や市場の需要に基づき、適切に判断しています。査定額に最も影響するのは、金の純度と重量です。24金に近いほど、また重さがあるほど、より高い評価が期待できます。
次に重要なのは、地金の形状や種類です。インゴットや金貨のように整った形状のものは需要が高く、評価につながりやすい傾向があります。
その他、刻印の有無、発行元の信頼性、保管状態なども査定のポイントになります。「おたからや」では経験豊かな査定士が、これらを総合的に評価したうえで納得の価格をご案内しています。
- おたからや査定員のコメント
金は世界情勢や為替の影響を受けながらも、長期的には安定した資産として高い需要を保ち続ける貴金属です。
インゴットやコインはもちろん、刻印のないチェーンや折れたアクセサリーでも純度と重量が確かであれば確かな価値があります。
「おたからや」では、世界51カ国との取引実績による信頼があり、最新の国際相場をリアルタイムで反映しつつ、メッキ品や金張りとの判別も含めて一点ずつ丁寧に査定し、余計な手数料を差し引かずに高水準の買取価格のご提示が可能です。
ご自宅に眠っているインゴットやジュエリーの切れ端などがございましたら、付属品の有無にかかわらずまずは無料査定だけでもお気軽にご利用ください。

金の買取なら「おたからや」
「おたからや」では、インゴットや金貨、喜平ネックレスから刻印の薄れたリングや片方だけのピアスまで、あらゆる金製品を専門鑑定士がその場で純度・重量を測定し、当日の地金相場を反映した公正な価格をご提示します。
また、全国1,640店舗以上のネットワークを活かし、お客様のご都合に合わせた買取方法をご提供。店頭買取はもちろん、出張買取やオンライン査定にも対応しており、大切な金製品を安心してお任せいただける体制を整えています。
江戸時代から変わらぬ価値を持つ金。その価値を最大限に活かすなら、ぜひおたからやにご相談ください。
おたからやの金買取
査定員の紹介
伊東 査定員

-
趣味
ショッピング
-
好きな言葉
有言実行
-
好きなブランド
ハリーウィンストン
-
過去の買取品例
おりん、インゴット
初めまして。査定員の伊東と申します。 おたからやでは金の買取をする際に、今日の金の1gの買取相場を基に、デザイン性などをプラスで評価して高価買取を行っております。過去に1万点以上の査定をさせていただきましたが、とても多くのお客様に想像以上の金額になったと喜んでいただきました。また、おたからやでは、すべての店舗に比重計を完備しているため、金の含有量を正確に測定することができます。 金額はもちろんのこと、接客も最高のおもてなしができるように心がけております。私共はお品物だけではなくお客様一人ひとりの思いに寄り添い満足して帰っていただけるように丁寧な説明を致します。誠心誠意対応させていただきますので、是非おたからやのご利用をお待ちしております。
その他の査定員紹介はこちら金を高く売るためのコツは、「金の価格が高いときに売ること」と「高値で買い取ってくれる専門店に売ること」です。金の価格は現在非常に高騰しているため、売却にはベストなタイミングといえます。
金の高価買取はおたからやにお任せください。
関連記事
タグ一覧
- #4℃
- #A.ランゲ&ゾーネ
- #GMTマスター
- #IWC
- #K10(10金)
- #K14(14金)
- #K22(22金)
- #K24(純金)
- #MCM
- #Van Cleef & Arpels
- #アクアノート
- #アクアマリン
- #アメジスト
- #アルハンブラ
- #アルマーニ
- #アンティーク時計
- #イエローゴールド
- #インカローズ
- #ヴァシュロンコンスタンタン
- #ヴァレンティノ
- #ヴァンクリーフ&アーペル
- #エアキング
- #エクスプローラー
- #エメラルド
- #エルメス
- #エルメス(時計)
- #オーデマ ピゲ
- #オパール
- #オメガ
- #お酒
- #ガーネット
- #カイヤナイト
- #カルティエ
- #カルティエ(時計)
- #グッチ
- #グリーンゴールド
- #クロエ
- #クロムハーツ
- #クンツァイト
- #ケイトスペード
- #ケリー
- #コーチ
- #ゴヤール
- #サファイア
- #サブマリーナー
- #サマンサタバサ
- #サンローラン
- #シードゥエラー
- #ジェイコブ
- #シチズン
- #シトリン
- #ジバンシィ
- #ジミーチュウ
- #ジャガールクルト
- #シャネル
- #シャネル(時計)
- #ジュエリー
- #ジュエリー買取
- #ショーメ
- #ショパール(時計)
- #スカイドゥエラー
- #スピネル
- #スフェーン
- #セイコー
- #ゼニス
- #セリーヌ
- #その他
- #ターコイズ
- #ターノグラフ
- #ダイヤモンド
- #タグ・ホイヤー
- #タンザナイト
- #チェリーニ
- #チューダー
- #ディオール
- #ティソ
- #デイデイト
- #デイトジャスト
- #デイトナ
- #ティファニー
- #ティファニー
- #トリーバーチ
- #トルマリン
- #ノーチラス
- #バーキン
- #バーバリー
- #パテック フィリップ
- #パネライ
- #ハミルトン
- #ハリーウィンストン
- #ハリーウィンストン(時計)
- #バレンシアガ
- #ピーカブー
- #ピアジェ
- #ピコタン
- #ピンクゴールド
- #フェンディ
- #ブライトリング
- #プラダ
- #プラチナ
- #フランクミュラー
- #ブランド品
- #ブランド品買取
- #ブランド時計
- #ブランパン
- #ブルガリ
- #ブルガリ(時計)
- #ブレゲ
- #ペリドット
- #ボーム&メルシェ
- #ボッテガヴェネタ
- #ポメラート
- #ホワイトゴールド
- #マークジェイコブス
- #マトラッセ
- #ミュウミュウ
- #ミルガウス
- #メイプルリーフ金貨
- #モーブッサン
- #ヨットマスター
- #リシャールミル
- #ルイ・ヴィトン
- #ルビー
- #レッドゴールド
- #ロエベ
- #ロレックス
- #ロンシャン
- #ロンジン
- #出張買取
- #地金
- #宝石・ジュエリー
- #宝石買取
- #時計
- #珊瑚(サンゴ)
- #相続・遺品
- #真珠・パール
- #色石
- #財布
- #金
- #金・プラチナ・貴金属
- #金アクセサリー
- #金インゴット
- #金の純度
- #金価格・相場
- #金歯
- #金縁メガネ
- #金貨
- #金買取
- #銀
- #銀貨
- #香水

知りたくありませんか?
「おたからや」が

写真1枚で査定できます!ご相談だけでも大歓迎!





































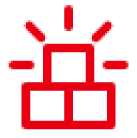

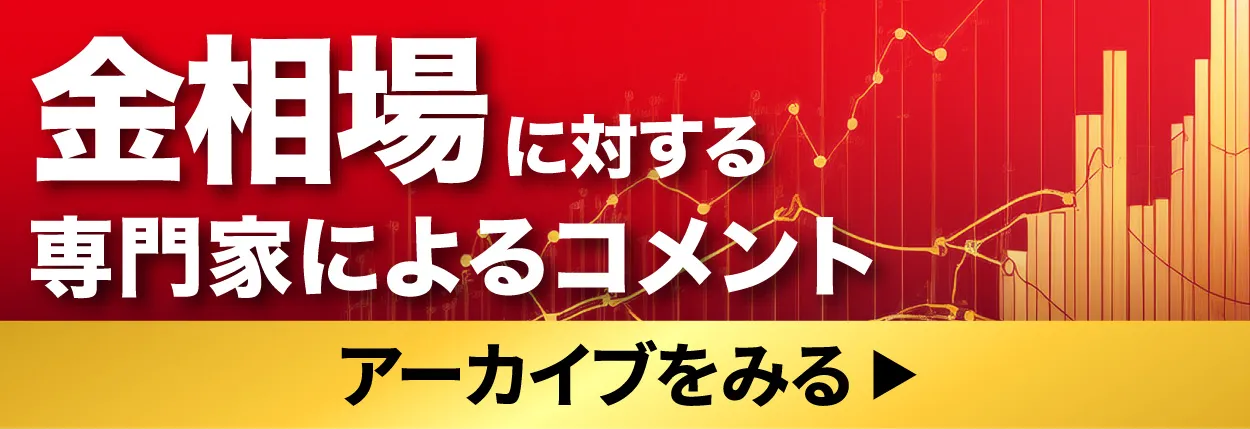
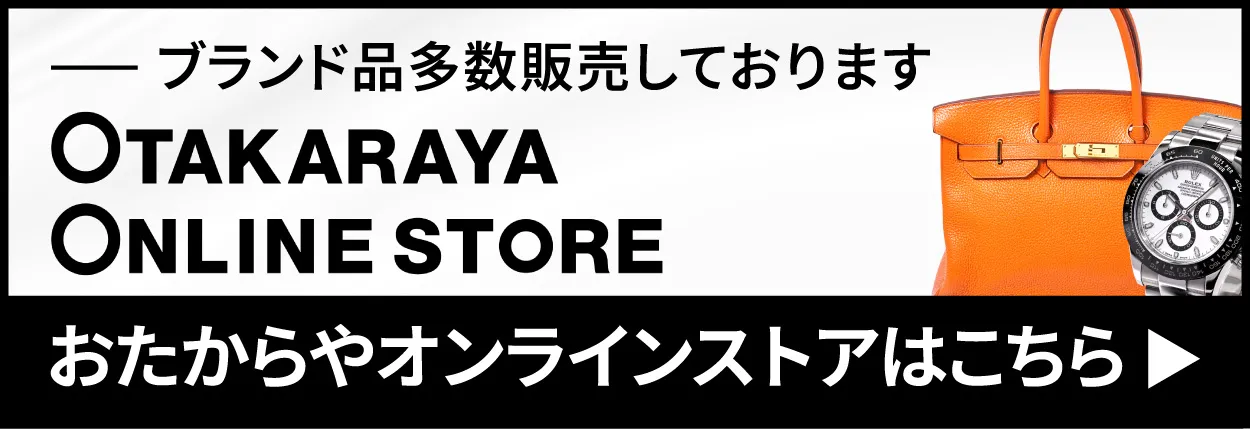
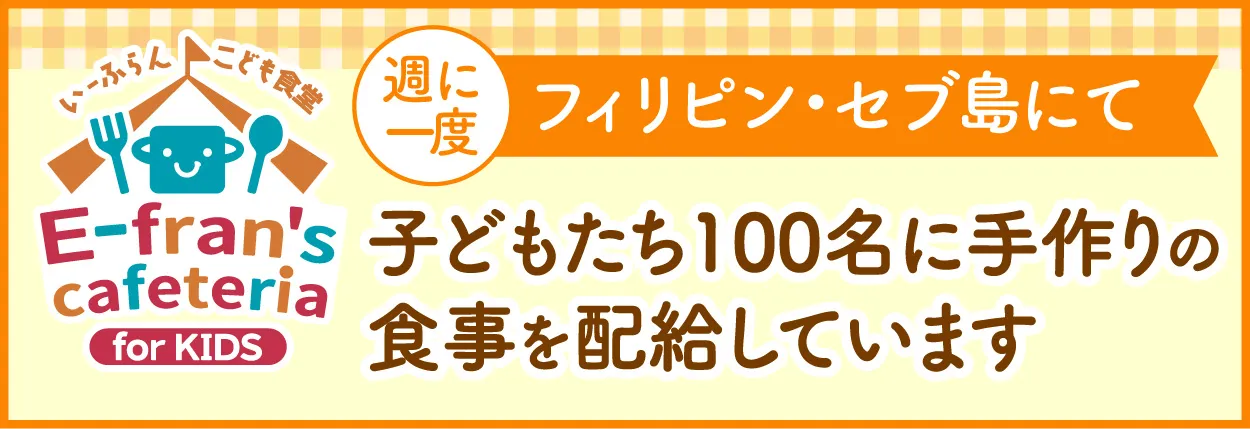

 金・インゴット買取
金・インゴット買取 プラチナ買取
プラチナ買取 金のインゴット買取
金のインゴット買取 24K(24金)買取
24K(24金)買取 18金(18K)買取
18金(18K)買取 バッグ・ブランド品買取
バッグ・ブランド品買取 時計買取
時計買取 宝石・ジュエリー買取
宝石・ジュエリー買取 ダイヤモンド買取
ダイヤモンド買取 真珠・パール買取
真珠・パール買取 サファイア買取
サファイア買取 エメラルド買取
エメラルド買取 ルビー買取
ルビー買取 喜平買取
喜平買取 メイプルリーフ金貨買取
メイプルリーフ金貨買取 金貨・銀貨買取
金貨・銀貨買取 大判・小判買取
大判・小判買取 硬貨・紙幣買取
硬貨・紙幣買取 切手買取
切手買取 カメラ買取
カメラ買取 着物買取
着物買取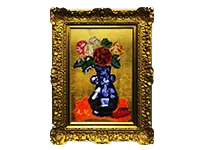 絵画・掛け軸・美術品買取
絵画・掛け軸・美術品買取 香木買取
香木買取 車買取
車買取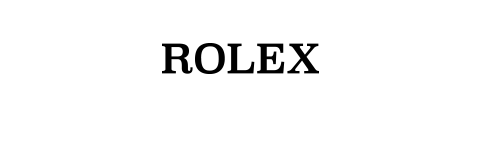 ロレックス買取
ロレックス買取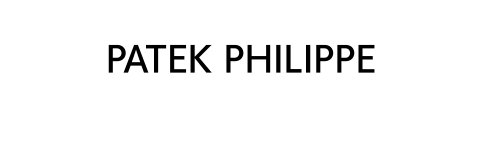 パテックフィリップ買取
パテックフィリップ買取 オーデマピゲ買取
オーデマピゲ買取 ヴァシュロン コンスタンタン買取
ヴァシュロン コンスタンタン買取 オメガ買取
オメガ買取 ブレゲ買取
ブレゲ買取 エルメス買取
エルメス買取 ルイ・ヴィトン買取
ルイ・ヴィトン買取 シャネル買取
シャネル買取 セリーヌ買取
セリーヌ買取 カルティエ買取
カルティエ買取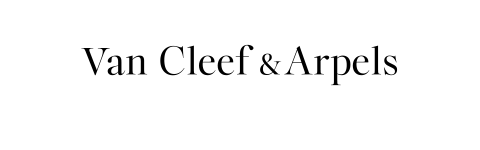 ヴァンクリーフ&アーペル買取
ヴァンクリーフ&アーペル買取 ティファニー買取
ティファニー買取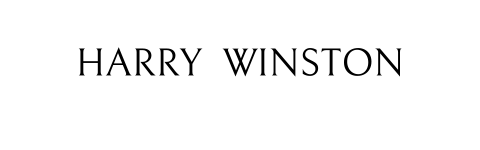 ハリー・ウィンストン買取
ハリー・ウィンストン買取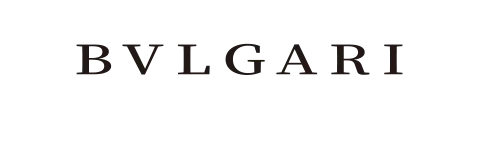 ブルガリ買取
ブルガリ買取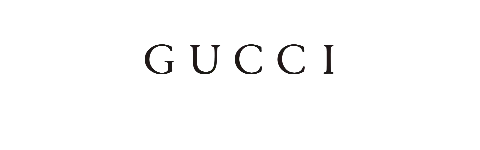 グッチ買取
グッチ買取
 ご相談・お申込みはこちら
ご相談・お申込みはこちら