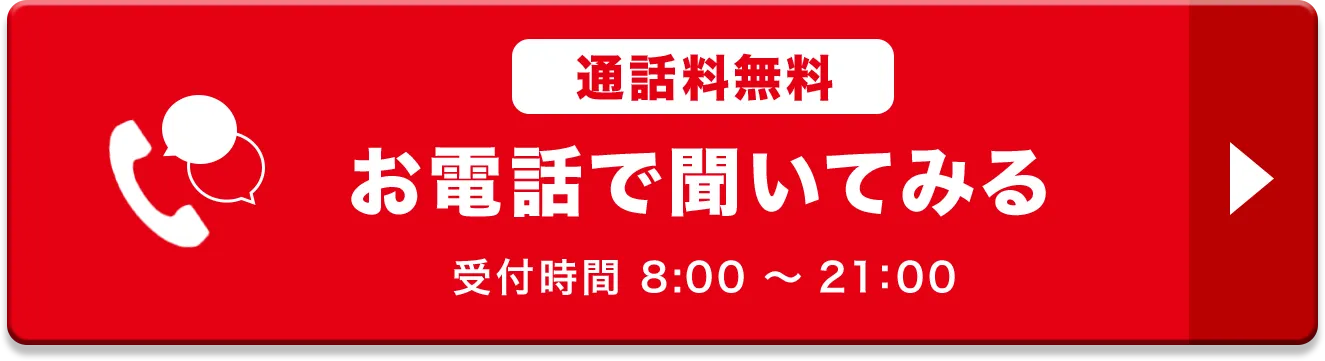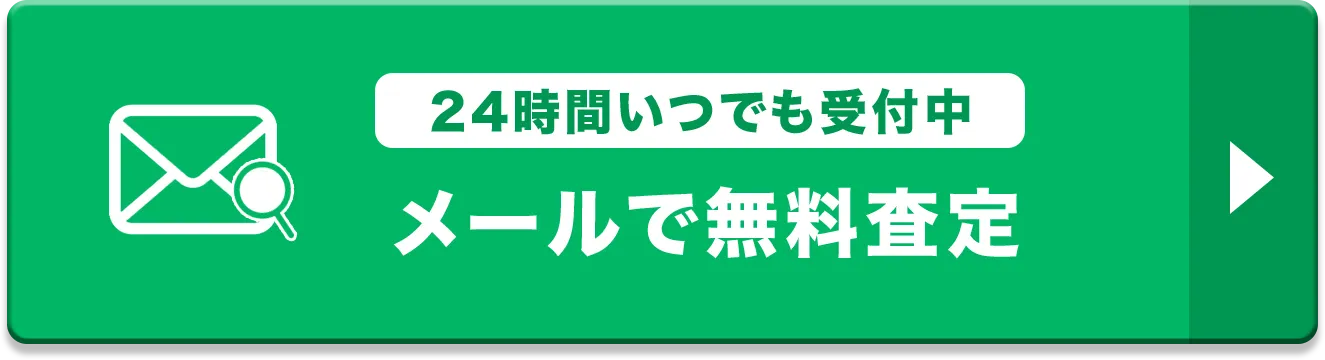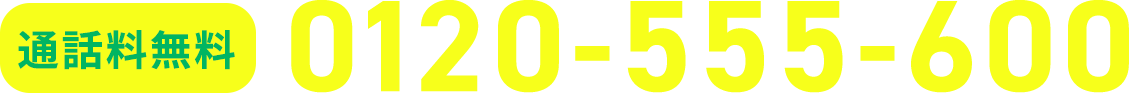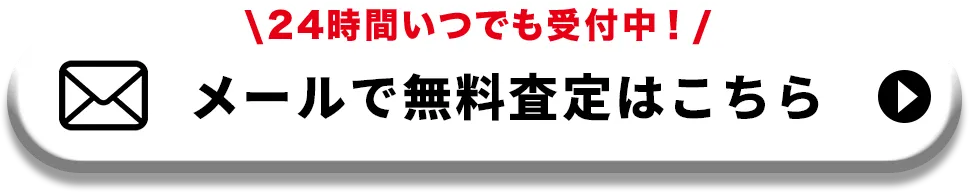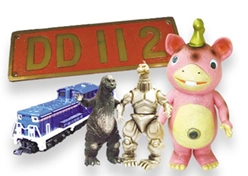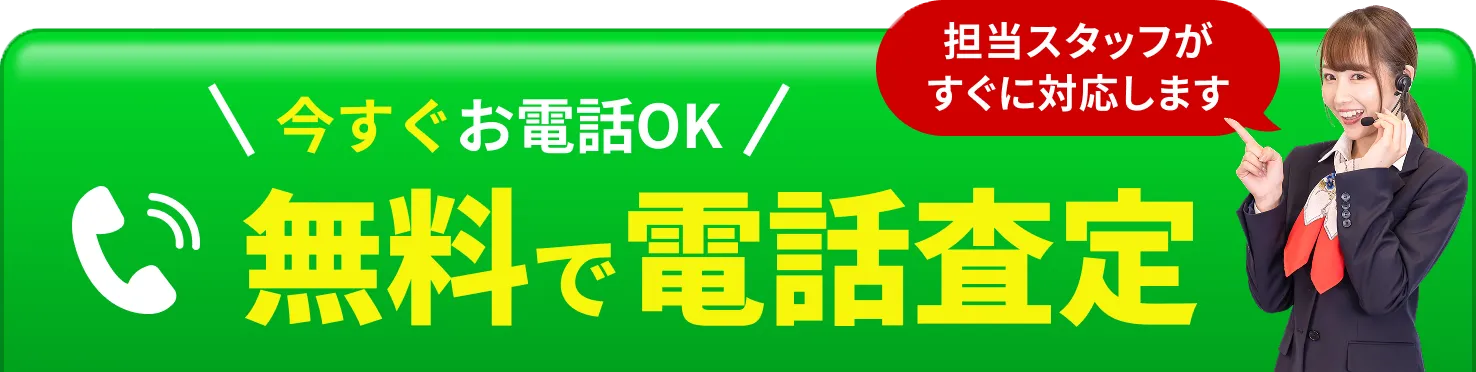富本銭と和同開珎の違いとは?概要から時代背景まで徹底解説

※下記の画像は全てイメージです
富本銭と和同開珎は、ともに古代日本で鋳造された銅銭ながら、発行年代・流通範囲・国家財政への関与が大きく異なるものです。今回は富本銭が天武天皇下で試行的に造られた背景と、和同開珎が和銅元年に制度化された経緯をご紹介いたします。
さらに両者のデザインや材質の違い、出土数から見える流通の実態、実物が見学できる博物館情報、査定時の評価ポイントまでを解説します。
この記事を読めば、古銭に対する理解が深まり、売買する際にも適正な取引ができるようになるので、ぜひ最後までご覧ください。

Contents
富本銭と和同開珎とは?概要と背景を整理

富本銭(ふほんせん)と和同開珎(わどうかいちん)は、いずれも日本の古代に登場した貨幣ですが、発行された時期や背景には大きな違いがあります。
この記事ではそれぞれの概要(発行目的)と歴史的な位置づけを整理します。
- 関連記事はこちら
・金貨の主な種類を徹底解説|特徴・違い・価値の見極め方をわかりやすく紹介
富本銭とは?
富本銭(ふほんせん)は、日本で最初に鋳造されたとされる古代の銅貨で、現在では和同開珎よりも早いとする説が有力です。
683年、天武天皇の時代に「銅銭を用い、銀銭を用いないように」との詔(みことのり)が発せられ、この方針に基づき、国家が主導して発行したと考えられています。当時は藤原京(ふじわらきょう)の建設が進められており、市場整備と物流効率化のために貨幣制度が必要とされました。
富本銭の表面には「富本」の二文字が刻まれ、日本独自の意匠とされています。裏面には北斗七星を模した七曜文(しちようもん)が施され、当時の信仰や思想と結びついた、独特なデザインが特徴とされています。
和同開珎とは?
和同開珎(わどうかいちん)は、708年に発行された日本初の国家主導による制度的な流通貨幣です。
奈良時代、元明天皇の治世に自然銅が発見され、元号が「和銅」に改元されました。その銅を用いて鋳造された和同開珎の「開珎」は、流通の意を表します。
富本銭より後の発行ながら、全国的に流通し制度も整備された最初の貨幣として重要視されています。国家財政の安定や経済発展を図る目的で発行され、社会基盤整備に大きく寄与しました。
なぜ和同開珎が「日本最初の貨幣」とされてきたのか?
和同開珎は発行後、各地で流通し、多数の出土例を残したことから、長く「日本最初の貨幣」とされてきました。
一方、富本銭の存在は知られていたものの、出土数が極めて少なく、用途も不明であったため、通説では和同開珎が最古の貨幣とされていました。
しかし1999年、奈良県の飛鳥池遺跡(あすかいけいせき)から富本銭が大量に出土し、鋳型(いがた)や炉跡(ろせき)も確認されたことから、富本銭がそれよりも前に鋳造された貨幣であることが明らかになりました。現在では、教科書でも「日本最古の貨幣」として富本銭が紹介されています。
- 関連記事はこちら
・地金型金貨とは?初心者向けに地金との違い、日本での歴史、世界の代表金貨、投資メリット・デメリット、買取価格や高く売るコツ、保管・税金まで徹底解説
富本銭と和同開珎のデザイン・流通・用途の相違点

富本銭と和同開珎は形状こそ似ていますが、刻まれた文字や材質、用途には大きな違いがあります。以下では、その具体的な相違点を詳しく見ていきます。
| 比較項目 | 富本銭 | 和同開珎 |
|---|---|---|
| 形状 | 円形方孔 | 円形方孔 |
| 大きさ | ほぼ同等 | ほぼ同等 |
| 表面の刻字 | 「富本」の二文字 | 「和同開珎」の四文字 |
| 裏面の意匠 | 七曜文(星の文様)あり | 文様なし |
| 主な材質 | アンチモンを含む銅合金 | 初期は銅合金、後に錫・鉛を含む青銅 |
| 流通範囲 | 限定的(主に飛鳥地域) | 全国規模 |
| 出土状況 | 飛鳥池遺跡に集中 | 各地で多数出土(奈良県だけで2,000枚以上) |
| 主な用途 | 実用貨幣説のほか、儀礼用・厭勝銭説あり | 実用貨幣として流通 |
デザイン・材質の違い
富本銭と和同開珎はいずれも円形で中央に四角い穴が開いた「円形方孔(えんけいほうこう)」の形式を採用しており、大きさもほぼ同じ大きさです。
ただし、表面の刻字や意匠(いしょう)には明確な違いがあります。富本銭は表に「富本」の二文字が鋳出され、裏面には七曜文(しちようもん)と呼ばれる星の文様が施されました。
一方の和同開珎は、「和同開珎」の四文字から成る漢字銭文(かんじせんもん)を持ち、唐の開元通宝(かいげんつうほう)を模倣した形式であり、通常、裏面に文様は施されていません。材質にも差があり、富本銭はアンチモンを含んだ銅合金で作られ、鋳造しやすいよう工夫されていました。
和同開珎も当初は同様の材質でしたが、次第に錫(すず)や鉛を含む青銅へと移行し、後期には鉛(なまり)の割合が高くなるなど、品質に変化が生じました。
- 関連記事はこちら
・金相場の歴史からわかる流れとは?30年の価格推移と高騰理由について解説
流通状況と用途の違い
富本銭と和同開珎の間には、流通状況に大きな差があります。
和同開珎は全国規模での流通を意図して発行され、各地で多数出土しています。奈良県だけでも2,000枚以上が確認され、広く流通していたと考えられます。
一方、富本銭は飛鳥池遺跡で多く出土したものの、他地域では少なく、日常的な流通品としての実用性には疑問が残ります。また、厭勝銭(えんしょうせん)や儀礼用とする説もあります。
- おたからや査定員のコメント
古銭は見た目が似ていても、実際の流通状況や用途によって価値が大きく異なります。
特に富本銭のように実用性や用途がはっきりしない銭は、学術的価値の面で高く評価されます。
一方、和同開珎のように広く流通した古銭は、出土例の多さや保存状態、刻字の明瞭さが査定の重要な基準になります。
「おたからや」では、用途の違いや時代背景をふまえ、丁寧に査定致しますので、安心してご相談ください。

富本銭と和同開珎はどこで発見された?出土場所と資料価値

富本銭と和同開珎は、それぞれ異なる地域から発見されており、出土状況は、それぞれの貨幣の流通や役割を示唆しています。以下では、それぞれの発見場所と資料的価値について解説します。
富本銭の主な出土地域と資料的意義
富本銭の出土は主に奈良県明日香村(あすかむら)の飛鳥池遺跡に集中しています。この遺跡では鋳造工房跡とみられる遺構が発見され、鋳型や未完成の銭、坩堝(るつぼ)などが多数、一括して出土しました。これにより、7世紀末の日本において、国家主導の本格的な貨幣鋳造が実施されていたことが実証されました。
富本銭は、唐の制度を参考にしつつも、独自の工夫を加えて製造されたことが、出土資料から確認されています。2023年には出土品と鋳造関連の遺物が国の重要文化財に指定され、その歴史的価値が広く認められました。
富本銭の発見は、日本最古の貨幣としての地位を確立させただけでなく、古代の経済政策や鋳造技術の水準解明に大きく貢献しています。
和同開珎の出土数・全国流通との関係
和同開珎は富本銭と比べて出土例が非常に多く、奈良県内の231か所の遺跡から2,000枚以上が出土し、他地域でも多数が発見されています。
分布は東北から九州に及び、広範な流通を裏付けています。埋蔵銭(まいぞうせん)として大量に保存されていた例も多く、私的に蓄蔵されていた可能性が指摘されています。
一方、富本銭は出土地域が限られ、広域流通の形跡はありません。こうした出土地の差異は、両者の流通規模の違いを如実に物語っています。
富本銭・和同開珎のあとには何が続いた?日本の貨幣制度の流れ

富本銭と和同開珎の発行を起点に、日本の貨幣制度は大きな変化を遂げていきました。以下では、両者の後に続く貨幣や制度の変遷をたどります。
- 関連記事はこちら
・金の価値にまつわる世界や日本の歴史を解説!金の価値を左右するポイントも
富本銭・和同開珎の後に登場した貨幣とは?
富本銭・和同開珎に続き、奈良時代から平安時代にかけて、国家による公式銅銭の発行が続きました。その後、万年通宝(まんねんつうほう)・神功開宝(じんぐうかいほう)などの新たな銅銭が順次発行され、最後の乾元大宝(958年)までに、合計12種類の公式銭(皇朝十二銭)が鋳造されました。
しかし、10世紀後半には貨幣鋳造が途絶え、987年には朝廷が銭貨の流通停止を通達しました。皇朝十二銭の発行後、日本の貨幣制度は一時的に中断期に入りました。その後、中世には中国から輸入された宋銭や明銭が流通し、国内での貨幣鋳造は行われませんでした。
やがて戦国時代末期から各地の大名が私鋳銭を発行するようになり、近世江戸時代には再び全国統一の貨幣制度が整備されました。
- 関連記事はこちら
・天保通宝の価値はどれくらい?種類ごとの特徴や高く売る方法を解説
寛永通宝との比較で見る貨幣制度の変遷
寛永通宝(江戸時代)と比較すると、古代の貨幣制度との違いが明確に浮かび上がります。古代の銭貨経済は国家による実験的導入期で、銅銭のみが限定的に流通するにとどまりました。
一方、江戸時代は金・銀・銭の三貨制度が確立し、貨幣が全国に浸透して安定した信用を得ました。寛永通宝は発行枚数が極めて多く、全国津々浦々にまで行き渡りました。古代銭が改鋳を重ねた結果、品質が低下し信用を失ったのに対し、江戸の貨幣は統一規格を維持し、人々の日常に定着した点で対照的です。
こうした比較から、日本の貨幣制度は、富本銭の黎明期(れいめいき)、和同開珎の確立期を経て、寛永通宝による成熟期へと発展したことが示されています。
- 関連記事はこちら
・江戸時代の三貨制度とは?金・銀・銭の役割と流通の実像をわかりやすく解説
富本銭・和同開珎は国家制度にどのように関与したか?
富本銭・和同開珎の発行はいずれも律令国家の政策として実施されました。富本銭は689年に鋳銭司(ちゅうせんし)が設置され、国家の経済基盤を整えるべく鋳造されたものです。
和同開珎も平城京造営の財源確保を目的に鋳造され、711年には蓄銭叙位令(ちくせんじょいれい)が出されるなど貨幣流通が国家財政に組み込まれました。
このように、古代の貨幣制度は中央政府による経済統制策の一環であり、富本銭と和同開珎はその先駆けと位置づけられます。その後、古代の貨幣政策はいったん挫折しましたが、富本銭と和同開珎の発行によって芽生えた貨幣経済の概念は、中世から近世へと受け継がれていきました。
富本銭・和同開珎が見られる博物館とおすすめ資料

富本銭や和同開珎の実物を観覧することで、古代日本の貨幣制度や歴史的背景への理解を深めることができます。以下では、これらの貨幣が展示されている博物館や、関連資料をご紹介します。
両貨幣が見られる博物館・展示施設一覧
両貨幣が見られる博物館・展示施設には下記の5つの施設があります
- 奈良文化財研究所 飛鳥資料館
- 奈良県立万葉文化館
- 東京国立博物館
- 日本銀行貨幣博物館
- 高森町歴史民俗資料館
奈良文化財研究所 飛鳥資料館(奈良県明日香村)
飛鳥池遺跡から出土した富本銭や鋳造関連の遺物を常設展示している資料館です。
国家主導による貨幣鋳造の実態を示す鋳型・坩堝・未完成品などが公開されており、富本銭の歴史的背景を実物から学ぶことができます。古代貨幣制度の成立過程を視覚的に理解できる貴重な展示施設です。
奈良県立万葉文化館(奈良県明日香村)
万葉集と古代文化をテーマとする博物館で、常設展示のほか、富本銭・和同開珎に関連する企画展を開催することがあります。
飛鳥時代の政治・経済背景とあわせて、古代貨幣の役割や意義を紹介しています。映像資料やパネル展示も充実し、初心者にもわかりやすい構成です。
東京国立博物館(東京都台東区)
本館の考古展示室にて、富本銭や和同開珎をはじめとする古代日本の貨幣や金属器を常設展示しています。
実物を通じて貨幣の意匠や材質の違いを比較することができ、古代国家の制度や文化に触れることができます。日本最古級の貨幣を首都圏で見られる数少ない場所です。
日本銀行貨幣博物館(東京都中央区)
日本銀行が運営する博物館で、日本の貨幣の歴史を古代から現代まで体系的に展示しています。
富本銭や和同開珎も収蔵され、貨幣制度の変遷やその社会的意義について学べます。パネルや模型、デジタル展示も充実しており、金融や経済の視点からも古代貨幣を捉えることができます。
高森町歴史民俗資料館(長野県高森町)
町内の古墳から出土した富本銭・和同開珎をはじめ、土器や装身具など地域の考古資料を展示しています。
地方でも古代貨幣が流通していた可能性を示す貴重な出土例として注目されています。地域史とともに古代国家の影響の広がりを実感できる資料館です。
富本銭・和同開珎を知りたい方におすすめの関連書籍・資料
富本銭・和同開珎について知りたい方におすすめの関連書籍・資料には下記の2つがあります。
- 今村啓爾『日本古代貨幣の創出 無文銀銭・富本銭・和同銭』
- 高木久史『通貨の日本史 無文銀銭、富本銭から電子マネーまで』
今村啓爾『日本古代貨幣の創出 無文銀銭・富本銭・和同銭』(講談社学術文庫)
富本銭や無文銀銭の発見をもとに、日本最古の貨幣制度がどのように成立したかを探る一冊です。考古学的な調査結果と文献資料の両面から、日本古代の経済構造や制度の変遷が丁寧に論じられています。
内容は専門的ながら構成が明快で、知識を深めたい読者にとって非常に読み応えのある一冊です。
参考:今村啓爾『日本古代貨幣の創出 無文銀銭・富本銭・和同銭』
高木久史『通貨の日本史 無文銀銭、富本銭から電子マネーまで』(中公新書)
本書は、古代から現代までの日本通貨の歴史を通史的に整理しており、時代ごとの制度や背景を幅広く学べる内容です。特に、富本銭の発見によって教科書の記述がどのように変化したのかにも言及されており、歴史の見直しがどのように行われたかが理解できます。
文体は平易で、通貨制度に初めて触れる方でも無理なく理解でき、基礎からしっかりと学びを深められる構成です。
参考:高木久史『通貨の日本史 無文銀銭、富本銭から電子マネーまで』
古銭に関するよくある質問
古銭は日本の貨幣史を理解するうえで重要な資料であり、現代の収集対象としても人気があります。
本Q&Aでは、「富本銭」「和同開珎」「寛永通宝」といった代表的な古銭について、歴史的背景や流通の実態、価値や違いを解説します。
Q. 和同開珎と富本銭の違いは何ですか?
A.
和同開珎は708年(和銅元年)に政府が鋳造・発行した日本最初の流通貨幣として位置づけられ、国家による本格的な貨幣制度の始まりを示します。
一方、富本銭は683年頃に鋳造されたと推定される最古の銭貨で、出土例は確認されていますが、広く流通した証拠は乏しく、厭勝銭(まじない用銭)とする説もあります。年代・流通の実態・制度性が主な違いです。
Q. 富本銭が流通しなかった理由は何ですか?
A.
富本銭が広く流通しなかった背景には、当時の経済構造と貨幣制度の未整備が影響しています。
- 無文銀銭が既に通用し銀価基準が定着
- 富本銭は銅製で価値尺度が不安定
- 発行量が少なく流通網が未整備
- 国家的流通政策や法令が未整備
これらの要素が重なり、富本銭は試験的な発行にとどまりました。鋳造量や交換比率を定める法令、徴税システムが整備され、銅銭の信用が固まったのは和同開珎の登場以降です。
Q. 富本銭の価値はいくらですか?
A.
富本銭は現存例が非常に少なく、一般的な流通価格が存在しないため、明確な市場価値は定まっていません。
一部の専門家や収集家の間では博物館展示レベルの文化財的価値が高く、仮に取引されても極めて高額になる可能性があるとされますが、実際の市場取引例はほとんど見られません。
Q. 寛永通宝と和同開珎の違いは何ですか?
A.
和同開珎は奈良時代に発行された古代日本の流通貨幣で、国家の貨幣制度の開始点として重要です。
一方、寛永通宝は江戸時代(17世紀初頭〜)に幕府が発行した銅・鉄・真鍮を使用した貨幣であり、数百年にわたって全国的に使用されました。時代背景・発行主体・流通期間が大きく異なり、和同開珎は初期貨幣制度の象徴、寛永通宝は安定した通貨経済の代表例といえます。
Q. 富本銭で一番古いものは?
A.
富本銭は683年頃(天武天皇12年頃)に鋳造されたと推定され、日本で確認されている最古の銅銭(古銭)と考えられています。
平城京跡や飛鳥池遺跡などの地層から出土した富本銭は、和同開珎(708年)より古い時期のものと確認され、日本貨幣史における初期鋳造銅銭として位置付けられています。なお、「富本銭」の出土例は限られており、年代は考古学的な推定に基づくものです。
Q. 和同開珎の本物と偽物の見分け方は?
A.
和同開珎の真贋を見分けるには、刻印の鮮明さ・文字の書体・サイズ・重量・経年変化などが重要なポイントです。本物は銅製で刻印が精巧・自然な摩耗が見られ、刻まれた「和」「同」「開」「珎」の文字が明確です。
一方、偽物は刻印や書体が粗く、サイズ・重量が本物と一致しないこと、多くは材質が異なる安価な金属であることが多い点が特徴です。専門家の鑑定も推奨されます。
Q. 和同開珎が廃れた理由は何ですか?
A.
和同開珎が廃れた主因は、鋳造コストを抑えるため銅の純度が落ち、見た目や重量が発行当初より劣化して信用が薄れたことです。加えて租税や給与が布・米で支払われ続け、貨幣経済が浸透しなかったため人々は携帯性より購買力を重視しました。
さらに流通網や両替制度が未整備で偽銭も横行し、朝廷は維持コストに見合わないと判断して鋳造を停止しました。
九州の銅産地が早くも枯渇傾向となり、原料調達難も拍車を掛けています。結果、数十年で流通は縮小し、米・布による物々交換や流入した宋銭での取引に移り変わっていきました。
Q. 日本で1番古い貨幣は?
A.
研究の進展により、日本で最も古い貨幣として確認されているのは富本銭であり、683年頃の鋳造と推定されています。
従来は708年の和同開珎が最古とされてきましたが、富本銭の出土でその認識が更新されました。ただし、富本銭の流通範囲や、貨幣としての機能をどの程度果たしたかについては議論が残ります。
Q. 富本銭は誰が作ったのか?
A.
富本銭が誰によって制作されたかについては、国家機関による正式な記録が残っておりません。
ただし、奈良時代以前の天武朝期の鋳造と推定されることから、当時の中央政権(天皇・朝廷)が何らかの公式目的で鋳造したと考えられています。しかし、富本銭の性格が貨幣としての流通を目的としたものか、政策的・象徴的なものかは学界で議論が続いています。
Q. 寛永通寳は一枚いくらの価値がありますか?
A.
寛永通宝は種類・鋳造時期・保存状態によって価値が大きく異なるものです。
一般的な後期鋳造の寛永通宝は数十円〜数百円程度が相場ですが、希少な種類や良好な保存状態のものでは数千円〜数万円、場合によって数十万円規模の査定が付くケースもあります。専門的な鑑定により価値が変動するため、査定依頼が推奨されます。
Q. 日本で1番価値が高い硬貨は何ですか?
A.
日本で高価に取引されている硬貨は、江戸〜明治期の金貨・銀貨・丁銀・豆板銀などの希少価値が高いものです。
例えば、宝永三ツ宝豆板銀や元禄丁銀などは高い価値が付くことがあり、コレクター市場で極めて高額で取引される例もあります。これらは希少性・歴史的価値が価格を押し上げています。
- 関連記事はこちら
・価値の高い記念硬貨とは?記念硬貨の定義や高く売るコツなど紹介
・5円玉のレアな年号は何年?希少な5円硬貨の年号やエラー硬貨の価値をご紹介
Q. 10銭は今で言うと何円ですか?
A.
法定上の額面価値としては「10銭=0.1円」に相当しますが、古銭としての価値は額面以上となることがあり、素材や発行年によって数百円〜数千円、稀少種では数万円以上になるケースもあります。
また、歴史的な物価換算では、時代によっては数十円〜数千円相当になるとする試算もあります。
Q. 古銭にはどんな種類がありますか?
A.
古銭は時代・素材・用途に応じて多様な種類があります。
主なものには穴銭(寛永通宝・天保通宝など)、皇朝十二銭(和同開珎等)、近代の金貨・銀貨・補助貨幣(10銭・5銭など)、大判・小判、丁銀・豆板銀などがあり、時代背景や素材によって収集価値・取引価格が異なります。専門カタログ等で種類ごとの相場を確認するのが有効です。
- 関連記事はこちら
Q. 古銭はどうしたらいいですか?
A.
保有している古銭の価値を知るには、専門の古銭買取店や鑑定士に査定を依頼することが基本です。
一般的なリサイクルショップでは価値が正確に評価されない場合があります。知識のある専門店に依頼することで正確な価値判断・保管方法のアドバイス・高価買取の可能性検討が可能です。
Q. 古銭は売れますか?
A.
はい、古銭は買取市場で売却可能です。取引方法としては店頭買取・出張査定があり、希少性や状態によっては高価買取となるケースもあります。
専門知識を持つ業者に査定してもらうことで、本来の価値を評価してもらえる可能性が高まります。
まとめ
富本銭と和同開珎の違いは、発行時期・流通規模・目的において明確です。富本銭は和同開珎よりも古く発行された日本最古の貨幣ですが、流通範囲が限られており、用途も不明な点が残されています。
一方、和同開珎は全国に広く流通し、日本初の本格的な流通貨幣としての役割を果たしました。さらに両貨幣の出土状況や制度的背景を比較することで、日本の貨幣制度の黎明期から成長過程を理解できます。
この記事で得た知識をもとに、ぜひ実物を見学しに博物館へ足を運んでみてはいかがでしょうか。実際に目にすることで、教科書では得られない新たな発見や歴史の奥深さを体感できるはずです。古代日本の経済や文化に触れるきっかけとして、現地での体験はきっと有意義なものになるでしょう。
「おたからや」での古銭の参考買取価格
ここでは、「おたからや」での「古銭」の参考買取価格の一部を紹介します。
| 画像 | 商品名 | 参考買取価格 |
|---|---|---|
 |
天保通宝おまとめ 穴銭 古銭 | 185,320円 |
 |
中国穴銭 おまとめ 古銭 | 170,630円 |
 |
明治二分判金 日本古銭 | 89,280円 |
 |
竜50銭銀貨 竜20銭銀貨 日本古銭 | 52,200円 |
 |
外国古銭 まとめ売り | 45,200円 |
 |
外国古銭 おまとめ | 25,420円 |
※状態や付属品の有無、時期によって買取価格が異なりますので詳細はお問い合わせください。
古銭は根強い人気を持つコレクションアイテムであり、特に歴史的背景や希少性が評価されやすいジャンルです。中でも江戸時代以前のものや発行数が少ない銭貨は、専門家や収集家の間で需要が高まっています。
査定額に最も影響を与えるのは、真贋の判定と希少性です。発行時期や鋳造地域が特定できる場合、価値は大きく評価が高まります。次に重要なのが保存状態で、摩耗や変色が少なく、銘文が判読できるものほど高く評価されます。
さらに、由来が明確な品や発掘記録のある古銭、または鑑定書付きのものは、学術的資料としての価値も加味され、査定額も高く評価されやすくなります。「おたからや」では、こうした多角的な視点から古銭の価値を丁寧に見極めています。
- おたからや査定員のコメント
古銭は単なる古いお金ではなく、その背景には時代ごとの政治体制や流通経済の変化が表れています。
富本銭のように出土数が限られており、用途も特定されていないものから、和同開珎のように国家が制度的に流通させた貨幣まで、査定において注目すべきポイントは多岐にわたります。
「おたからや」では、真贋はもちろん、発行年代、保存状態、そして当時の流通状況に至るまで幅広く評価し、お客様の大切な古銭にふさわしい価格を提示できるよう努めています。
初めての方でも安心してご相談いただける環境を整えておりますので、お手元の古銭が気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。

古銭の買取なら「おたからや」
ご自宅に眠っている古銭、「もしかしたら価値があるかも?」と気になっていませんか?「おたからや」では、古銭に詳しい専門の査定員が一点ずつ丁寧に鑑定し、年代・希少性・保存状態など多角的な視点で価値を見極めます。
たとえ傷や汚れがあっても問題ありません。鑑定書がなくても査定が可能ですので、「本物かどうかわからない」という方もお気軽にご相談ください。
全国1,630店舗以上のネットワークと世界規模の取引ルートを活かし、最新の市場相場に基づいた適正価格をご提示いたします。また、ご来店が難しい方には出張買取やオンライン査定にも対応しております。収集品の整理や相続など、あらゆるご事情に寄り添いながら、安心・丁寧に対応いたします。まずは一度、お気軽にご相談ください。
※本記事は、おたからや広報部の認可を受けて公開しております。
おたからやの金買取
査定員の紹介
伊東 査定員

-
趣味
ショッピング
-
好きな言葉
有言実行
-
好きなブランド
ハリーウィンストン
-
過去の買取品例
おりん、インゴット
初めまして。査定員の伊東と申します。 おたからやでは金の買取をする際に、今日の金の1gの買取相場を基に、デザイン性などをプラスで評価して高価買取を行っております。過去に1万点以上の査定をさせていただきましたが、とても多くのお客様に想像以上の金額になったと喜んでいただきました。また、おたからやでは、すべての店舗に比重計を完備しているため、金の含有量を正確に測定することができます。 金額はもちろんのこと、接客も最高のおもてなしができるように心がけております。私共はお品物だけではなくお客様一人ひとりの思いに寄り添い満足して帰っていただけるように丁寧な説明を致します。誠心誠意対応させていただきますので、是非おたからやのご利用をお待ちしております。
その他の査定員紹介はこちら金を高く売るためのコツは、「金の価格が高いときに売ること」と「高値で買い取ってくれる専門店に売ること」です。金の価格は現在非常に高騰しているため、売却にはベストなタイミングといえます。
金の高価買取はおたからやにお任せください。
関連記事
タグ一覧
- #4℃
- #A.ランゲ&ゾーネ
- #GMTマスター
- #IWC
- #K10(10金)
- #K14(14金)
- #K22(22金)
- #K24(純金)
- #MCM
- #Van Cleef & Arpels
- #アクアノート
- #アクアマリン
- #アメジスト
- #アルハンブラ
- #アルマーニ
- #アンティーク時計
- #イエローゴールド
- #インカローズ
- #ヴァシュロンコンスタンタン
- #ヴァレンティノ
- #ヴァンクリーフ&アーペル
- #エアキング
- #エクスプローラー
- #エメラルド
- #エルメス
- #エルメス(時計)
- #オーデマ ピゲ
- #オパール
- #オメガ
- #お酒
- #ガーネット
- #カイヤナイト
- #カルティエ
- #カルティエ(時計)
- #グッチ
- #グリーンゴールド
- #クロエ
- #クロムハーツ
- #クンツァイト
- #ケイトスペード
- #ケリー
- #コーチ
- #ゴヤール
- #サファイア
- #サブマリーナー
- #サマンサタバサ
- #サンローラン
- #シードゥエラー
- #ジェイコブ
- #シチズン
- #シトリン
- #ジバンシィ
- #ジミーチュウ
- #ジャガールクルト
- #シャネル
- #シャネル(時計)
- #ジュエリー
- #ジュエリー買取
- #ショーメ
- #ショパール(時計)
- #スカイドゥエラー
- #スピネル
- #スフェーン
- #セイコー
- #ゼニス
- #セリーヌ
- #その他
- #ターコイズ
- #ターノグラフ
- #ダイヤモンド
- #タグ・ホイヤー
- #タンザナイト
- #チェリーニ
- #チューダー
- #ディオール
- #ティソ
- #デイデイト
- #デイトジャスト
- #デイトナ
- #ティファニー
- #ティファニー
- #トリーバーチ
- #トルマリン
- #ノーチラス
- #バーキン
- #バーバリー
- #パテック フィリップ
- #パネライ
- #ハミルトン
- #ハリーウィンストン
- #ハリーウィンストン(時計)
- #バレンシアガ
- #ピーカブー
- #ピアジェ
- #ピコタン
- #ピンクゴールド
- #フェンディ
- #ブライトリング
- #プラダ
- #プラチナ
- #フランクミュラー
- #ブランド品
- #ブランド品買取
- #ブランド時計
- #ブランパン
- #ブルガリ
- #ブルガリ(時計)
- #ブレゲ
- #ペリドット
- #ボーム&メルシェ
- #ボッテガヴェネタ
- #ポメラート
- #ホワイトゴールド
- #マークジェイコブス
- #マトラッセ
- #ミュウミュウ
- #ミルガウス
- #メイプルリーフ金貨
- #モーブッサン
- #ヨットマスター
- #リシャールミル
- #ルイ・ヴィトン
- #ルビー
- #レッドゴールド
- #ロエベ
- #ロレックス
- #ロンシャン
- #ロンジン
- #出張買取
- #地金
- #宝石・ジュエリー
- #宝石買取
- #時計
- #珊瑚(サンゴ)
- #相続・遺品
- #真珠・パール
- #色石
- #財布
- #金
- #金・プラチナ・貴金属
- #金アクセサリー
- #金インゴット
- #金の純度
- #金価格・相場
- #金歯
- #金縁メガネ
- #金貨
- #金買取
- #銀
- #銀貨
- #香水

知りたくありませんか?
「おたからや」が

写真1枚で査定できます!ご相談だけでも大歓迎!





































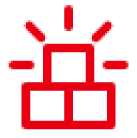

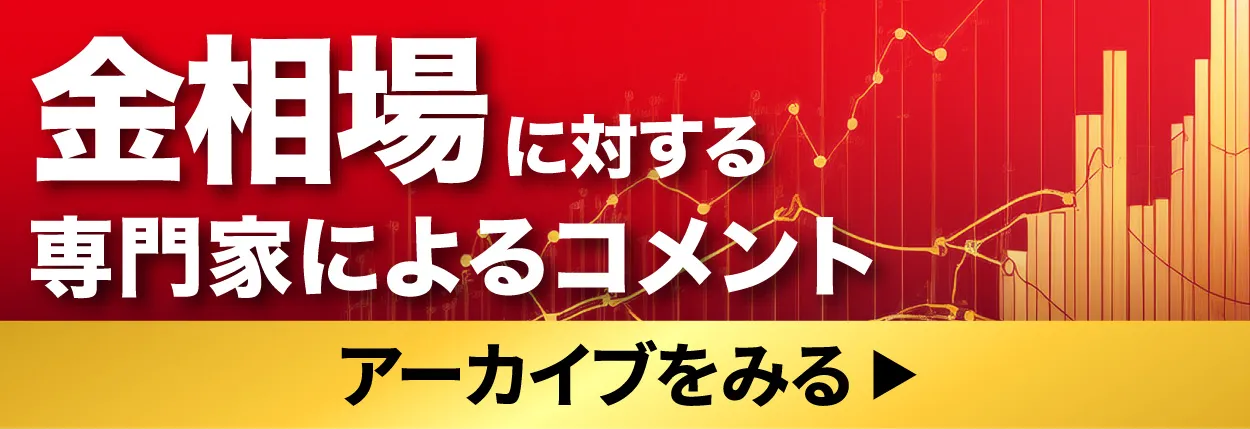
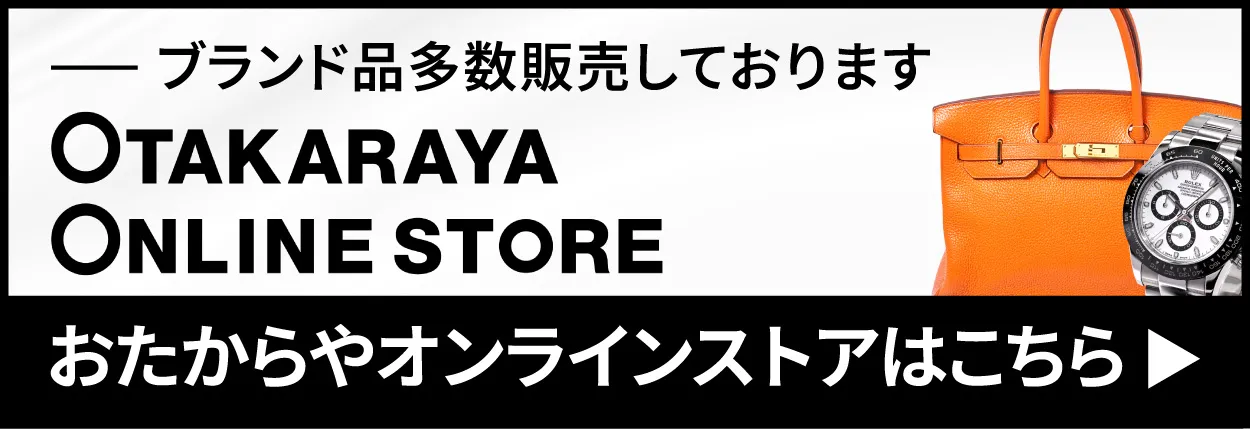
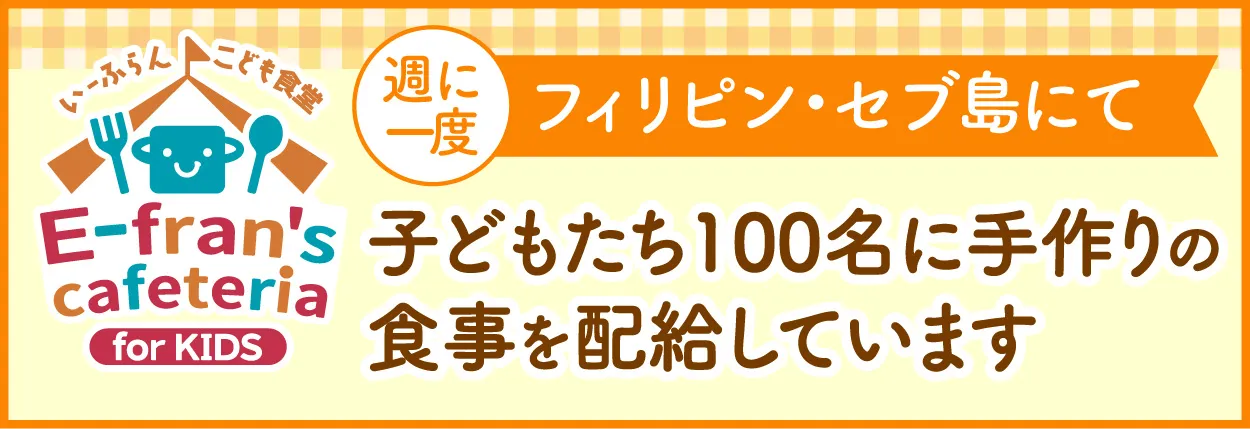

 金・インゴット買取
金・インゴット買取 プラチナ買取
プラチナ買取 金のインゴット買取
金のインゴット買取 24K(24金)買取
24K(24金)買取 18金(18K)買取
18金(18K)買取 バッグ・ブランド品買取
バッグ・ブランド品買取 時計買取
時計買取 宝石・ジュエリー買取
宝石・ジュエリー買取 ダイヤモンド買取
ダイヤモンド買取 真珠・パール買取
真珠・パール買取 サファイア買取
サファイア買取 エメラルド買取
エメラルド買取 ルビー買取
ルビー買取 喜平買取
喜平買取 メイプルリーフ金貨買取
メイプルリーフ金貨買取 金貨・銀貨買取
金貨・銀貨買取 大判・小判買取
大判・小判買取 硬貨・紙幣買取
硬貨・紙幣買取 切手買取
切手買取 カメラ買取
カメラ買取 着物買取
着物買取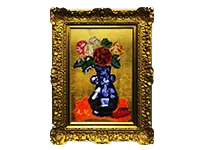 絵画・掛け軸・美術品買取
絵画・掛け軸・美術品買取 香木買取
香木買取 車買取
車買取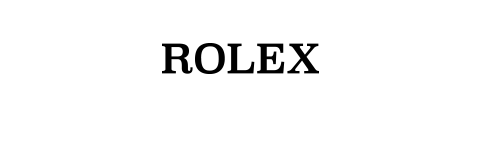 ロレックス買取
ロレックス買取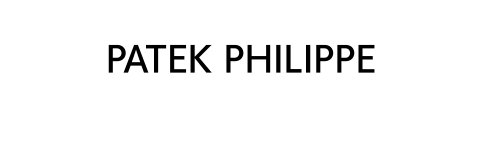 パテックフィリップ買取
パテックフィリップ買取 オーデマピゲ買取
オーデマピゲ買取 ヴァシュロン コンスタンタン買取
ヴァシュロン コンスタンタン買取 オメガ買取
オメガ買取 ブレゲ買取
ブレゲ買取 エルメス買取
エルメス買取 ルイ・ヴィトン買取
ルイ・ヴィトン買取 シャネル買取
シャネル買取 セリーヌ買取
セリーヌ買取 カルティエ買取
カルティエ買取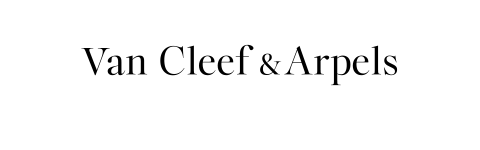 ヴァンクリーフ&アーペル買取
ヴァンクリーフ&アーペル買取 ティファニー買取
ティファニー買取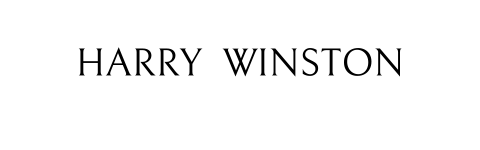 ハリー・ウィンストン買取
ハリー・ウィンストン買取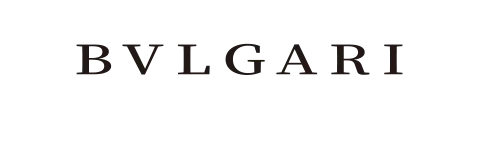 ブルガリ買取
ブルガリ買取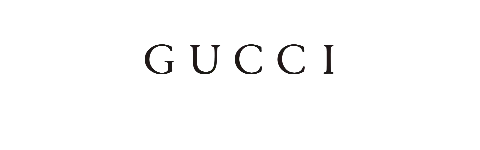 グッチ買取
グッチ買取
 ご相談・お申込みはこちら
ご相談・お申込みはこちら