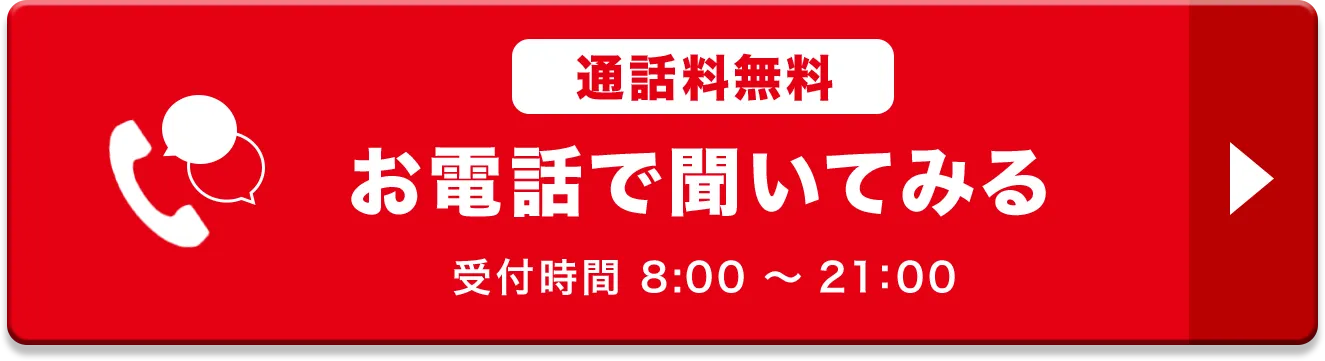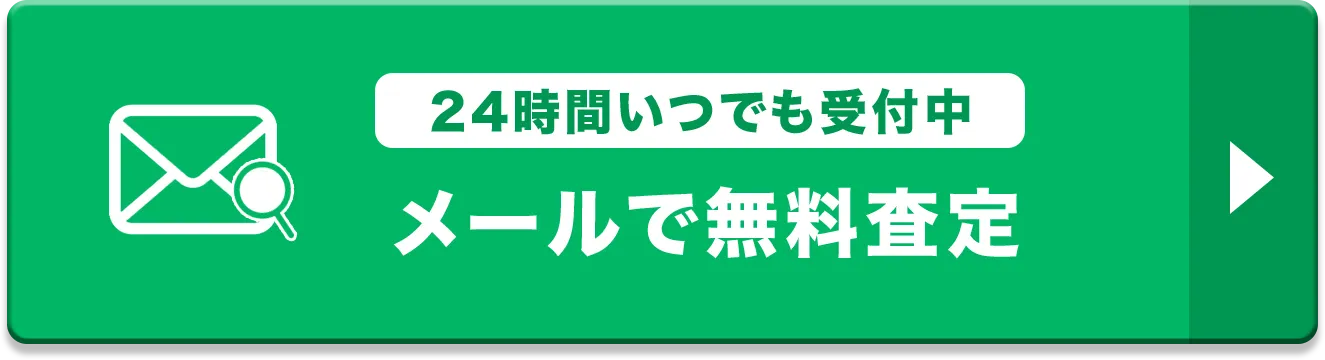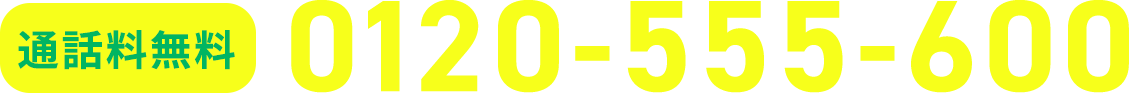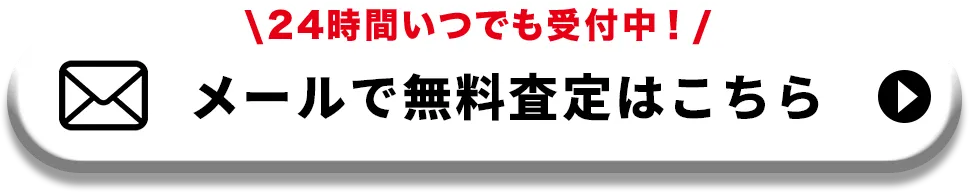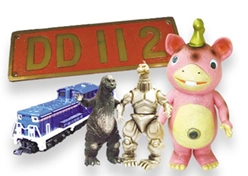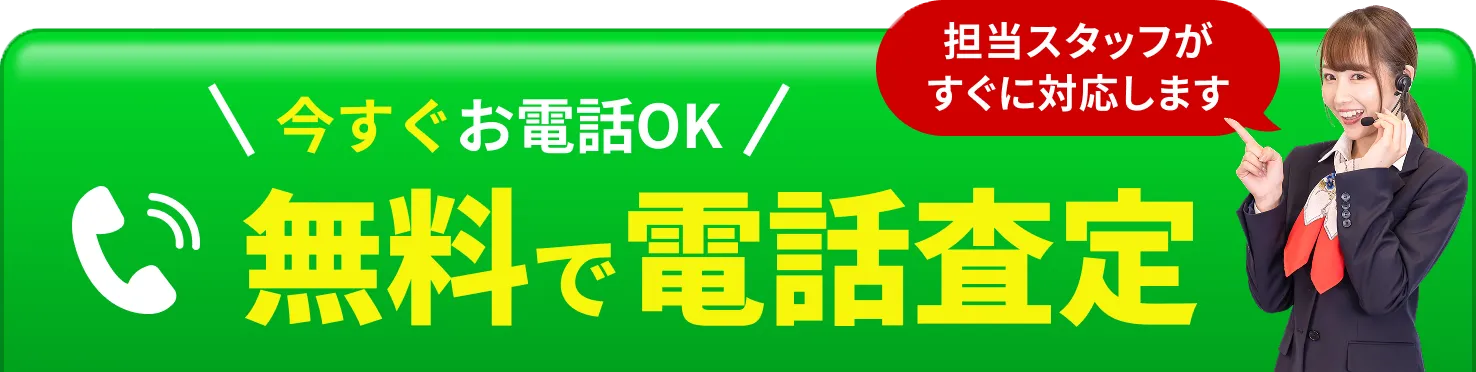金投資をする上での基本知識とは?メリット・デメリットや取引方法をご紹介

※下記の画像は全てイメージです
金(ゴールド)は古くから価値を保ち続け、世界で投資対象として選ばれてきました。近年はインフレや経済の不透明さを背景に、個人投資家からの関心が高まっています。この記事では、金投資をする上でのメリットとデメリット、現物・投資信託・ETF(上場投資信託)などの取引方法、注意点を順に解説します。
さらに、手数料や税制の基本も整理し、はじめての方も比較検討しやすい基礎知識をご紹介します。
Contents
金投資とは?
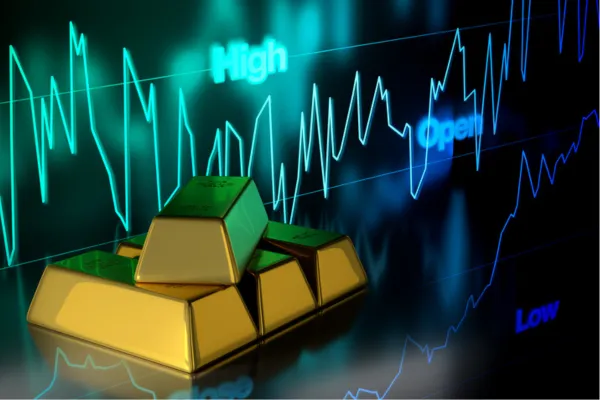
金投資とは、実物資産である金に資金を配分し、価格上昇による利益を期待する投資です。価格は、需要と供給のバランスや為替、金利、国際情勢などで変動します。株式や債券と異なり、金そのものが世界共通の価値を持つため、インフレ対策や資産の価値保存にも有用といえるでしょう。
近年は個人の資産運用でも関心が高まり、地金やコインの直接購入に加え、金価格に連動する金融商品への投資などさまざまです。どれも価格変動に応じた売却益の獲得を目的とします。こうした性質から、価格上昇の局面で収益を狙える投資対象として位置づけられており、金の価格変動を前提にした運用となります。
金投資のメリット

金投資のメリットは、相場の波と付き合いながら資産の安定に寄与する点です。代表的なのは、地政学リスクに強い傾向がある、インフレ下で価値を保ちやすいというものです。
保有比率や手段の選択、為替や金利の影響への備え方で効果は変わりますので、目的と期間に応じて検討してください。
世界情勢が悪化しても価値が安定している
金は「有事の金」と呼ばれ、戦争や金融不安などで市場の不確実性が高まる局面では、資金の避難先として選ばれやすい資産です。
株式や通貨が売られてボラティリティが上がるときも、金は相対的に値持ちがよく、下落幅が抑えられる場面が見られます。現物やETFなど保有手段が多く、流動性が確保しやすい点も安心材料となるでしょう。
ただし、為替や金利の影響は残るため、比率を決めて段階的に組み入れると、分散効果を得やすくなります。長期視点で保有し、定期的に配分を見直してください。また、短期急騰時には利益確定の基準を事前に用意すると、ぶれにくくなります。
インフレ対策として有効である
金はインフレによって通貨の購買力が薄れる局面でも相対的な力を維持しやすい現物資産です。物価上昇に合わせて名目価格が伸びるため、現金の目減りを緩和する盾として機能します。70年代の高インフレ期に実証されたこの特性は、長期分散ポートフォリオに組み入れる根拠となるでしょう。
一方で、短期的には金利や為替の変動に左右されやすく、価格が揺れる場面もあります。積立や定率での買付を用いれば取得価格を平準化でき、タイミングの偏りを抑えられます。
現物、ETF、純金積立など保有形態でコストや課税が変わるため、目標と合わせて事前に確認し、定期的にリバランスするようにしましょう。
需要が高く価値が安定している
金は国や文化を横断して受け入れられる資産で、各国の中央銀行の準備資産、投資、宝飾など多面的な需要に支えられています。需要の分散と供給量の少なさが合わさることで、長期的に見て価値が大きく損なわれにくい点が強みです。
さらに、国際的な指標価格や取引所が整備され、流通の厚みがあることも価値の安定につながります。現物・ETF・投資信託とさまざまな投資ルートがあることも需要を下支えする要因です。短期的な価格の上下は避けられませんが、他の資産と組み合わせると安定感が増すでしょう。
- おたからや査定員のコメント
金投資は、地政学リスクやインフレに対する有効なヘッジで、現物・ETF・投資信託など複数の手段があり、分散投資に組み込みやすい資産です。
ただし、為替や金利の影響、売買手数料や保管費、税制の違いが運用成果に直結します。目的と保有期間を明確にして、全資産の3〜10%を目安に積立やETFで取得価額を平準化し、年1回は配分とコストを見直すようにしましょう。

金投資のデメリット

金投資には利点と同時に注意点があります。価格は為替や金利、需給、地政学要因の影響を受け、保有中の配当はなく、手段によっては手数料も発生します。
費用や税制の違いまで把握すると、目的に合うリスク管理がしやすいでしょう。変動の要因を切り分けて考えることが、損失を抑えた運用につながります。以下で主なデメリットを整理します。
為替の影響によって価格が下がる場合がある
金価格は為替の影響を強く受けて左右されがちです。金の国際相場は米ドル建てで示されるため、円高が進むと円換算の価格が下がる恐れがあります。
世界の価格が横ばいでも、為替次第で評価額は変わります。投資家は金の需給や金利動向に加え、ドル円の方向も確認してください。
反対に円安が進む局面では、国際価格が下がっても円建てでは下げ幅が緩む、あるいは上昇する場合もあります。
購入と売却のタイミングで為替差があり、損益を左右します。為替ヘッジがあるETFは影響を抑えられますが、コストと特性を理解して選択しましょう。短期志向の方は指標発表時の変動にも注意し、余裕資金で運用してください。
配当や利息が発生しない
金は保有しても利息や配当を生みません。株式なら配当、債券であれば利息が得られますが、金はインカムゲインがないため、保有益は主に売却時の差益に限られます。また、金利が上昇する局面では、利回り資産との比較をすると魅力が感じられなくなる点にも注意が必要です。
運用計画では収益源の偏りを避け、他資産との組み合わせで不足分を補う設計が有効でしょう。キャッシュフローが出ないため、複利効果を狙う運用とは相性が異なります。目的や期間を明確にし、値動きと費用を想定しておくと安心です。
投資方法によって手数料がかかる
金の投資方法ごとに費用がかかります。地金や金貨は、購入時と売却時の手数料に加え、保管コストが収益を圧迫します。
また、純金積立では購入手数料や、月次の管理料が発生する場合があるほか、投資信託やETFでは信託報酬が継続的に差し引かれます。さらに、為替ヘッジ付き商品は追加コストを伴うケースもあるため注意してください。
期待収益はこれらの費用を含めて評価し、同一目的の中で最も総コストの低い手段を選択してください。目論見書や取引規定を事前に確認すると、思わぬ負担を避けやすくなります。保険料や配送費が必要となるケースもあるため、保有規模が大きいほど影響を無視できません。費用体系を比較してから契約しましょう。
金投資の種類

金への投資は、現物を手元で保有する方法から、金融商品で価格変動に連動させる方法まで多岐にわたります。コストや税制、保管方法も異なります。
目的とリスク許容度を起点に適否を見極めるため、次項で代表的な方法の仕組みと留意点を概観しましょう。初めての方でも比較しやすいよう、利点と不利点、向いている投資家像も解説します。
金地金への投資
金地金(インゴット)を購入して現物を保有する方法は、仕組みが分かりやすく、インフレや通貨不安への備えとして安心感があります。購入は貴金属専門店や銀行を通じて行い、品位刻印や重量証明で品質を確認します。
一方で、保管場所の確保と防犯が必須です。自宅保管では耐火金庫が望ましいでしょう。また、貸金庫なら安全性は高まりますが、維持費が発生します。
売買には手数料やスプレッド(買う時の価格と、売る時の価格の違い)が伴い、購入証明書の管理も求められます。短期の売買より、長期の資産保全に向く方法です。
価格は相場と連動して日々変動するため、まとまった金額で一度に買うより、時期を分散して購入すると偏りを抑えられます。
金貨への投資
金貨を購入して現物を保有する方法は、少額から始めやすく、メイプルリーフ金貨やウィーン金貨ハーモニーなど、国際的に認知された純金コインを選べます。
収集性や贈答のしやすさが魅力です。一方で、金貨は傷や変形によって評価が下がりやすいため、素手での取り扱いは避け、専用ケースでの保管が基本です。盗難・紛失リスクや保管コストも考慮してください。
また、購入時は信頼できる業者を選び、品位と重量、発行体の信用を確認します。
流通量が多いコインは売買が容易です。記念硬貨は希少性で地金価格を上回る場合もありますが、相場次第でプレミアムが縮小することもあります。
純金積立
純金積立は、毎月一定額で自動的に金を積み立てる方法です。少額から始められ、価格が高い時は少なく、安い時は多く買い付けるため、平均購入単価を平準化できます。
買付は日次や月次の設定が可能で、長期の資産形成に有効です。一方で、買付手数料や積立管理料がかかる場合があり、買値と売値の差も存在します。短期で大きな利益を目指す手法には適しません。
積立比率と目標額を定め、入金の自動化と進捗の点検を組み合わせると、無理なく継続できます。解約や引出の手数料、受渡方法、課税の扱いも事前に確認すると安心です。価格変動が大きい局面ほど分散効果が出やすく、積立の継続が成果に結びつきます。
金の投資信託
金の投資信託は、金価格や関連資産に連動するよう、運用会社がファンドを運用する方法です。
専門家が銘柄選定やリバランスを行うため、初心者でも少額から分散投資を始めやすく、積立設定もしやすい点が特長です。一方で、信託報酬などのコストがかかり、ETFより高めとなる場合があります。
ただし、購入時や解約時の手数料、運用方針、連動対象は確認が必要です。目標と期間に合うファンドを選べば、資産の分散に役立ちます。
また、インデックス型かアクティブ型か、為替ヘッジの有無、分配金の方針も見比べてください。基準価額は市場環境で変動しますので、長期の積立と定期的な見直しを行うと、ぶれを抑えやすくなります。
金のETF
金のETFは、金価格に連動するよう設計された上場投資信託です。証券取引所で株式と同様に売買できます。現物を保有せず価格変動にアクセスでき、リアルタイムの取引と流動性が強みです。
一般に投信より信託報酬が低めで、コストを抑えやすい点も魅力です。一方で、口座開設や売買手数料が必要で、元本は保証されません。為替の影響を受ける商品もあります。
目標の配分比率を定め、定期的にリバランスすると、効果の安定が期待できるでしょう。指標との乖離や保管形態(現物裏付け型または先物連動型)、為替ヘッジの有無は確認が必要です。
指値や成行など注文方法を使い分け、購入時期を分散すると価格の偏りを抑えられます。
金の先物投資
金の先物取引は、将来の一定時点に定めた価格で売買する契約を、取引所で売買する方法です。証拠金を差し入れてレバレッジをかけるため、少ない資金で大きな値動きに対する利益を狙えますが、同時に損失拡大のリスクも高まります。
また、相場が予想に反すると追証が発生する場合があり、日々の価格変動や金利、為替の影響も無視できません。
短期売買向きで、仕組みの理解と厳格なリスク管理が不可欠です。損切り基準と資金管理ルールを事前に定め、順守してください。
ポジションサイズの上限、ロスカットの水準、取引時間帯も重要です。経済指標の発表前後は価格の変動が起きやすいので、スプレッドの拡大や約定の遅延に注意しましょう。
金鉱株投資
金鉱株投資は、金の採掘・精錬・販売を手がける企業の株式に投資する方法です。金価格の上昇は企業収益の押し上げ要因となりやすく、金相場に連動したリターンを目指せます。
一方で、株価には、各社の経営や鉱区の生産性、設備投資、産出国の政情など、多様な要因が影響します。したがって金そのものではなく、株式投資である点を理解し、決算や埋蔵量、採掘コスト構造を確認することが重要です。
分散投資や指数連動型ファンドの活用は、個別リスクの抑制に有効です。為替や金利の変動も評価に影響し、ヘッジ方針でリスクが変わります。長期のテーマとして位置付け、比率を見直すと、相場の偏りに流されにくくなるでしょう。
初心者でも始めやすい投資方法は?

金投資の初心者は、内容が分かりやすく、手続きも簡単な方法を選ぶことが大切です。まずは、専門家が運用する投資信託と、株式のようにリアルタイム売買できるETFの基本、費用やリスクを押さえ、少額から無理なく始める準備を整えましょう。
口座開設の有無や最低投資額、保管の手間の違いも比較すると、より選択しやすくなります。
プロが運用する投資信託
金の投資信託は、運用を専門家に任せられるため初心者に適しています。金価格に連動するファンドを買えば、現物の保管や売買の判断を自分で行う必要がありません。
少額から購入でき、積立にも向くため始めやすいでしょう。また、つみたてNISAを利用すれば、継続しやすいでしょう。注意点として、信託報酬や管理費用が発生することが挙げられます。
目論見書で費用と方針を確認し、目的に合う商品を選んでください。ファンドによっては先物を組み合わせるため、値動きが金現物と一致しない場合があります。
元本保証ではなく、基準価額は上下します。分配方針や為替ヘッジの有無が違うため、仕組みを理解して選ぶことが重要です。
株式市場で売買できる金ETF
金ETFは、証券口座があれば株式と同様の手続きで売買でき、価格を見ながら取引しやすい点が魅力です。信託報酬は投資信託より低めに設定される商品が多く、保管の手間もかかりません。
反面、取引手数料や売買スプレッドの影響を受けるうえに、元本は保証されません。保有対象や為替ヘッジの有無で特性が異なるため、目論見書で仕組みと費用を確認し、資産配分に合う銘柄を選択してください。
国内では現物連動型と先物連動型があり、連動精度や保管形態が異なります。指値・成行で機動的に売買できますが、薄商いだと約定が遅れがちです。長期保有では分配方針や信託期間も確認してください。
金を売却した際の利益は課税対象になる

金の売却で利益が出た場合は、課税対象です。ただし税の扱いは、金融商品として運用した場合と、地金や金貨など現物を売却した場合で異なります。違いを理解しておくと、思わぬ負担を避けやすくなります。
申告方法や税率、特別控除の有無も変わるため、準備段階で把握することが大切です。それぞれの課税関係を確認しましょう。
金融商品の場合は分離課税
金ETFや金の投資信託など金融商品として運用した利益は、株式等と同様に申告分離課税の「譲渡所得」となり、原則20.315%(所得税15.315%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)で課税されます。
特定口座(源泉徴収あり)を利用すれば、売却時に税額が差し引かれ、確定申告を省略できます。他の所得と合算せず、損益通算や繰越控除の可否は商品性と口座区分で異なるため、注意が必要です。
純金積立口座など金融類似商品の利益も、同枠の扱いとなるケースが多いです。年間取引報告書で損益を把握し、「源泉徴収なし」を選んだ場合は確定申告で精算します。税率や控除の適用は、制度変更や商品仕様で異なるため、最新の条件を確認しましょう。
現物取引をした場合は総合課税
自ら購入した地金や金貨など現物を売却して得た利益は、給与などと合算される総合課税の「譲渡所得」となります。
所得が多いほど税率が上がる一方、個人の譲渡所得には年間50万円の特別控除があり、利益が50万円以下なら課税されません(超過分のみ課税)。確定申告では、取得価額や諸費用を差し引いた差額を計算し、他の所得と合わせて申告します。
保有規模や売却回数により必要書類が変わるため、事前の整理が有効です。計算には取得価額の把握が不可欠で、書類不足は負担増につながります。取得時の領収書や明細を保管し、売却時の手数料や送料を経費として控除できるよう準備すると、計算がスムーズになります。
金投資がおすすめな人

金投資は万人向けではありませんが、資産を長期で守りたい方、相場の上下に過度に振られたくない方、安定した価値を重視する方には適しています。
現物・投信・ETFなど方法の違いも踏まえ、分散効果やインフレ耐性の観点から、金投資に向く人の条件を明確にし、目的とリスク許容度を起点に検討しやすくします。
長期的な保有を考えている人
金は無利息で短期の値動きもありますが、長い歴史を通じて価値がゼロになった例はなく、インフレや危機の局面でも購買力の維持に役立ってきました。
そのため、老後資金や教育費のように時間軸が長い目的を持つ方、資産をじっくり守りたい方に向きます。保有比率と購入基準をあらかじめ定め、積立や複数回の分散購入を組み合わせると、価格の偏りを抑えられます。
現物は保管コストや盗難リスク、ETFや投信は、信託報酬や為替の影響に注意が必要です。定期点検とリバランス、急騰時の利益確定ルールも整えてください。目標期間と出口を明確にすると判断がぶれにくくなります。
価値が安定しているもので取引をしたい人
発行体の信用に依存しない実物資産を選びたい方には、金の特性が適します。金は企業業績や国の財政に左右されにくく、株式や債券と相関が低い傾向があります。市場が不安定なときに下落幅を和らげ、全体のドローダウンを抑える役割を果たすでしょう。
一方で、短期の変動や為替の影響は避けられず、元本は保証されません。現物・ETF・投資信託のいずれを選ぶかで、保管やコストが異なります。
指標との乖離や流動性、注文方法も確認してください。目標配分を定め、段階的な購入と定期的な見直しで安定感を高めましょう。安全資産とされる場面でも価格は動きますから、想定レンジと損益基準を事前に決めると迷いにくくなります。
分散投資を検討している人
株式や債券に偏ったポートフォリオに、値動きの異なる資産を加えたい方には金が有効です。金は他資産と完全に逆相関ではありませんが、値動きのタイミングや方向がずれるため、組み入れることで全体の変動幅を抑えやすくなります。
特に下落局面で下げを和らげ、資産の回復力を高める効果が期待できます。保有比率を決め、定期的にリバランスしましょう。現物・ETF・投信で費用や為替影響が異なりますので、役割とコストを見比べてください。
購入時期を分散し、目標レンジの上限下限を事前に定めると運用判断が安定します。流動性と税制の扱いも確認しておくと、判断がぶれにくくなるでしょう。
金投資で気を付けるべきこと

金投資で失敗を避けるには、目的と手法を先に定め、費用とリスクを考慮して計画的に進めることが大切です。
ここでは、投資家が最初に確認すべき要点として「目的の明確化」「方法の選択」「デメリットの把握」を示し、実行の順序と判断基準をわかりやすく整理します。
目的に合わせた投資方法を決定する
投資家は、まず金投資の目的を明確にしましょう。インフレ対策、通貨下落への備え、資産分散のいずれを重視するかで、方法と保有期間が変わります。
長期の価値保全を狙う場合は、現物の保有が候補となります。短期の値幅を取りたい場合は、流動性の高いETFが選択肢となるでしょう。
目的を軸に据えると、判断がぶれず、入金額や売却基準も設定しやすくなります。予備費の範囲で少額から始め、定期積立か一括かも選びます。
分配方針や為替ヘッジの有無、手数料水準も目的に照らして比較してください。資産全体の安全域を超えないこと、損切りとリバランスの条件を先に決めておくことも大切です。
購入する金の種類を決める
次に、購入する金の種類を決めます。地金や金貨は実物を手元に置ける安心感がある一方で、保管手間や費用が課題です。また、純金積立は少額から始めやすく、購入時期を分散しやすい反面、手数料や管理料を伴います。
さらに、ETFは売買が容易で保管の手間がありません。信託報酬や為替ヘッジの有無、連動方式の違いまで比較し、自分の投資額と手間に合う手段を選んでください。
現物の購入では、配送費や保険料が追加される場合があります。ETFには現物連動型と先物連動型があり、連動精度やコスト構造が異なります。目論見書や取引規定を読み、最終的な総コストで評価すると判断がぶれません。
金投資のデメリットにも目を向ける
金投資のメリットだけでなく、デメリットも確認しましょう。金は安全資産と言われますが、短期では価格が大きく変動し、保有中の利息や配当はありません。金利上昇局面では相対的魅力が低下しやすく、為替の方向でも評価額が揺れます。
そのため、過度な期待は控え、余裕資金で計画的に運用してください。事前に損切り基準と保有上限を決め、分散と継続性でリスクをならすと安定につながるでしょう。価格要因を金の需給、実質金利、ドルの強弱に分けて把握すると判断がしやすくなります。
保管費や信託報酬といったコストも収益を圧迫します。相場ニュースの確認も重要です。
保有している現物の金を手放す際のポイント

現物の金を売却するときは、手順と準備を整えるほど、安全で有利な取引につながります。買取業者の選定、書類の確認、相場の見極めという基本を押さえ、トラブルや機会損失を避けましょう。
保管方法の違いや、購入証明書の提示可否も確認してください。売却時期の判断も価格に影響します。以下、要点を順に解説します。
信頼できる買取業者に依頼する
金を売却するときは、実績と信頼のある買取業者を選ぶことが第一歩です。古物営業許可の有無、店舗数や運営年数、査定の透明性、手数料の明示などを確認しましょう。
初めての場合は複数社で見積もりを取り、金額と対応を比較すると安心です。本人確認書類や持ち込み点数の扱い、キャンセルの可否も事前に確かめてください。
「おたからや」では店頭にプロの鑑定士が常駐しており、ご来店いただければ全国どこの店舗でも無料で査定を行うことが可能です。鑑定士は豊富な実績に基づき国内外の取引データを参照し、査定の根拠を丁寧にご説明いたします。
付属品が揃わない場合でも素材や状態、流通性を総合的に評価するため査定を実施することができるのでご安心ください。査定にご納得いただければ当日中に現金で受け取ることも可能です
インゴットなどの場合は購入証明書を用意する
インゴットなどを売却する際は、購入時に発行された購入証明書や取引証明書を事前に用意しましょう。真贋確認と来歴確認が円滑になり、手続きがスムーズになります。
提示が必須ではない店舗もありますが、多くの店舗で提示を求められる例があり、不足すると買取額や所要時間に影響する場合があります。
紛失した証明書は再発行できないことが一般的です。日頃から保管場所を固定し、売却時には忘れずに持参してください。
本体の品位刻印やシリアルの照合、重量測定と合わせて提示すると、査定の根拠が明確になりやすく、トラブル防止にもつながります。コピーや写真だけでは足りない場合があるため、原本を用意しましょう。
価格が高いタイミングを狙う
売却益を高めたい場合は、できるだけ相場が高値圏にある局面を狙いましょう。金価格は為替や金利、地政学リスク、投資需要などで日々変動します。
チャートの長期トレンドと移動平均、直近の高値安値、ニュースの材料を併せて確認すると判断しやすくなります。円安が進むと国内価格が押し上げられる場合があり、海外の上昇と重なると有利です。
ただし、天井の見極めは困難です。複数回に分けた売却や事前の目標価格設定、手数料と税の控除後金額の試算を行い、慌てずに意思決定してください。
まとめ
金投資は長い歴史を通じて価値が認められ、インフレ対策や分散に有効な選択肢です。一方で、為替の影響や無配当、手数料の負担といった弱点もあるため、特性を理解した上で活用してください。
まずは少額から始め、積立や一括など自分に合う購入方法を選び、目的と保有期間を先に決めましょう。
運用を任せられる投資信託や、株式のように売買できるETFは初心者向きです。税制や費用も確認し、リスク許容度に合わせて購入額を調整し、無理のない配分でポートフォリオに組み入れてください。
「おたからや」での金の参考買取価格
ここでは、「おたからや」での「金」の参考買取価格の一部を紹介します。
2026年02月27日09:30更新
今日の金1gあたりの買取価格相場表
| 金のレート(1gあたり) | ||
|---|---|---|
| インゴット(金)28,377円 -24円 |
24金(K24・純金)28,150円 -24円 |
23金(K23)27,072円 -23円 |
| 22金(K22)25,880円 -22円 |
21.6金(K21.6)25,256円 -21円 |
20金(K20)23,099円 -19円 |
| 18金(K18)21,254円 -18円 |
14金(K14)16,459円 -14円 |
12金(K12)12,770円 -10円 |
| 10金(K10)11,408円 -9円 |
9金(K9)10,244円 -9円 |
8金(K8)7,605円 -6円 |
| 5金(K5)3,689円 -3円 |
||
※上記の買取価格はあくまで参考価格であり、市場の動向、
付属品の有無などによって実際の査定額が変動する場合があります。
※土日・祝日を除く前営業日の日本時間9:30の価格と比較
※状態や付属品の有無、時期によって買取価格が異なりますので詳細はお問い合わせください。
金製品は、まず純度(K24、K18など)と重量が査定の基本となります。ブランド刻印やデザイン性、仕上げの良さは加点要素になり、宝石が付いている場合は石の種類やセッティング状態も評価に反映されます。
一方で、表面の擦れやサイズ直しの跡、変形は減額要因となります。刻印や保証書などの付属品が揃っていると真贋確認が迅速になり査定が安定しますので、売却を検討される際は付属品をご用意のうえ店頭でご相談ください。
- おたからや査定員のコメント
金は古くから価値保存手段として重視され、インフレや地政学リスクに対するヘッジ性が魅力です。一方で為替影響・利子配当がない点や売買手数料、保管コストが負担となります。
まずは目的と保有期間を明確にし、現物・ETF・投信の比率を決めて少額積立を行うようにしましょう。
税制・信託手数料は事前に確認し、現物は安全な保管場所を確保してください。定期的にポートフォリオを見直し、相場変動時は冷静に対処することが、長期的な成功の鍵となります。

金の買取なら「おたからや」
「おたからや」では、インゴット・純金コイン・K18やK14、K10といったジュエリーから、歪んだスクラップや片方だけのピアス、刻印の薄れた品まで幅広く査定可能です。専門鑑定士が純度を瞬時に測定し、最新相場を反映した高水準の査定額をご提示します。
査定は完全無料・予約不要、ご成約後は最短即日で現金化が可能です。大切な金製品を納得の価格で売却したい方は、豊富な実績を誇る「おたからや」へぜひご相談ください。
おたからやの金買取
査定員の紹介

-
趣味
ショッピング
-
好きな言葉
有言実行
-
好きなブランド
ハリーウィンストン
-
過去の買取品例
おりん、インゴット
伊東 査定員
初めまして。査定員の伊東と申します。 おたからやでは金の買取をする際に、今日の金の1gの買取相場を基に、デザイン性などをプラスで評価して高価買取を行っております。過去に1万点以上の査定をさせていただきましたが、とても多くのお客様に想像以上の金額になったと喜んでいただきました。また、おたからやでは、すべての店舗に比重計を完備しているため、金の含有量を正確に測定することができます。 金額はもちろんのこと、接客も最高のおもてなしができるように心がけております。私共はお品物だけではなくお客様一人ひとりの思いに寄り添い満足して帰っていただけるように丁寧な説明を致します。誠心誠意対応させていただきますので、是非おたからやのご利用をお待ちしております。
その他の査定員紹介はこちら金を高く売るためのコツは、「金の価格が高いときに売ること」と「高値で買い取ってくれる専門店に売ること」です。金の価格は現在非常に高騰しているため、売却にはベストなタイミングといえます。
金の高価買取はおたからやにお任せください。
関連記事

知りたくありませんか?
「おたからや」が
写真1枚で査定できます!ご相談だけでも大歓迎!





































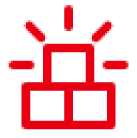

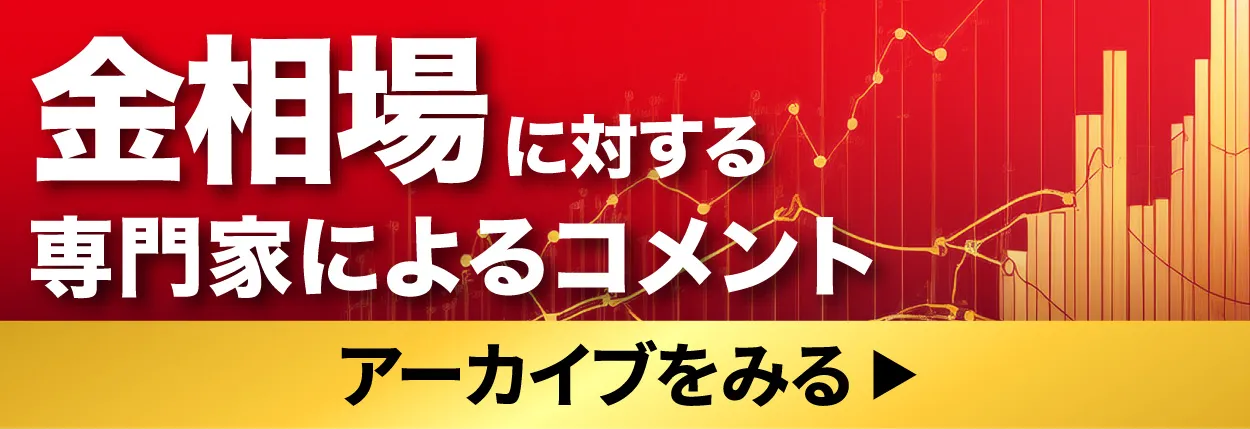
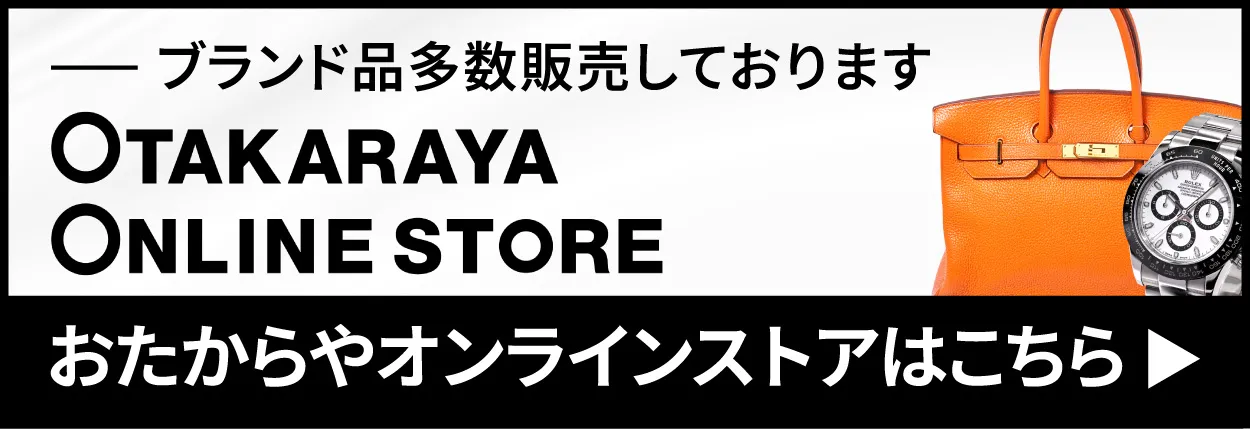
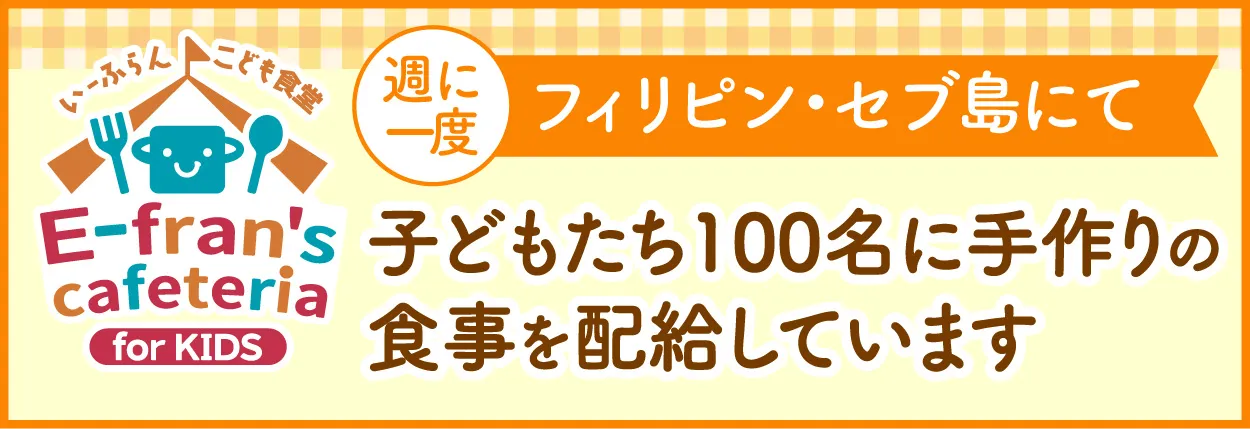

 金・インゴット買取
金・インゴット買取 プラチナ買取
プラチナ買取 金のインゴット買取
金のインゴット買取 24K(24金)買取
24K(24金)買取 18金(18K)買取
18金(18K)買取 バッグ・ブランド品買取
バッグ・ブランド品買取 時計買取
時計買取 宝石・ジュエリー買取
宝石・ジュエリー買取 ダイヤモンド買取
ダイヤモンド買取 真珠・パール買取
真珠・パール買取 サファイア買取
サファイア買取 エメラルド買取
エメラルド買取 ルビー買取
ルビー買取 喜平買取
喜平買取 メイプルリーフ金貨買取
メイプルリーフ金貨買取 金貨・銀貨買取
金貨・銀貨買取 大判・小判買取
大判・小判買取 硬貨・紙幣買取
硬貨・紙幣買取 切手買取
切手買取 カメラ買取
カメラ買取 着物買取
着物買取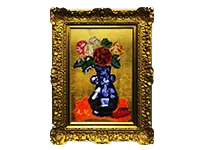 絵画・掛け軸・美術品買取
絵画・掛け軸・美術品買取 香木買取
香木買取 車買取
車買取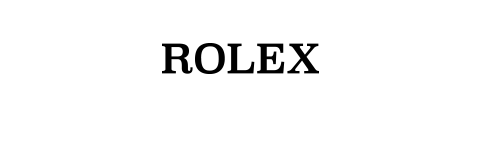 ロレックス買取
ロレックス買取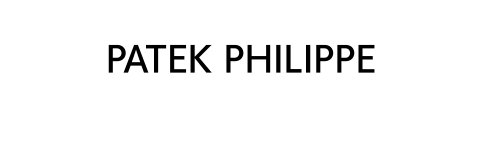 パテックフィリップ買取
パテックフィリップ買取 オーデマピゲ買取
オーデマピゲ買取 ヴァシュロン コンスタンタン買取
ヴァシュロン コンスタンタン買取 オメガ買取
オメガ買取 ブレゲ買取
ブレゲ買取 エルメス買取
エルメス買取 ルイ・ヴィトン買取
ルイ・ヴィトン買取 シャネル買取
シャネル買取 セリーヌ買取
セリーヌ買取 カルティエ買取
カルティエ買取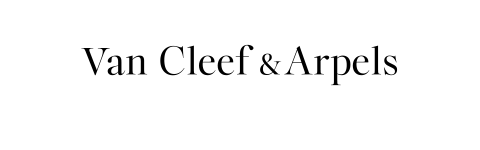 ヴァンクリーフ&アーペル買取
ヴァンクリーフ&アーペル買取 ティファニー買取
ティファニー買取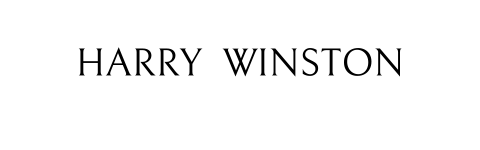 ハリー・ウィンストン買取
ハリー・ウィンストン買取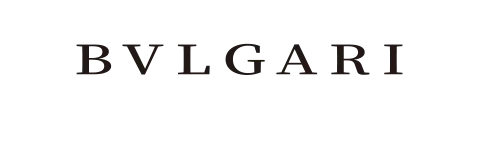 ブルガリ買取
ブルガリ買取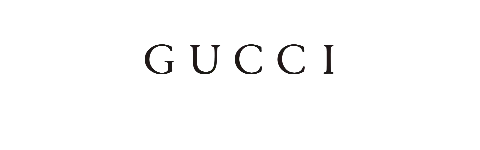 グッチ買取
グッチ買取
 ご相談・お申込みはこちら
ご相談・お申込みはこちら