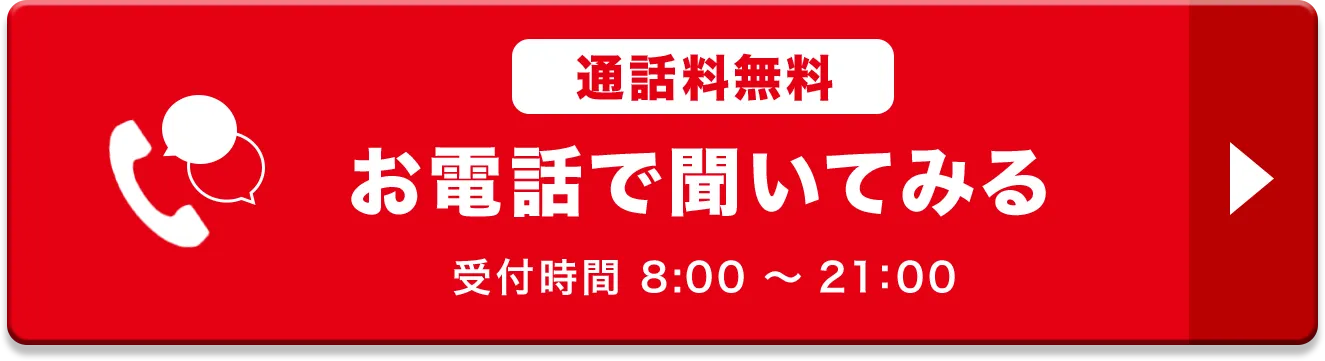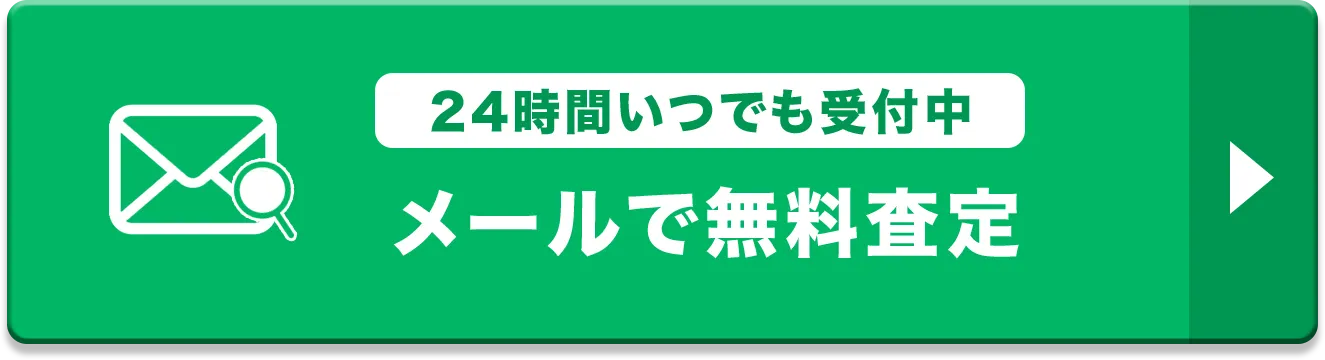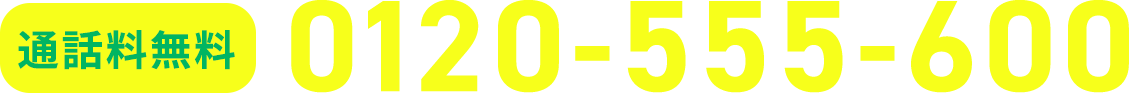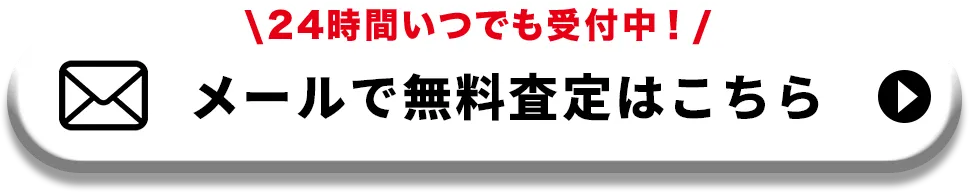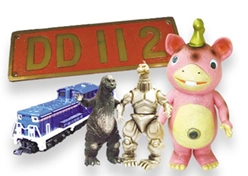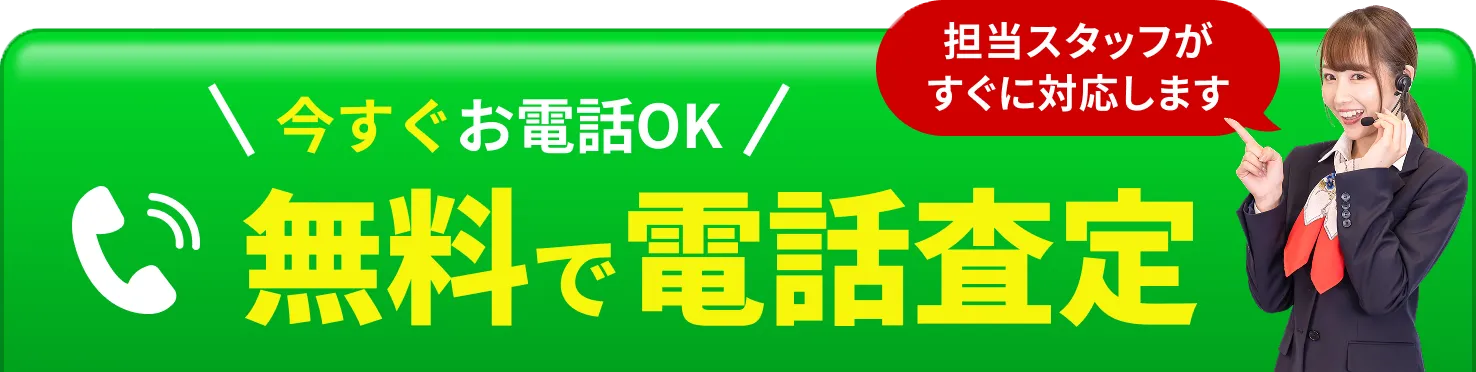金の歴史や加工技術について解説!現在の価値についてもご紹介

※下記の画像は全てイメージです
金は古代から人々を惹きつけ、文明や経済の発展と密接に結び付いてきました。その希少性と美しさにより、通貨や宝飾として長く使用されています。
本記事では、世界と日本の金の歴史、金貨の変遷、代表的な加工技術、そして現代でも価値が高い理由を解説します。また、具体例を交えながら、時代ごとの背景と技術の発達も詳しく取り上げるので、ぜひ最後までご覧ください。
金にまつわる世界の文明の歴史
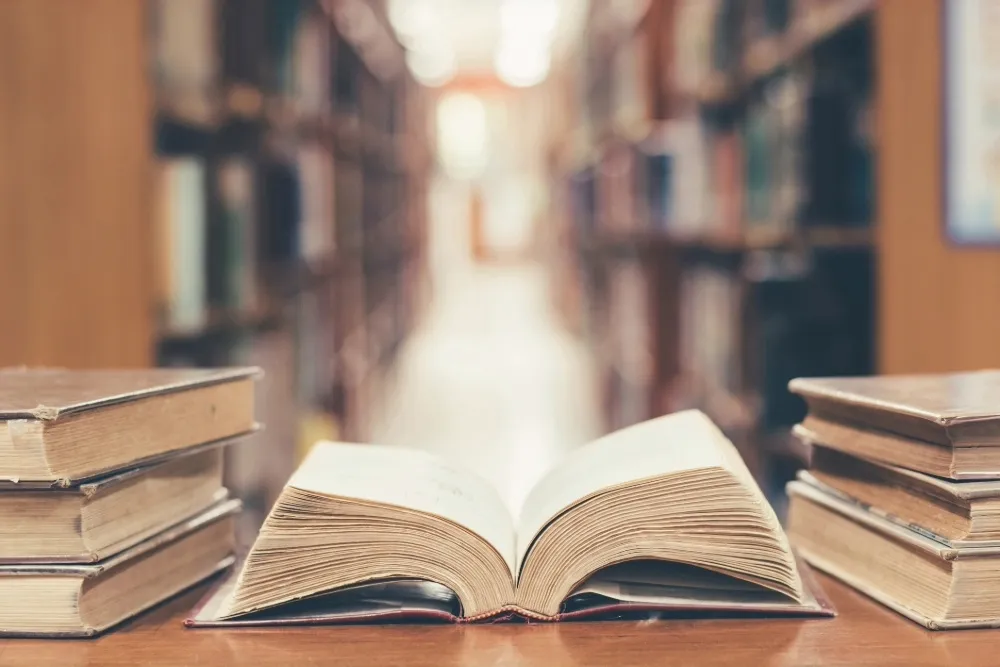
人類は太古から金に特別な価値を見出してきました。古代の諸文明では、驚くほど高度な技術で金を扱ったとも言われています。
ここでは、シュメール、トラキア、古代エジプトの3つの古代文明に焦点を当て、遺物と技法の痕跡から各文明と金の関わりを確認し、権威や信仰との結び付きにもふれます。歴史的背景を踏まえることで、金の文化的価値と現在まで続く評価の源泉が見えてくるでしょう。
高度な技術で金を扱っていたとされるシュメール文明
シュメール文明はメソポタミア南部で紀元前4千年紀後半〜3千年紀(ウルク期〜初期王朝期)に興隆し、金の鋳造や鍛金、象嵌、粒金など高度な宝飾技術を発達させました。ウルの王墓からは金装飾の竪琴や装身具が出土し、権力と祭祀を彩りました。
太陰暦と60進法に基づく観測と記録は生産や交易管理にも結び付いています。「世界最古の金製品」はシュメールではなく、紀元前4600〜4200年頃のブルガリア・ヴァルナ墓地由来とされます。金は王権の象徴と位置付けられ、広域交易で供給されたと考えられます。
黄金文明とも呼ばれるトラキア文明
トラキア文明は、ギリシャやアケメネス朝ペルシャと交流した紀元前1千年紀に繁栄し、精緻な金工で知られます。ブルガリア各地の王墓や祭祀具から黄金製品が多数出土したので、「黄金文明」とも呼ばれます。
2004年にはセウテス3世の墓から厚さ約3mm・約672gの黄金マスクが見つかりました。金の供給は地域の鉱床と広域交易に支えられ、葬送や祭祀で権威を示す役割を担ったと考えられます。
数多くの金製品が発掘された古代エジプト文明
古代エジプト文明は、古代文明の中でも金との結び付きが強いことで著名です。紀元前3000年頃までに統一国家となり、この時期にはすでに金製の装飾品が数多く作られていたとされています。実際には遺跡各地から黄金の遺物が極めて多く発掘され、他文明と比べても圧倒的な量が確認されています。
出土品は装飾品や副葬品が中心で、金の美観と加工技術の高さを示すこととなりました。こうした事実から、人々は「古代エジプト=黄金」という強いイメージを抱いています。当時から金は権威や信仰とも結び付き、社会と文化の象徴として広く用いられていました。その傾向は後世にも受け継がれています。
エジプト文明にまつわる「三大黄金マスク」とは
エジプトの黄金マスクで著名なのは、ツタンカーメン(第18王朝)に加え、タニス出土のプスセンネス1世とアメンエムオペト(いずれも第21王朝)の3点で、通称「三大黄金マスク」と呼ばれます。1922年のツタンカーメン墳墓の発見とその後行われたタニス王墓群の調査で実物が確認され、良好な保存状態が保たれています。
各作例は打出し・鍛金・象嵌が高度に施され、王権と葬送儀礼の象徴として美術史・金工技術史の基準資料となる例です。青金石やガラス質の象嵌が彩色効果を高め、顔に現れる感情や印象の表現と王名のカルトゥーシュも精緻に表されています。
古代エジプトでは延べ棒ではなくドーナツ状だった
現代では金塊といえば台形の「延べ棒」型のインゴットを思い浮かべますが、古代エジプトの保管形態は少し異なっていました。壁画や象形文字にはドーナツ状の環になった金塊が描かれ、鋳造後に環状へ成形して保管した様子がうかがえます。この形は持ち運びや吊り下げで扱いやすく、数量管理にも利点があったと考えられます。
形こそ延べ棒ではありませんが、金そのものは貴重な資源として価値基準となっていました。現代の延べ棒と果たす役割は同じで、価値を示す実物として機能しました。独特の形状は、古代の金文化と実務の特徴を示す例といえるでしょう。
身分の高い女性が金製品のアクセサリーを身につけていた
金はその美しさと希少性から、古来より身分や権威の象徴として用いられてきました。古代エジプトでも例外ではなく、地位の高い女性は金の首飾りや装飾品を身につけていたと伝えられます。
たとえば、クレオパトラ7世も黄金や宝石で飾られた「ウェセク」と呼ばれる首飾りを着用したとされています。ウェセクは幾重にも連なる形状で、王侯貴婦人のみが許された特別な装身具でした。宮廷の儀礼や祝祭でも重んじられ、黄金の装飾は富と権力を示し、装う者の美しさを引き立てました。
日本の金の歴史

日本でも金は古くから特別な金属として重んじられてきました。産出と利用の歴史は8世紀に始まり、中世には「黄金の国ジパング」として海外に知られることになりました。
ここでは残されている記録から中世・近世の逸話までをたどり、日本における金の歩みを整理します。全体像を押さえると、現在の金の評価の理解も進むでしょう。
日本では8世紀に金が発見された
日本では、奈良時代の749年に陸奥国(現在の宮城県)で金が産出されたことが最初期の記録として伝わっています。史書「続日本紀」は、陸奥国の黄金山(現・宮城県遠田郡涌谷町付近)で砂金が見つかり、聖武天皇に献上されたと記しました。
東大寺大仏は752年に完成し、鍍金(めっき)には約150kgの黄金が用いられました。この献上は大仏造立の資材確保にも結び付いたと考えられます。これらの事実は、8世紀に国産の金が流通し、政治と宗教の場面で活用されたことを示す事例です。金が採れる産金地の記憶は地域史にも残り、今日まで広く語り継がれています。
東方見聞録にて「黄金の国ジパング」と呼ばれることになる
13世紀末、ヴェネチア共和国の商人であるマルコ・ポーロが口述した「東方見聞録」は、日本を「ジパング」として欧州に紹介しました。彼は来日しておらず、元朝で得た伝聞に基づき宮殿の屋根や床まで黄金で覆われていたと記されていました。
当時は鎌倉時代で、陸奥や佐渡の産金や平泉・金色堂の実例が背景にあったと考えられます。記述は誇張を含んでいましたが、欧州の日本像を形づくり、のちの探検や交易への関心を高めました。そのイメージは航海者の地理認識や地図作製にも影響し、アジア航路の発展を刺激したとされています。
日本最大の金脈は佐渡金山
佐渡金山は日本最大級の金脈として知られます。慶長6年(1601年)に鉱脈が見出され、関ヶ原後に徳川家康が天領と定めて大規模採掘が始まりました。幕府直轄の厳格な管理下で江戸初期は採掘が活発化し、金銀の産出は幕府財政を支えました。
産出は次第に減少しましたが、1869年には西洋技術と外国人技師の導入で一時回復しています。島内では坑道網や選鉱・排水技術が改良され、稼働は約400年に及びました。象徴的な露頭「道遊の割戸」は規模を物語り、現在は一部坑道が公開され観光資源となっています。歴史を体感できる展示も整備されています。
- おたからや査定員のコメント
奈良期の涌谷砂金から佐渡金山まで、日本産金は宗教・財政を支えた歴史背景が評価を押し上げます。8世紀献上金付き由緒品や佐渡初期鋳造の小判は、本物であれば流通量の少ない希少な品物です。産地刻印・奉納書が揃えばさらに上乗せが期待できます。もしお持ちの方は錆び落としは避け乾拭きで保管し、重量と比重値を記録しておくといいでしょう。
佐渡道遊の割戸由来の鉱石片や元禄小判は資料としての価値が高く、国際オークションでも指名買いが入るほどです。

金貨の歴史について

金は古代から貨幣として用いられてきました。世界最古の金属貨幣は金を含むコインとされており、価値の基準づくりにつながっています。
日本でも時代ごとに多様な通貨が鋳造され、経済と制度の発展を支えました。各国の通貨制度や交易の広がりとも結び付き、重さや品位の管理が整えられてきました。背景を知ることで、位置づけがより明確になります。ここでは通貨の歩みを確認していきましょう。
世界最古の金貨は「エレクトロン貨」
金属貨幣の起源は紀元前7世紀の中東とされ、リディア王国(現トルコ西部)で鋳造された「エレクトロン貨」が広く知られています。この貨幣は自然金由来の金銀合金から作られ、紀元前670年頃には市中で流通していたと考えられます。
造幣にはパクトロス川の砂金が用いられ、表面には王家の紋章が打刻されました。ここで金の重量と品位の管理が進み、物々交換の効率の悪さを解消することにつながりました。エレクトロン貨は純金ではありませんが、貨幣の価値を定めて決済を標準化し、貨幣経済の出発点として「世界最古の金貨」と位置付けられます。
日本の金貨は様々なものがある
日本の金貨史は、外来制度と国産技術の交差で発展してきました。奈良の和同開珎は銅銭で、当初の金は献上品や装飾が中心でした。室町期には明銭の流入と砂金の秤量決済が広がり、金の貨幣利用は中世後期に本格化します。安土桃山では大判・小判が生まれ、江戸では慶長小判が規格化されました。
幕府は金座を置き両・分・朱の制度を運用したことで、楕円の小判と長方形の大判が普及します。明治には円建ての1円・5円・10円・20円金貨が鋳造され、制度改正ののち流通は次第に縮小しました。
鎌倉時代
鎌倉時代には国産の金貨はまだ鋳造されておらず、金は砂金や小塊のまま秤量で売買されていました。竹筒や革袋に収め、取引の場で目減りを差し引いて決済する実務が広がります。流通の主役は中国銭でしたが、砂金は高額決済や寺社への献納、工芸品に用いられました。
規格が未整備だったため、試金石で純度を確かめ、輸送の紛失防止や秤量の精度確保も重視されます。商人は証文や仲介を介した信用取引も進めました。奥州などの産金地は商圏を潤し、実物資産としての信用が定着しました。検分では色調の比較など簡便な方法も併用し、取引の透明性を保つ体制を整えています。
室町時代
室町時代には貿易で明銭が大量に流入し、当時すでに出回っていた宋銭や個人や民間の工房などが私的に製造した貨幣とともに流通の主役となりました。
高額の決済には金銀地金や砂金を秤で量る秤量貨幣が用いられ、寺社造営や豪商の取引に広がります。16世紀後半の南蛮貿易では灰吹法(※1)や南蛮吹き(※2)が伝わり、銀の増産と併せて金の品位管理も進みました。
戦国期には甲斐や陸奥で金山開発が進み、座や関所の統制下で流通が整えられます。割符などの信用決済も併用され、貨幣経済の浸透が加速し、安土桃山〜江戸の大判・小判の整備へとつながりました。これらの変化は取引の標準化を促し、後世の通貨制度の基盤を形作ったと考えられます。
※1:金や銀を含んだ合金を、灰を敷き詰めた炉で加熱し、融点の低い鉛を酸化させて灰に吸収させて、金や銀を取り出す方法
※2:金や銀を鉱石などから一度鉛に溶け込ませ、そこから金や銀を抽出する方法
安土桃山時代
安土桃山時代には、豊臣秀吉のもとで金地金の規格化が進みました。代表例が「天正大判」です。約165gの大型金板で、御用金(臨時の上納金)や大口決済、諸大名への恩賞に用いられました。鋳造は後藤家が統括を任され、品位・意匠・署名を厳格に管理しました。槌目を残す打ち出し仕上げは威信の表現でした。
発行は16世紀末で、戦国を越えた権威と財政の可視化を意図し、金山開発とともに供給体制が整います。額面は重量と品位で担保され、規格貨幣制度の始まりとなりました。この枠組みは江戸初期の小判と金座の創設へ継承され、流通の標準化を後押しします。
江戸時代
江戸時代には、徳川家康が金銀貨の制度化を進め、金座・銀座(のちの銭座)を設けて鋳造方法と品位・重量を統一しました。通貨単位は両・分・朱に整理され、慶長小判は純度約86%・重さ約18gが基準です。金座は引き続き後藤家が統括し、打刻と検定を担いました。
銀は丁銀・豆板銀として秤量流通し、相場維持に合わせて改鋳が実施され、佐渡などの鉱山は直轄で、精錬の改良が進みました。これらの整備は産金・産銀を安定させ、幕府財政と都市商業を支える基盤となり、貨幣経済の普及にも弾みがつきました。
明治時代
明治時代には、通貨制度が近代化しました。明治4年の新貨条例で円・銭・厘と洋式の円形硬貨が導入され、小判からの移行が進みます。大阪には香港造幣局の設備を移した造幣寮(現・造幣局)が設置され、製造と品位証明を担いました。明治15年には日本銀行が創設され、紙幣発行が統一されます。
さらに1897年に金本位制が確立し、1円・5円・10円・20円の金貨が本位貨となりました。貨幣法で1円=0.75gの純金と定め、国際取引に対応しています。当初は銀の流通が大きく、事実上の銀本位でしたが、制度整備で金本位へ移行します。造幣局は刻印試験や地金分析を行い、品質管理の近代化も進めました。
大正時代
大正時代は、名目上の金本位制を維持しましたが、1917年に金輸出が禁止され、紙幣を本位貨幣と交換する兌換(だかん)は事実上停止します。これにより金貨の流通は縮小し、小額決済は銀・銅・白銅貨と日本銀行券が担いました。
国内では補助貨の増発が進み、実務は銀・紙幣決済へシフトします。その結果、造幣局は品位証明と供給安定に注力しました。戦時・戦後の物価上昇に対応して金融制度の整備も進み、近代的な通貨運用が根づきました。その結果、流通構造は金から銀・紙幣中心へ転換しました。
金の加工技術の種類

金製品の輝きは、多様な加工と材料特性への緻密な配慮に支えられています。
ここでは、金が柔らかく延性・展性に富む特性を踏まえ、古来から現代まで受け継がれる代表技法の要点を簡潔に紹介します。
彫刻技術
金の彫刻は、地金にタガネを当て小槌で刻む「彫り」と、裏から叩いて面を起こす「打出し」を組み合わせる技法です。職人は片切り、毛彫り、魚々子で陰影と質感を設計し、鏡面との対比で光を制御します。純金は軟らかいため、焼きなましと刃の目立てを繰り返し、バリ取りや面直しも丁寧に行います。
意匠は象嵌と併用すると奥行きが増し、指輪や根付金具でも一点物の表情となります。仕上げはサテンと鏡面を使い分け、磨きで線が消えないよう彫りの深さと角度を一定に保たなければいけません。
研磨技術
研磨は、金の表面を研磨剤とバフで段階的に整え、荒研ぎ、中研ぎ、仕上げで小さな傷を除去し、鏡面やサテンなど狙いの質感にする工程です。純金は軟らかく発熱しやすいため、圧と回転数を抑え、石留め部はマスキングし、仕上げ後は超音波洗浄で残りかすを除去します。
鏡面仕上げは映り込みで面の粗が目立ちやすいため、平面を均一にして行うことが重要です。ヘアライン研磨は一定方向に筋目を通し、マットとの対比で意匠を際立たせます。最後に酸洗いで酸化膜を落とし、再研磨で面を整え、エッジのだれや歪みを防ぎます。
サンドブラスト加工
サンドブラスト加工は、金属表面に微細な研磨材を高圧で吹き付け、光の反射を拡散させて落ち着いたマットな質感を作ります。鏡面仕上げとは対照的で、部分的に用いると光沢部とのコントラストで意匠が際立ちます。表面は微細な凹凸が増えるため汚れが付きやすく、落としにくいです。
美しい状態を長く保つには、柔らかい布での乾拭きと定期的な洗浄を心掛けるとよいでしょう。細かな傷が目立ちにくい利点もありますが、皮脂や化粧品の残留はくすみの原因となりやすいでしょう。使用後は中性洗剤で軽く洗い、十分に乾燥させて保管してください。研磨剤入りクロスや硬いブラシの使用は避けましょう。
ネイルサンド工程
ネイルサンド工程は、専用機のダイヤモンド針で金属表面を連続的に打ち、無数の微小な凹凸を形成する方法です。この凹凸が多数の反射面となり、光を受けるたびに星のようなきらめきを放ちます。サンドブラストより粗い質感ながら、より強い輝きを生み出す特殊な表面加工です。
ジュエリーでは、表面を華やかに見せたい部位に施すと効果的で、金本来の柔らかな光と相まって豪奢で立体的な印象を与えるでしょう。加工は光沢仕上げとの対比で効果が高まり、デザイン全体の存在感を強めます。表面全体に施すと強いきらめきが生まれ、部分使いでは焦点が生まれてデザインの魅力が一段と引き立ちます。
マット加工
マット加工は、金属表面の光沢を意図的に抑えて、落ち着いた質感に仕上げる技法の総称です。サンドブラストはマット加工の一種で、ほかにヘアライン仕上げ(細かな筋目を通す)や薬品エッチング(薬剤で表面を腐食させて艶を落とす)があります。結婚指輪では指紋や小傷が目立ちにくく、鏡面との対比で奥行きを強められます。同じ金製品でも印象が変わり、落ち着いた高級感を与えるでしょう。
部分的に用いると光の当たり方に抑揚が生まれ、輪郭が引き締まります。仕上げ後は汚れが残りやすいため、柔らかい布で拭き取り、定期的に洗浄すると美しく保てます。
伸線加工
伸線加工は、金属を線状に伸ばす方法です。延性に富む金は極細線まで引き延ばせます。金を棒状に整え、穴の開いたダイス(切削を行う工具)に順次通して引き、直径を段階的に小さくしながら均一な太さに仕上げているのが特徴です。
こうしてできた金線はチェーンやネックレス、金網細工、繊細なフィリグリー装飾に使われます。現代は機械化が進んでいますが、江戸時代には金糸として西陣織などに織り込まれ、工芸で重宝されてきました。中間焼きなましを挟むと、伸びと強度のバランスが整います。
プレス加工
プレス加工は、金の板材を金型とプレス機で圧力をかけて成形する方法です。打ち抜きや曲げ、絞り、刻印を組み合わせ、同じ形状を量産できます。金は軟らかく、スプリングバックが小さい反面、バリや歪みが出やすいため、クリアランス管理と中間焼鈍、面取り・研磨の徹底が重要です。
貨幣の打刻やジュエリーの台座・留め具に広く用いられます。工程設計では板厚と必要トン数、潤滑、金型表面処理が、歩留まりを左右します。順送型なら透かしや立体ロゴも安定再現でき、K18などの合金は硬度差に応じて条件の最適化が必要です。
フィリグリークラフト
フィリグリークラフトは、髪の毛ほど細い金の線を「ねじった線」と「まっすぐな線」に分け、渦巻きや草花の形に曲げて土台に固定していく透かし模様の技法です。金の線は熱を加えてやわらかくし、ピンセットで少しずつ形をそろえます。細かな粒や凹凸を加えることで影が出て、ツヤのある部分と落ち着いた質感の部分を組み合わせ、光の見え方を設計できます。外側には枠を付けて強度を持たせ、仕上げ前に表面の汚れをきれいに落とします。
線の太さはデザインに合わせて微調整し、最後は専用の研磨でツヤを整えます。金属をつなぐポイントは必要最小限にとどめ、重さや変形を抑えることが大切です。角が丸くなりすぎないように注意し、全体の線が均一に立ち上がるように仕上げます。
砂型鋳造
砂型鋳造は、砂で作った型に溶けた金属を流し込み、冷まして取り出す作り方です。砂の型は自由な形を作りやすく、金の延べ棒や小物づくりにも向いています。表面のざらつきや縮みは、型をしっかり固めて流し込みやすい道を作ることで減らすことができます。
ただし、細かな寸法や表面のなめらかさは金属の型を使う方法より劣りやすいです。そのため、空気抜きの道を確保し、型の表面にコーティングをして、適切な温度で流し込むことが大切になります。少量生産や試作に向いており、仕上げは研磨で整えると見映えが良くなる傾向にあります。
金の価値が高い理由

金の価値は、希少性と腐食しにくい物性、実物資産としての信頼、宝飾品から電子部品までの広い需要、国際市場での高い換金性に支えられます。
ここからはなぜ金の価値が高いのかを解説いたします。
希少性が高く重宝される
金は地球上の存在量が限られ、その希少性が価値の源泉です。生成は隕石の衝突など特殊な条件に依存し、大規模な採掘は容易ではありません。古代は重機がなく、人力で川底の砂金を集めたり坑道を掘っていましたが、得られる金の量はごくわずかでした。
現在も世界の年間産出量は大きくは増えておらず、新鉱脈の発見も少ないです。そのため、需給面から価格が高くなりやすい傾向があります。
この入手困難さは古代から権力者や富裕層の憧れにつながり、金は宝飾品と通貨の両面で特別に扱われてきました。供給の制約と需要の高さが価格を押し上げています。
世界情勢に左右されにくく信用が高い
金の価値を支えるもう1つの要因は、その高い信用力です。金は古来より、世界各地で通用する実物資産として認められ、発行体の信用に依存しません。極端なインフレや世界情勢が不安定な場合でも資産防衛の手段として機能します。株価が不安定な局面や通貨安のときは、安全資産として買われやすく、価格が上がる場合も多く見受けられます。
純度や重量は国境を越えても広く普遍的に評価され、換金のしやすさもポイントです。錆びにくく、劣化しにくい性質も、長期の保存と価値の維持を支えるポイントです。こうした特性は時代と地域を超えて金の信用を裏打ちし、資産としての位置付けを安定させるでしょう。
柔らかく加工がしやすい
金は延性が極めて高く、薄く延ばしたり細く伸ばしたりできる金属です。用途は宝飾品にとどまらず、工芸や建築の装飾、電子部品の配線や接点にも及びます。用途の広さは需要の大きさに直結し、市場価値を押し上げます。また、加工のしやすさによって古代から数多くの工芸品・美術品が生まれ、価値の蓄積が進みました。
金は世界中で使用されており、時代や地域を超えて評価が保たれてきました。熱や腐食に強い耐性があることも、素材としての信頼を支えます。再加工や修理にも適し、耐久性も高いです。この「美しく加工しやすい金属」という特性が、金を長く珍重させてきた理由といえるでしょう。
流動性が高く、投資にも適している
金は資産としての流動性が高く、現金化のしやすさが価値を支えます。地金や金貨は世界各地で換金でき、価格情報も即時に近い形で共有されるため、運用上の扱いやすさがある資産です。値動きは株式や不動産より穏やかで、大幅下落が起こりにくいので、長期的にはインフレに耐えられるという特性があります。
そのため、中央銀行は外貨準備の一部として保有し、個人も資産配分の一部に組み入れる例が多く、投資対象としての人気も根強いです。換金性と価格の安定性が評価を高め、長期の資産形成でも役割を果たします。市場全体の不確実性が高い局面でも分散効果を期待できるとされています。
まとめ
古代の遺産から現代の金融市場まで、金は特別な輝きを放ち、人類史と切り離せない存在です。シュメールやエジプトで磨かれた金工の高度な技術は、工芸の現場で今も受け継がれ続けています。日本でも大仏の鍍金や貨幣制度の整備に深く関わり、社会と文化を形づくってきました。希少性と美観に加え、時を超える信用が価値を支えてきました。
現代の投資や外貨準備でも、その位置付けは揺らいでいません。長い時間軸で見ても、価値の保存手段として機能してきました。多くの人々に選ばれています。歴史と技術、価値の背景を知れば、手にする金製品や資産としての金への理解と愛着が一層深まるでしょう。
「おたからや」での金の参考買取価格
ここでは、「おたからや」での「金」の参考買取価格の一部を紹介します。
2026年02月04日14:00更新
今日の金1gあたりの買取価格相場表
| 金のレート(1gあたり) | ||
|---|---|---|
| インゴット(金)27,948円 +1520円 |
24金(K24・純金)27,724円 +1507円 |
23金(K23)26,662円 +1450円 |
| 22金(K22)25,489円 +1387円 |
21.6金(K21.6)24,874円 +1353円 |
20金(K20)22,750円 +1238円 |
| 18金(K18)20,933円 +1138円 |
14金(K14)16,210円 +882円 |
12金(K12)12,577円 +684円 |
| 10金(K10)11,235円 +611円 |
9金(K9)10,089円 +548円 |
8金(K8)7,490円 +407円 |
| 5金(K5)3,633円 +197円 |
||
※上記の買取価格はあくまで参考価格であり、市場の動向、
付属品の有無などによって実際の査定額が変動する場合があります。
※状態や付属品の有無、時期によって買取価格が異なりますので詳細はお問い合わせください。
金製品の査定では純度(K24やK18等)と重量が最も重要で、ブランド刻印やデザイン性は加点項目となります。
表面の擦れやサイズ直しの履歴は減額につながり、保証書や刻印を整えて店頭でご相談いただくと相場を踏まえた適正な査定が可能です。
- おたからや査定員のコメント
金は古代メソポタミアの象嵌技法から現代ETFまで価値を保ち続けています。純度と重量のわかりやすさが信用を支え、為替と国際相場で即換金できる流動性も魅力です。
刻印が鮮明で傷が少ないインゴットやブランドジュエリーはプレミアがつきやすいため、証明書を保管し、使用後は乾拭きして個装ポーチで防湿保管すると査定上限を狙いやすくなります。

金の買取なら「おたからや」
「おたからや」では、インゴットや純金コイン、K18やK14のジュエリーから、歪んだリングや刻印が薄れたスクラップまで幅広く査定可能です。専門知識豊富な鑑定士が純度を正確に測定し、ロンドン金価格や東京商品取引所の最新相場を反映した高水準の査定額をご提示します。
公正に評価する体制が整っているため、書類等の付属品がなくてもご安心ください。査定は完全無料・予約不要、ご成約後は最短即日で現金化いたします。大切な金製品を納得の価格で売却したい方は、豊富な実績を誇る「おたからや」へぜひご相談ください。
おたからやの金買取
査定員の紹介
伊東 査定員

-
趣味
ショッピング
-
好きな言葉
有言実行
-
好きなブランド
ハリーウィンストン
-
過去の買取品例
おりん、インゴット
初めまして。査定員の伊東と申します。 おたからやでは金の買取をする際に、今日の金の1gの買取相場を基に、デザイン性などをプラスで評価して高価買取を行っております。過去に1万点以上の査定をさせていただきましたが、とても多くのお客様に想像以上の金額になったと喜んでいただきました。また、おたからやでは、すべての店舗に比重計を完備しているため、金の含有量を正確に測定することができます。 金額はもちろんのこと、接客も最高のおもてなしができるように心がけております。私共はお品物だけではなくお客様一人ひとりの思いに寄り添い満足して帰っていただけるように丁寧な説明を致します。誠心誠意対応させていただきますので、是非おたからやのご利用をお待ちしております。
その他の査定員紹介はこちら金を高く売るためのコツは、「金の価格が高いときに売ること」と「高値で買い取ってくれる専門店に売ること」です。金の価格は現在非常に高騰しているため、売却にはベストなタイミングといえます。
金の高価買取はおたからやにお任せください。
関連記事
タグ一覧
- #4℃
- #A.ランゲ&ゾーネ
- #GMTマスター
- #IWC
- #K10(10金)
- #K14(14金)
- #K22(22金)
- #K24(純金)
- #MCM
- #Van Cleef & Arpels
- #アクアノート
- #アクアマリン
- #アメジスト
- #アルハンブラ
- #アルマーニ
- #アンティーク時計
- #イエローゴールド
- #インカローズ
- #ヴァシュロンコンスタンタン
- #ヴァレンティノ
- #ヴァンクリーフ&アーペル
- #エアキング
- #エクスプローラー
- #エメラルド
- #エルメス
- #エルメス(時計)
- #オーデマ ピゲ
- #オパール
- #オメガ
- #お酒
- #ガーネット
- #カイヤナイト
- #カルティエ
- #カルティエ(時計)
- #グッチ
- #グリーンゴールド
- #クロエ
- #クロムハーツ
- #クンツァイト
- #ケイトスペード
- #ケリー
- #コーチ
- #ゴヤール
- #サファイア
- #サブマリーナー
- #サマンサタバサ
- #サンローラン
- #シードゥエラー
- #ジェイコブ
- #シチズン
- #シトリン
- #ジバンシィ
- #ジミーチュウ
- #ジャガールクルト
- #シャネル
- #シャネル(時計)
- #ジュエリー
- #ジュエリー買取
- #ショーメ
- #ショパール(時計)
- #スカイドゥエラー
- #スピネル
- #スフェーン
- #セイコー
- #ゼニス
- #セリーヌ
- #その他
- #ターコイズ
- #ターノグラフ
- #ダイヤモンド
- #タグ・ホイヤー
- #タンザナイト
- #チェリーニ
- #チューダー
- #ディオール
- #ティソ
- #デイデイト
- #デイトジャスト
- #デイトナ
- #ティファニー
- #ティファニー
- #トリーバーチ
- #トルマリン
- #ノーチラス
- #バーキン
- #バーバリー
- #パテック フィリップ
- #パネライ
- #ハミルトン
- #ハリーウィンストン
- #ハリーウィンストン(時計)
- #バレンシアガ
- #ピーカブー
- #ピアジェ
- #ピコタン
- #ピンクゴールド
- #フェンディ
- #ブライトリング
- #プラダ
- #プラチナ
- #フランクミュラー
- #ブランド品
- #ブランド品買取
- #ブランド時計
- #ブランパン
- #ブルガリ
- #ブルガリ(時計)
- #ブレゲ
- #ペリドット
- #ボーム&メルシェ
- #ボッテガヴェネタ
- #ポメラート
- #ホワイトゴールド
- #マークジェイコブス
- #マトラッセ
- #ミュウミュウ
- #ミルガウス
- #メイプルリーフ金貨
- #モーブッサン
- #ヨットマスター
- #リシャールミル
- #ルイ・ヴィトン
- #ルビー
- #レッドゴールド
- #ロエベ
- #ロレックス
- #ロンシャン
- #ロンジン
- #出張買取
- #地金
- #宝石・ジュエリー
- #宝石買取
- #時計
- #珊瑚(サンゴ)
- #相続・遺品
- #真珠・パール
- #色石
- #財布
- #金
- #金・プラチナ・貴金属
- #金アクセサリー
- #金インゴット
- #金の純度
- #金価格・相場
- #金歯
- #金縁メガネ
- #金貨
- #金買取
- #銀
- #銀貨
- #香水

知りたくありませんか?
「おたからや」が

写真1枚で査定できます!ご相談だけでも大歓迎!





































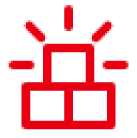

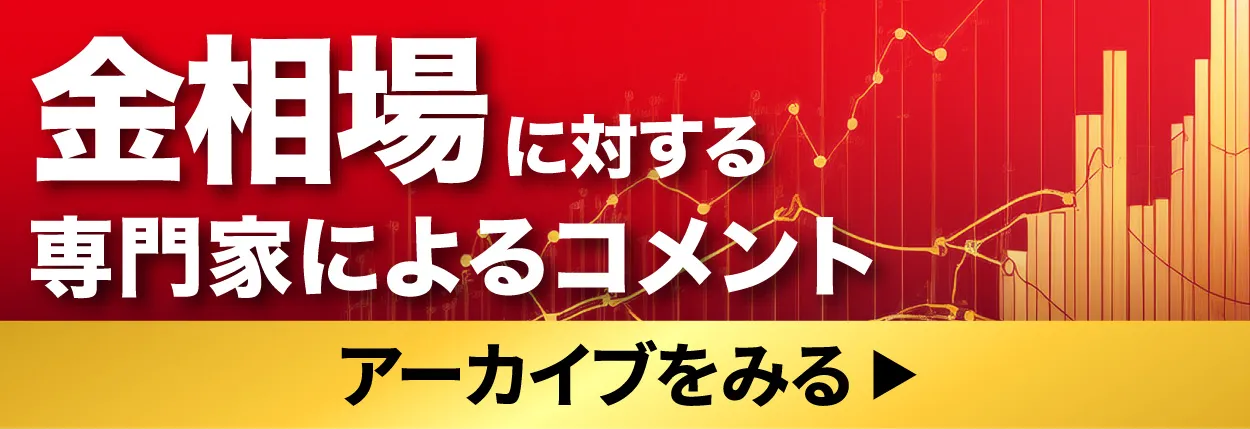
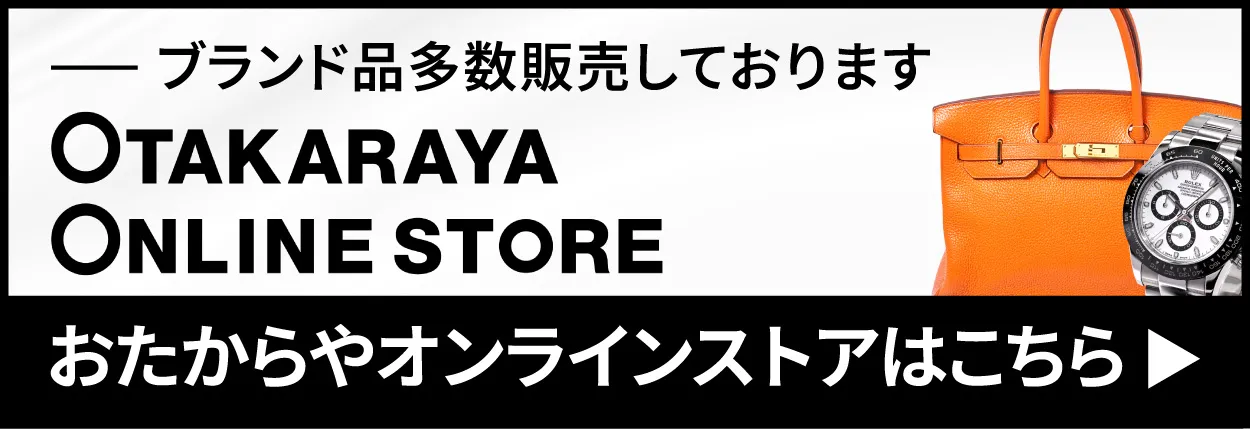
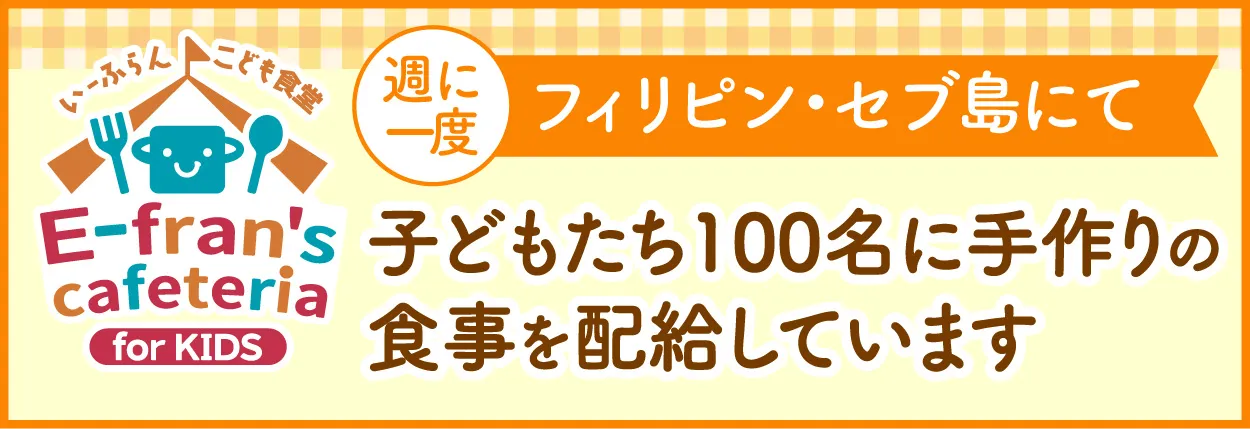

 金・インゴット買取
金・インゴット買取 プラチナ買取
プラチナ買取 金のインゴット買取
金のインゴット買取 24K(24金)買取
24K(24金)買取 18金(18K)買取
18金(18K)買取 バッグ・ブランド品買取
バッグ・ブランド品買取 時計買取
時計買取 宝石・ジュエリー買取
宝石・ジュエリー買取 ダイヤモンド買取
ダイヤモンド買取 真珠・パール買取
真珠・パール買取 サファイア買取
サファイア買取 エメラルド買取
エメラルド買取 ルビー買取
ルビー買取 喜平買取
喜平買取 メイプルリーフ金貨買取
メイプルリーフ金貨買取 金貨・銀貨買取
金貨・銀貨買取 大判・小判買取
大判・小判買取 硬貨・紙幣買取
硬貨・紙幣買取 切手買取
切手買取 カメラ買取
カメラ買取 着物買取
着物買取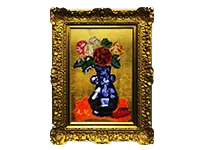 絵画・掛け軸・美術品買取
絵画・掛け軸・美術品買取 香木買取
香木買取 車買取
車買取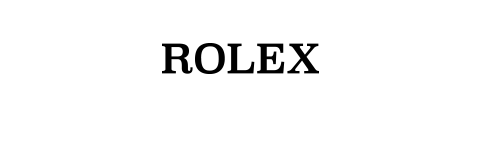 ロレックス買取
ロレックス買取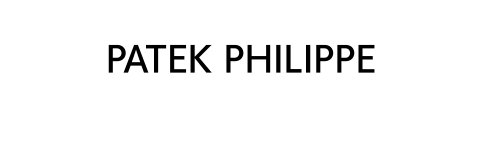 パテックフィリップ買取
パテックフィリップ買取 オーデマピゲ買取
オーデマピゲ買取 ヴァシュロン コンスタンタン買取
ヴァシュロン コンスタンタン買取 オメガ買取
オメガ買取 ブレゲ買取
ブレゲ買取 エルメス買取
エルメス買取 ルイ・ヴィトン買取
ルイ・ヴィトン買取 シャネル買取
シャネル買取 セリーヌ買取
セリーヌ買取 カルティエ買取
カルティエ買取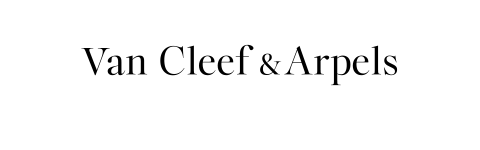 ヴァンクリーフ&アーペル買取
ヴァンクリーフ&アーペル買取 ティファニー買取
ティファニー買取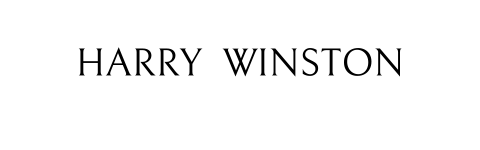 ハリー・ウィンストン買取
ハリー・ウィンストン買取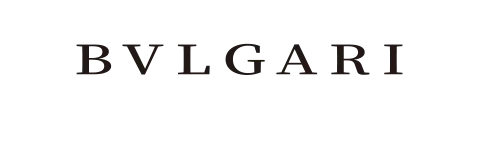 ブルガリ買取
ブルガリ買取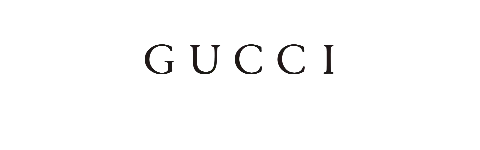 グッチ買取
グッチ買取
 ご相談・お申込みはこちら
ご相談・お申込みはこちら