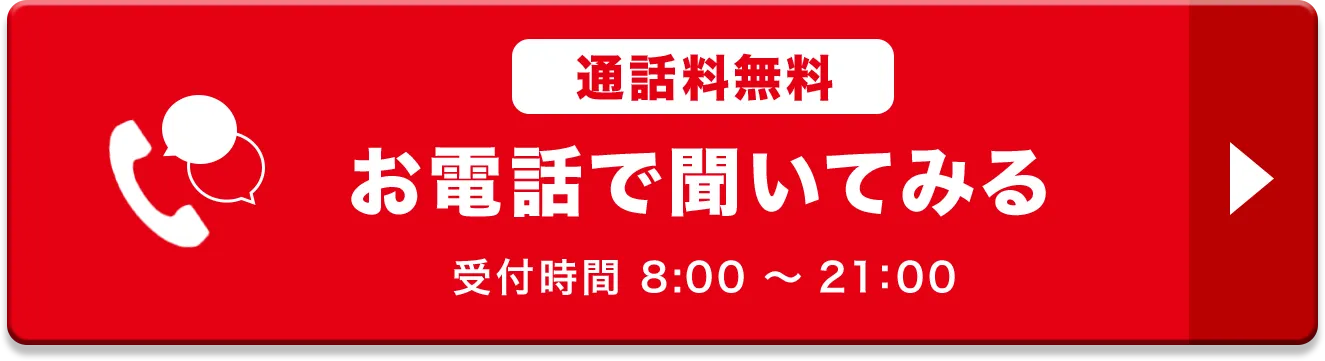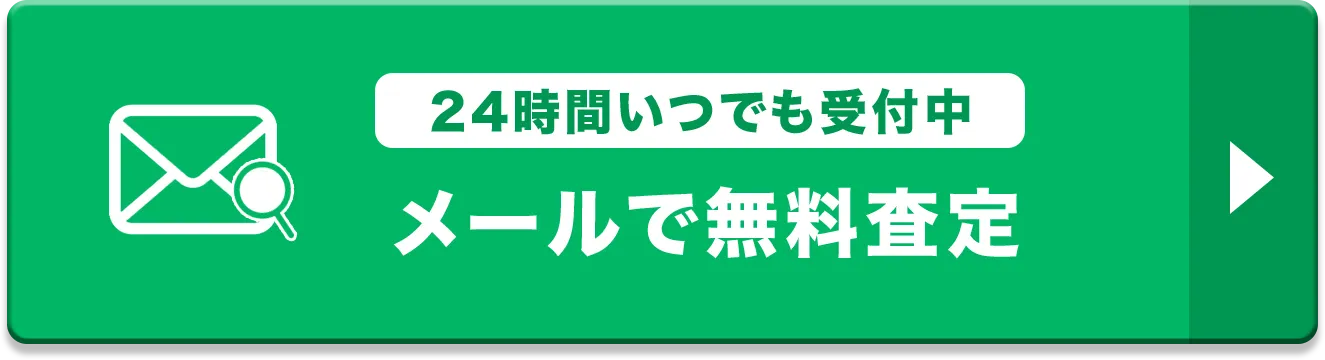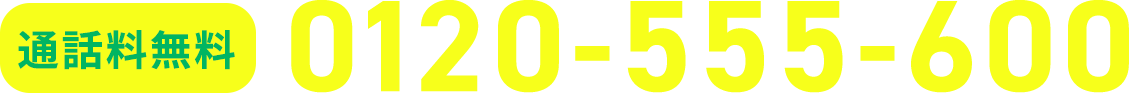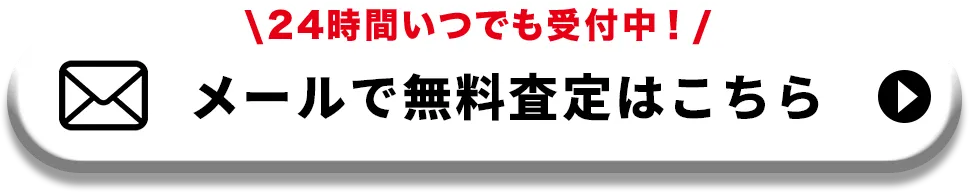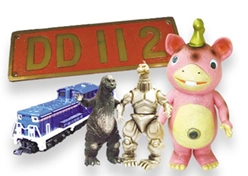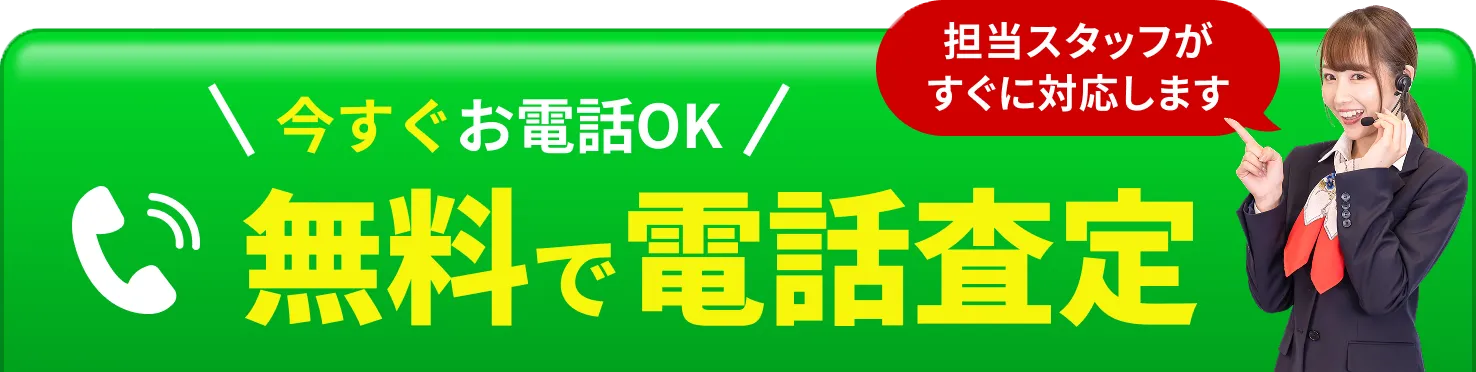※下記の画像は全てイメージです
ダイヤモンドは硬度が高く、地球上で最も硬い物質として知られています。
その「硬さ」は、「絆の強さ」や「永遠の象徴」として、数々の名言やことわざで用いられてきました。
一方で、「ダイヤモンドは、実は脆くて割れやすい」という話を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのため、「ダイヤモンドは本当に硬いの?」「それとも脆いの?」と疑問を持たれる方も少なくありません。
この記事では、ダイヤモンドをはじめとする宝石の硬度について、わかりやすく解説いたします。
Contents
宝石の硬さの程度を示す硬度

ダイヤモンドをはじめとする宝石において、「硬度」は非常に重要な要素です。
硬度とは、物体の硬さの程度を示す指標であり、宝石の耐久性を評価する上で欠かせない基準となります。
硬度には主に、物体同士の擦れにより生じる傷付きやすさを測定する「引っ掻き硬さ」と、外部からの圧力にどれだけ耐えられるかを測定する「押し込み硬さ」の2つの測定法があります。
「引っ掻き硬さ」の代表例としてモース硬度という測定法があり、「押し込み硬さ」には、ビッカーズ硬度やヌープ硬度という測定法が存在します。
ここでは、それぞれの硬度の種類について詳しく解説いたします。
モース硬度
モース硬度(Mohs hardness、単位:mohs)は、鉱物の「引っ掻き硬さ」を示す指標で、鉱物を硬さの低い順に1から10まで番号付けしたものです。
この指標は、ドイツの鉱物学者フリードリッヒ・モースによって考案されました。
一般的に「ダイヤモンドの硬度は10」として知られているのは、このモース硬度を指しています。
モース硬度の最大値である10に位置するのがダイヤモンドであり、硬度10の宝石はダイヤモンド以外には存在しません。
ただし、モース硬度は、絶対的な評価の尺度ではなく、物質間の「引っ掻き硬さ」を相対的に比較したものです。
例えば、硬度9の鉱物であるコランダム(ルビーやサファイア)は、硬度10のダイヤモンドで擦ると傷が付きますが、硬度8のトパーズで擦っても傷が付きません。
このように、モース硬度は、鉱物同士の硬さを比較することで評価されます。
ビッカース硬度
ビッカース硬度(Vickers Hardness、単位:Hv)は、物質の「押し込み硬さ」を表す指標です。
この硬さは、ビッカース硬度計という試験機を用いて測定されます。
具体的には、ダイヤモンド製の正四角錐の頂点を対象物に一定の圧力で押し付け、その際にできた窪みの大きさから硬さを数値化します。
この数値が大きいほど、物質が硬いことを示します。
また、ジュエリーの分野では、主に金やプラチナなどの地金の硬さを評価する際に用いられます。
例えば、純金の硬度は約80Hv、純プラチナは100Hv〜110Hv(いずれもジュエリー用途に仕上げ加工が施された後の値)とされており、純度の高い金はプラチナよりも柔らかい性質を持つことが分かります。
ヌープ硬度
ヌープ硬度(Knoop hardness、単位:MPaまたはN /㎟)は、ビッカース硬度と同様に「押し込み硬さ」を示す指標です。
測定方法は似ていますが、ヌープ硬度では、ダイヤモンド製の測定具が細長い菱形をした四角錐になっています。
この形状により、ビッカース硬度よりも硬さの微妙な変化を敏感に捉えることができるため、特に脆い物質の測定に適しています。
また、ジュエリーの分野では、地金の硬さには主にビッカース硬度が採用される一方で、宝石の硬さを測定する際にはヌープ硬度が用いられることが一般的です。
- おたからや査定員のコメント
宝石の耐久性を語る際は、「硬度」に加えて、「安定性」も重要な要素となります。
「安定性」とは、化学薬品、紫外線、温度や熱に対する耐性を指し、宝石の長期的な耐久性に大きく影響します。
ダイヤモンドは、この「安定性」が非常に優れており、硫酸や王水などの強力な酸にも侵されないほどの高い耐久性を持っています。

ダイヤモンドと他の宝石の硬度比較

ここでは、代表的な宝石や他の物質に関する「モース硬度」と「ヌープ硬度」の数値をご紹介いたします。
| 宝石名または鉱物名 | モース硬度 | ヌープ硬度 | 近い硬度の物質 (モース硬度) |
|---|---|---|---|
| ダイヤモンド | 10 | 5,500~6,950 | 該当なし |
| ルビー、サファイア | 9 | 1,600~2,000 | チタン |
| トパーズ | 8 | 1,250 | タングステン |
| クオーツ (アメシスト、シトリン) |
7 | 710~790 | クロム |
| オパール | 6 | 540~600 | 工具 やすり |
| アパタイト | 5 | 430~490 | ガラス(5.5) |
| フルオライト | 4 | 163 | プラチナ1000
(4.5) 18金 (~4.5) 鉄くぎ (4.5) |
| カルサイト | 3 | 135 | 銅貨 |
| 石膏、琥珀 | 2 | 32 | 24金(2.5)
爪(2.5) |
| 滑石(タルク) | 1 | 0 | 鉛 |
※一般的な値であり、実際には個体ごとの硬度のばらつきがあります。
上図から、宝石をモース硬度順に並べても、またはヌープ硬度順に並べても、どちらも同じ順序で並ぶことがわかります。
これは、モース硬度(引っ掻き硬さ)が高い宝石は、ヌープ硬度(押し込み硬さ)も高いという特性を示しています。
ただし、モース硬度は、宝石同士を擦り合わせて順位付けする「相対的」な硬度であるのに対し、ヌープ硬度は、測定器を用いて具体的な数値で示される「絶対的」な硬度です。
そのため、ヌープ硬度は、モース硬度では表せない細かな硬さの違いを把握するのに適しています。
- おたからや査定員のコメント
ヌープ硬度では、1位のダイヤモンドと2位のルビー・サファイアの間に、実に3倍以上の差があります。
このことから、モース硬度で比較した際、数値上の差は1だけですが、実際の硬さには大きな開きがあります。
モース硬度は相対的なランキングに過ぎないため、ダイヤモンドの突出した硬さを十分に表現することはできません。

ダイヤモンドが「硬いのに脆い」と言われる理由

ビッカース硬度やヌープ硬度の検査で「ダイヤモンドを押し付ける」と説明しましたが、この測定方法こそ、ダイヤモンドがほかのどんな物質よりも「硬い」性質を持つことを示す証拠です。
一方で、「ダイヤモンドは脆い」と言われることがありますが、この矛盾するように見える特性は一体なぜなのでしょうか?
ここでは、その理由を詳しく解説いたします。
「硬度が高い」=「砕けない」ではない
「硬度」とは、物質の表面の強さを示す指標であり、物質同士を擦り合わせた際の強さ(モース硬度)や、圧力を加えた際の強さ(ヌープ硬度)によって評価されます。
しかし、物質が、瞬間的な衝撃や内部への負荷に耐えられるかどうかは、「靭性(じんせい)」に大きく関係します。
靭性(じんせい)は、衝撃に対する抵抗力を示す指標で、「割れにくさ」や「欠けにくさ」に関係します。
ここで重要なのは、硬度と靭性には相関がなく、「表面の強さ」と「衝撃耐性」は、全く異なる性質を持つ点です。
例えば、ガラスのモース硬度は5.5であり、銅貨のモース硬度3よりも高いですが、ガラスを床に落とすと割れ、銅貨は割れることなく転がるだけです。
これは、ガラスの靭性が、銅貨よりも低いためです。
このように、硬度が高い物質が必ずしも砕けにくいわけではありません。
ダイヤモンドが砕ける条件
ダイヤモンドには、衝撃に弱い特定の方向が存在します。
これは「劈開(へきかい)」と呼ばれる性質で、ダイヤモンドは、正八面体の結晶構造に沿った面が割れやすいという特徴があります。
ダイヤモンドの靭性は、決して低くはありませんが、その値は方向によって異なります。
靭性スケールによる計測では、最硬度の方向で8,000の値を示す一方、劈開面に沿った方向では5,000と、大きな数値差が確認されています。
1.瞬間的な強い衝撃
劈開面に沿った力でなくても、瞬間的な強い衝撃を受けると、劈開面で損傷が生じる可能性があります。
軽い衝撃であれば、欠けや割れで済む場合もありますが、強い衝撃を受けた場合、最悪の場合には砕けてしまうこともあります。
さらに、天然のクラック(割れ)を持つクラリティ(透明度)の低いダイヤモンドは、その割れ目から裂けるリスクが高まるため、取り扱いには注意が必要です。
2.一定の方向からの衝撃
ダイヤモンドのカット職人は、この劈開の特性を利用し、特定の方向から鋭い衝撃を加えることで、意図的にダイヤモンドを分割します。
しかし、偶然にも劈開面に沿った力が加わると、強い衝撃でなくとも、同様に割れてしまう可能性があります。
これは、「ダイヤモンドのアキレス腱」とも言われる、ダイヤモンド特有の性質です。
カラーダイヤモンドや人工(合成)ダイヤモンドの硬度と靭性

ピンクやイエローなどのカラーダイヤモンドには、自然に形成されたものと人為的に色付けされたものがありますが、どちらも無色透明のダイヤモンドと硬度や靭性に違いはありません。
また、人工的に作られたダイヤモンドも、成分は天然のものと同一であり、強度に差はありません。
ただし、人工ダイヤモンドには、天然ダイヤモンドに見られるクラック(割れ)が存在しない場合が多いため、靭性が向上することもあります。
- 関連記事はこちら
・カラーダイヤモンドの価値を決める要素とは?種類別の特徴も紹介!
砕けたり傷の付いたダイヤモンドも売れる?

傷や割れのあるダイヤモンドも売却可能ですが、いくつか注意点があります。
評価項目の1つであるクラリティ(透明度)は、内包物や割れの状態を検査するものですが、後から生じた傷や欠けは、評価を下げる要因となります。
特に、評価不能なほどの欠けがある場合は、リカット(再カット)が必要となり、その際には、重量の減少やリカット費用が差し引かれるため、大幅なマイナス評価は避けられません。
さらに、砕けてしまった場合、元の石が非常に大きなものでない限り、ほとんど値段が付かない可能性がある点にも注意が必要です。
ダイヤモンドの取り扱いの注意点
ダイヤモンドを割れや欠けから守るためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。
まず、衝撃を避けることが最優先であるため、スポーツやアウトドア、力仕事などのアクティブな場面では、必ずジュエリーを外してください。
また、ダイヤモンドを保管する際は、ジュエリーケースに入れ、他のジュエリーや宝石と接触しないようにしましょう。
特に、ダイヤモンド同士で触れ合うと、傷が付く恐れがあります。
さらに、ダイヤモンドジュエリーを購入する際は、ダイヤモンドが露出しているデザインは傷が付くリスクが高いため、不安な方は、石がしっかりと保護されているデザインの商品を選ぶことをおすすめします。
- おたからや査定員のコメント
長年、ダイヤモンドジュエリーをご使用されていると、気づかないうちにぶつけて傷が付いていることがあります。
傷が付いたダイヤモンドは、購入時の鑑定書通りには評価されない場合があります。
購入から長い時間が経過している場合や、ぶつけた記憶がある方は、一度おたからやにご相談ください。
おたからやでは、汚れや傷、破損など、どのような状態のダイヤモンドでも買取対応いたしますので、安心してお任せください。

- 関連記事はこちら
・ダイヤモンドのくすみ解消!お手入れ&クリーニングで輝きを戻す方法
ダイヤモンドの買取なら「おたからや」へ
「おたからや」では、GIA(米国宝石学会)認定のGG(Graduate Gemologist)資格を持つ鑑定士が在籍しており、国際的に通用する専門知識をもとにした正確な査定が可能です。
ダイヤモンドをはじめとする、お客様の大切な宝石やジュエリーを最大限に評価し、ご納得いただける買取価格をご提示いたします。
また、鑑定書や鑑別書がなくても買取が可能なため、どなたでも安心してご相談いただけます。
店頭買取だけでなく、便利な出張買取やWEB査定にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
おたからやの宝石買取
査定員の紹介
岩松 査定員

-
趣味
旅行、読書
-
好きな言葉
日々是好日
-
好きなブランド
ダイヤモンド・宝石
-
過去の買取品例
10カラットダイヤモンド
-
資格
GIA G.G.取得
おたからやでは毎日大小合わせて約数百点の宝石を査定しております。宝石はダイヤモンドの4Cをはじめとして色や形、重さ蛍光性など様々な要素で評価額が大きく変わります。おたからやは自社でオークションを行っており、日々の宝石の需要に敏感に対応することができます。 査定に関してもプロのスタッフやダイヤモンドテスターなどの専門の査定具を完備しているため、全国の店舗ですぐに正確な査定が可能です。 気になるお品物がございましたら是非おたからやをご利用ください。
その他の査定員紹介はこちらダイヤモンドなどの宝石の高価買取は「おたからやへ」
関連記事
タグ一覧
- #4℃
- #A.ランゲ&ゾーネ
- #GMTマスター
- #IWC
- #K10(10金)
- #K14(14金)
- #K22(22金)
- #K24(純金)
- #MCM
- #Van Cleef & Arpels
- #アクアノート
- #アクアマリン
- #アメジスト
- #アルハンブラ
- #アルマーニ
- #アンティーク時計
- #イエローゴールド
- #インカローズ
- #ヴァシュロンコンスタンタン
- #ヴァレンティノ
- #ヴァンクリーフ&アーペル
- #エアキング
- #エクスプローラー
- #エメラルド
- #エルメス
- #エルメス(時計)
- #オーデマ ピゲ
- #オパール
- #オメガ
- #お酒
- #ガーネット
- #カイヤナイト
- #カルティエ
- #カルティエ(時計)
- #グッチ
- #グリーンゴールド
- #クロエ
- #クロムハーツ
- #クンツァイト
- #ケイトスペード
- #ケリー
- #コーチ
- #ゴヤール
- #サファイア
- #サブマリーナー
- #サマンサタバサ
- #サンローラン
- #シードゥエラー
- #ジェイコブ
- #シチズン
- #シトリン
- #ジバンシィ
- #ジミーチュウ
- #ジャガールクルト
- #シャネル
- #シャネル(時計)
- #ジュエリー
- #ジュエリー買取
- #ショーメ
- #ショパール(時計)
- #スカイドゥエラー
- #スピネル
- #スフェーン
- #セイコー
- #ゼニス
- #セリーヌ
- #その他
- #ターコイズ
- #ターノグラフ
- #ダイヤモンド
- #タグ・ホイヤー
- #タンザナイト
- #チェリーニ
- #チューダー
- #ディオール
- #ティソ
- #デイデイト
- #デイトジャスト
- #デイトナ
- #ティファニー
- #ティファニー
- #トリーバーチ
- #トルマリン
- #ノーチラス
- #バーキン
- #バーバリー
- #パテック フィリップ
- #パネライ
- #ハミルトン
- #ハリーウィンストン
- #ハリーウィンストン(時計)
- #バレンシアガ
- #ピーカブー
- #ピアジェ
- #ピコタン
- #ピンクゴールド
- #フェンディ
- #ブライトリング
- #プラダ
- #プラチナ
- #フランクミュラー
- #ブランド品
- #ブランド品買取
- #ブランド時計
- #ブランパン
- #ブルガリ
- #ブルガリ(時計)
- #ブレゲ
- #ペリドット
- #ボーム&メルシェ
- #ボッテガヴェネタ
- #ポメラート
- #ホワイトゴールド
- #マークジェイコブス
- #マトラッセ
- #ミュウミュウ
- #ミルガウス
- #メイプルリーフ金貨
- #モーブッサン
- #ヨットマスター
- #リシャールミル
- #ルイ・ヴィトン
- #ルビー
- #レッドゴールド
- #ロエベ
- #ロレックス
- #ロンシャン
- #ロンジン
- #出張買取
- #地金
- #宝石・ジュエリー
- #宝石買取
- #時計
- #珊瑚(サンゴ)
- #相続・遺品
- #真珠・パール
- #色石
- #財布
- #金
- #金・プラチナ・貴金属
- #金アクセサリー
- #金インゴット
- #金の純度
- #金価格・相場
- #金歯
- #金縁メガネ
- #金貨
- #金買取
- #銀
- #銀貨
- #香水

知りたくありませんか?
「おたからや」が

写真1枚で査定できます!ご相談だけでも大歓迎!





































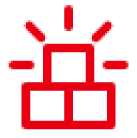

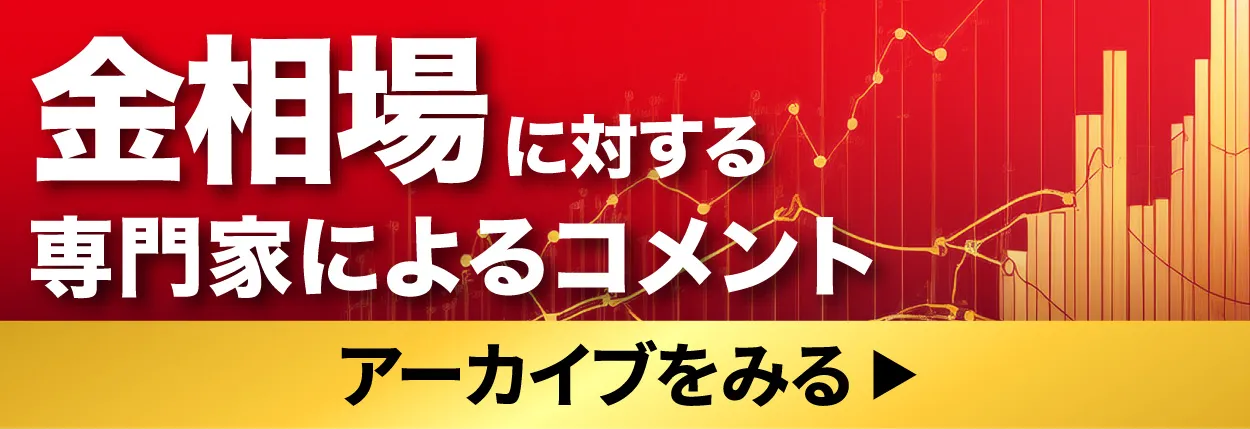
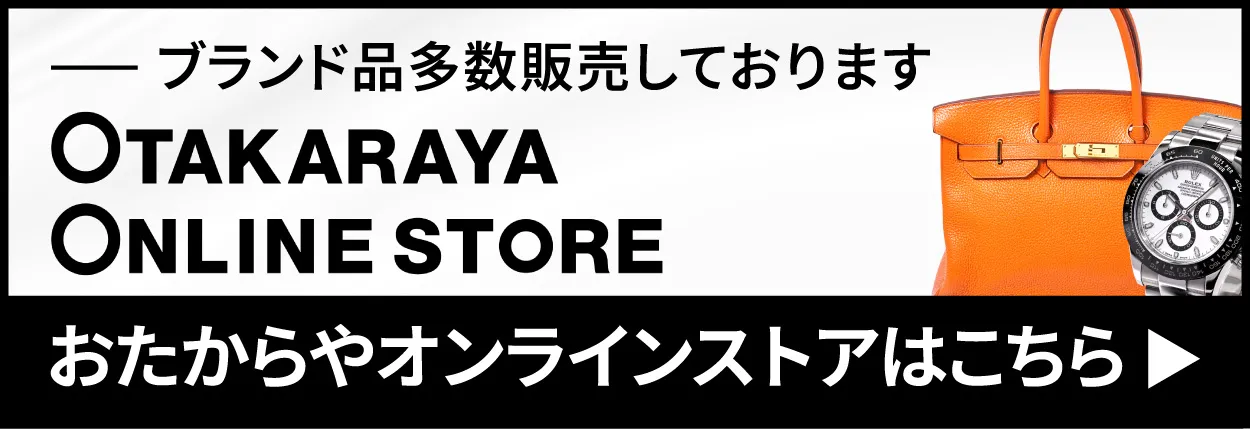
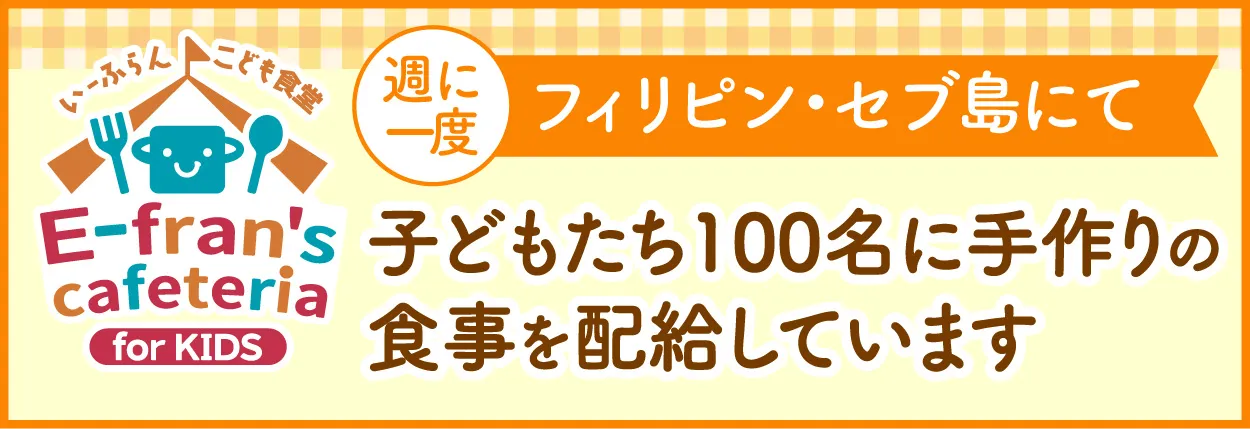

 金・インゴット買取
金・インゴット買取 プラチナ買取
プラチナ買取 金のインゴット買取
金のインゴット買取 24K(24金)買取
24K(24金)買取 18金(18K)買取
18金(18K)買取 バッグ・ブランド品買取
バッグ・ブランド品買取 時計買取
時計買取 宝石・ジュエリー買取
宝石・ジュエリー買取 ダイヤモンド買取
ダイヤモンド買取 真珠・パール買取
真珠・パール買取 サファイア買取
サファイア買取 エメラルド買取
エメラルド買取 ルビー買取
ルビー買取 喜平買取
喜平買取 メイプルリーフ金貨買取
メイプルリーフ金貨買取 金貨・銀貨買取
金貨・銀貨買取 大判・小判買取
大判・小判買取 硬貨・紙幣買取
硬貨・紙幣買取 切手買取
切手買取 カメラ買取
カメラ買取 着物買取
着物買取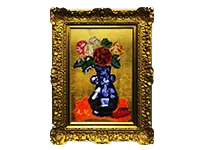 絵画・掛け軸・美術品買取
絵画・掛け軸・美術品買取 香木買取
香木買取 車買取
車買取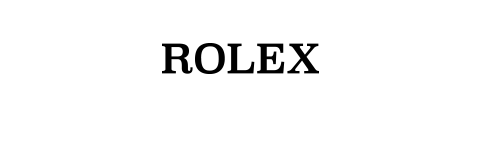 ロレックス買取
ロレックス買取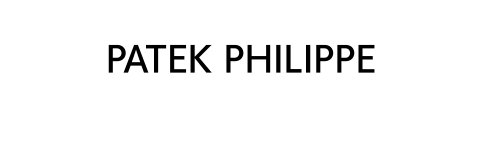 パテックフィリップ買取
パテックフィリップ買取 オーデマピゲ買取
オーデマピゲ買取 ヴァシュロン コンスタンタン買取
ヴァシュロン コンスタンタン買取 オメガ買取
オメガ買取 ブレゲ買取
ブレゲ買取 エルメス買取
エルメス買取 ルイ・ヴィトン買取
ルイ・ヴィトン買取 シャネル買取
シャネル買取 セリーヌ買取
セリーヌ買取 カルティエ買取
カルティエ買取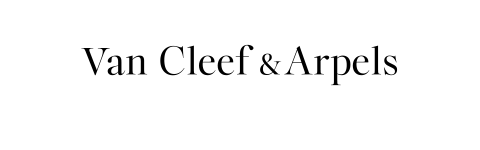 ヴァンクリーフ&アーペル買取
ヴァンクリーフ&アーペル買取 ティファニー買取
ティファニー買取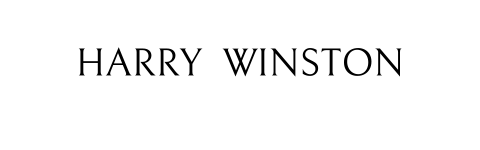 ハリー・ウィンストン買取
ハリー・ウィンストン買取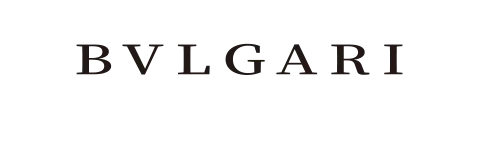 ブルガリ買取
ブルガリ買取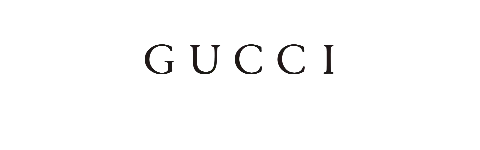 グッチ買取
グッチ買取
 ご相談・お申込みはこちら
ご相談・お申込みはこちら