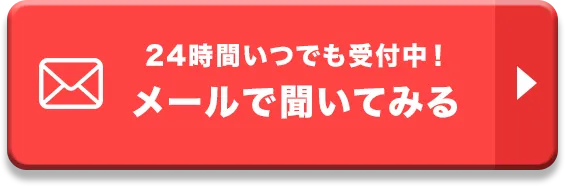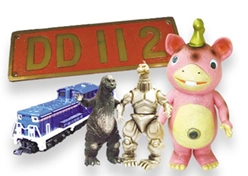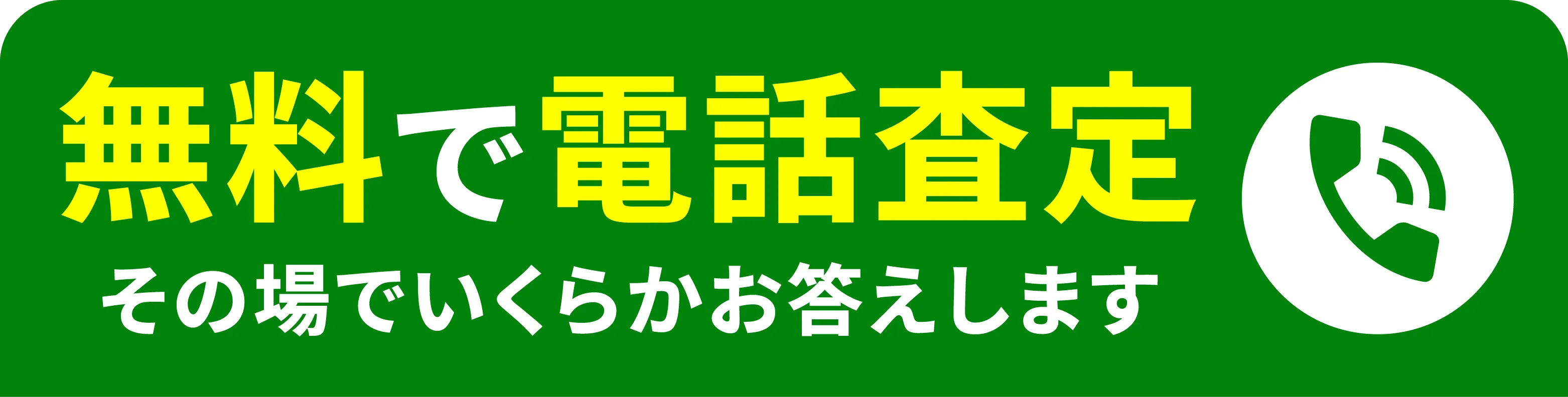金の産出国
ランキングトップ10!
実は日本が埋蔵量世界一に
なれるかもしれない
理由も解説?

※下記の画像は全てイメージです
2025年06月16日に金の買取価格が史上初めて17,508円を記録するなど、今注目が集まる「金」。今後の金相場はどうなっていくのか気になる方もいるでしょう。
金の産出量は、金の相場を決定する要因の一つです。金の相場の先行きを予想するなら、代表的な金の産出国と、各国の産出量の推移について知っておきましょう。
今回は、金の産出国ランキングや産出量の推移、産出量と金相場の関係について解説します。金で資産運用を行なっている方や、これから資産運用を始めたい方はぜひチェックしてみてください。
Contents
【2022年度版】
金の産出国
ランキングトップ10
まずは2022年の金産出量トップ10から紹介します。
| 順位 | 国名 | 生産量 |
|---|---|---|
| 1位 | 中華人民共和国 | 330t |
| 2位 | オーストラリア ロシア |
320t |
| 4位 | カナダ | 220t |
| 5位 | アメリカ合衆国 | 170t |
| 6位 | カザフスタン メキシコ |
120t |
| 8位 | 南アフリカ | 110t |
| 9位 | ペルー ウズベキスタン |
100t |
出典:U.S. Geological Survey「Mineral Commodity Summaries 2023」
2022年、金の産出量世界第1位は、中華人民共和国(中国)です。広大な国土にはまだ未開発の地域がたくさん残っており、近年では新疆(しんきょう)ウイグル自治区で超大型金鉱の存在が確認されるなど、明るいニュースも報告されています。
中国は21世紀、富裕層割合の急増にともない、特に宝飾品の金の価値が高まったことから、国内需要が増加しました。この流れから、中国政府は外貨獲得の有力な手段として金の価値に注目し、積極的な採掘を推進しています。今後もしばらくは、中国が産出量1位を維持するでしょう。
南アフリカ共和国は、8位という結果です。以前は金の産出量世界1位の座を守っていた同国ですが、1990年代に地表近くの大部分は採掘されてしまいました。
南アフリカ共和国には、今も地下深くに金があることがわかっていますが、採掘には膨大なコストがかかり、採算が取れない状況です。現在、南アフリカの金産出量は減少傾向にあります。
金の産出量の推移とトレンド

かつて最大の金産出国であった南アフリカが衰退し、中国やオーストラリア、ロシアが台頭してきたように、各国の金産出量は年々変化しています。
例として、2005年から2022年までの17年を取り上げてみましょう。
2005年の金産出量トップは、南アフリカ共和国です。その産出量は約295t、世界の産出量の12%を占めていました。ですが、前項でも解説したように金産出量は年々減少し、2007年には世界一の座を中国に譲ります。2019年には12位にまで後退し、2020年では2005年産出量の1/3以下にまで減少しています。
2007年にトップに躍り出た中国は、その後、右肩上がりの増産を続けました。2005年時点約225tだった産出量は、2014年には倍増しています。ですがその後、環境規制強化が世界のトレンドとなった影響で、2017年を境に産出量を減少させています。
2005年に2位のオーストラリアは、2009年まで産出量が少しずつ減少していきました。その後緩やかな増加に転じ、2022年には約320tを産出しています。この間に他国の順位が激しく入れ替わりましたが、緩やかな増産を続けるオーストラリアは2009年以降2022年までほぼ2位の座をキープしています。
中国が1位の座を獲得した2007年は、金の産出に関して転換期の年といえるでしょう。2017年以降産出量を急激に伸ばしているロシアは2位のオーストラリアを猛追している一方、2005年まで3位だったアメリカは2013年にロシアに逆転を許し、その後5位が続いています。また、カナダは2011年から緩やかな増産傾向にあり、2021年にはアメリカを追い越しています。
金の世界年間産出量は、2009年までは約2,400t前後で推移していました。2010年に約2,500tを超えると、中国での急激な増産の影響により産出量が増加し、2015年には約3,000tを超えました。
2017年には約3,200tを超え、2018年の約3,300tでいったん落ち着きを見せます。その後、金の産出量は若干減少し、2021年は約3,090t、2022年は約3,100tとなっています。
各国の金採掘の歴史
ここでは、アメリカ・中国・オーストラリア・ロシア・日本での金産出に関する歴史を紹介します。
アメリカ
アメリカの金産出の歴史は、1848年のゴールドラッシュから始まります。ジェームズ・マーシャルという人物が、カリフォルニア州に流れる川で砂金を見つけたことをきっかけに金鉱脈が発見されたのです。そのため、多くの人々が一攫千金を夢見て押し寄せました。
カリフォルニア州では当時、1年で8万人も人口が増加しており、一攫千金を夢見る移住者は、年号から「フォーティナイナーズ(49ers)」と呼ばれました。ゴールドラッシュで産出された金は、世界の貨幣供給量にも影響を与え、金産出国としてのアメリカの地位を確かなものにしました。
中国
1980年代、中国政府主導により、金の採掘が本格的に始められました。それまで社会主義体制を敷いていた中国ですが、この頃には鄧小平により市場経済への移行が始まっていました。
経済の移行にともない、外貨獲得の有力手段として金の採掘が盛んになりました。採掘が本格化しておよそ20年後の2007年には、中国は金産出国として世界1位にランクされるようになったのです。
国内需要も増加傾向にある中国は、積極的に金鉱山やレアメタルの採掘を進めています。この先もしばらくは、中国産の金が世界市場に存在感を示し続けるでしょう。
中国は広い国土を持ちますが、金が産出される土地は、内モンゴル自治区・山東省・福建省・湖南省などの一部地域に限られています。これらの地域で産出される金は、中国全土での金産出量の約半分を占めているのです。
中国で最も重要な金採掘地区は、新疆ウイグル自治区にある薩瓦亜尓頓金鉱です。この金鉱は、1993年に巨大金鉱脈が発見されて以来注目を集め、大規模調査により100tクラスの金鉱であることが明らかになりました。その後の調査では、「金の埋蔵量は約127t」というデータも公表されています。
なお、薩瓦亜尓頓金鉱は「天山山脈中央アジア黄金ベルト」に位置しています。これは世界的に見ても最大級の鉱石地帯であり、ウズベキスタンやカザフスタンなど複数の国にわたって広がっています。薩瓦亜尓頓金鉱が発見されたことにより、この黄金ベルトが中国国内にも伸びていることが証明されたといえます。
オーストラリア
金産出国としてのオーストラリアの歴史は、イギリス政府との関連が強いといえるでしょう。
1770年、イギリスの探検家キャプテン・クックが現在のシドニーに到着したことをきっかけに、オーストラリアへの白人の入植が始まりました。
その当時、イギリス政府はオーストラリアに監獄を建設し、オーストラリアをイギリスの犯罪者の流刑地として使用していました。ですが、巨大金鉱の発見により、流刑地ではなく財宝が埋蔵されている大陸として注目するようになったのです。
オーストラリアはイギリス政府に自治権を要求し、独立へ向けての気運が高まりました。そして1901年、入植者たちは連邦政府を樹立し、イギリスからの独立を勝ち取ります。今のオーストラリアがあるのは、「強大金鉱の発見によるもの」といっても過言ではありません。
オーストラリアでの金発見のニュースはまたたく間に世界に広がり、イギリス・アメリカ・アジアなどから多くの人が押し寄せました。なかでも中国からの移民は約4万人と突出しています。
巨大金鉱が発見されたアメリカ・カリフォルニア州では、金がすぐに採掘しつくされたことにより、民族間紛争にまで発展しました。しかし、同様に金鉱が発見されたオーストラリアでは、金が豊富にあり多くの人へ配分されたため、トラブルや争いは少なかったといわれています。
オーストラリアでは、初期のゴールドラッシュ後も大規模金鉱が発見されました。ビクトリア州のバララットやベンディゴなどがその代表です。そのため、これらの地域は大きな経済発展を遂げています。さらに、ビクトリア州政府が「金鉱を発見した人には奨励金を支払う」という声明を発表したことにより、多くの人が押し寄せ、10年間で人口は約5倍にも達しました。
現在では、これらの金鉱は掘りつくされ閉山しています。金鉱の一部は、テーマパークに作り替えられ、観光スポットとして現在も愛されています。オーストラリアの歴史は、金採掘の歴史を抜きに語れないといえるでしょう。
ロシア
旧ソ連成立以前から、ロシアでは東部のコルィマ川中流域で砂金が採れることが知られていました。しかし、1年の半分以上が氷点下という非常に厳しい土地柄、金採掘の進展は見られませんでした。
本格的な金採掘事業の始まりは、1917年のロシア革命以降になります。当時、ソビエト共産党の方針に異議を唱える者は政治犯と烙印を押され、極寒の地シベリアへ送られていきました。流刑者たちは、厳しい環境のなか重労働を強いられたのです。
その強制労働の場所の一つが、砂金が採れるコルィマ川上流に位置するコルィマ鉱山だったのです。1928年には港も建設され、物資や労働者の受け入れ体制が確立、鉱山への街道も整備され、コルィマ鉱山で金の採掘が本格的にスタートします。
これらのインフラの建設に従事したのは、ほとんどが流刑者たちです。彼らは永久凍土が広がる極寒の地で、十分な防寒具や食料も与えられず酷使されました。
シベリアの強制収容所はナチスドイツのアウシュヴィッツと双璧をなす史上最悪の施設といわれています。ロシアの金採掘の歴史は、人類の負の遺産の側面を持つといえるでしょう。
1953年、シベリアの強制労働を主導していたスターリンの死去をきっかけに、恐怖政治が終焉を迎え、その後の数年間で、政治犯の烙印を押された人たちの名誉が回復されていきました。
ソ連崩壊後のロシアでは製造業がふるわず、ロシア経済全体が低迷期を迎えることになります。この時期も規模を縮小しながらも金採掘は続けられました。
2000年代以降も金の採掘は継続されており、特に2007年以降の金産出量は右肩上がりの伸びを見せています。2013年以降はオーストラリアとともに、金産出量2位の座を争っています。
日本
地下資源に乏しいとされる日本も、かつては多くの金を産出してきました。14世紀「東方見聞録」のなかでも、日本は「黄金の国ジパング」と紹介されています。
戦国時代に入ると、覇権を争う武将たちが資金確保のため急激に金鉱山を開発し、金の産出量は一気に増加しました。なかでも最大の産出量を誇ったのが佐渡金山です。1603年に採掘が始まった佐渡金山は、その後400年間にわたって大量の金が産出され、まさに「黄金の国」のような様相を呈していました。
明治以降、ほとんどの鉱山から金が掘りつくされ、かつての隆盛は見られなくなります。
しかし、現在の日本の金産出量はゼロというわけではありません。今も鹿児島県の菱刈鉱山では、金の採掘が行なわれています。菱刈鉱山はほかの鉱山に比べて金含有率が高く、鉱山1tあたりおよそ4gの金を含んでいるそうです。そのため、世界でも金の産出効率がとても高い、優秀な鉱山といわれています。
金産出量の少ない日本ですが、「金鉱山」ではなく「都市鉱山」にスポットを当てると意外な事実が見えてきます。日本国内に大量に存在する多くの電子デバイスや精密機器の内部には、金が素材として使われています。廃棄された電子機器類の内部から金を取り出せば、国内でも大量の金を獲得できるのです。
回収した携帯電話1tあたりにおよそ280gの金が含まれているといわれています。一般的な鉱石1tあたりに含有される金は5g程度であるため、鉱石に比べ、なんと50倍もの金が含まれていることになります。使い捨てられた電子機器はまさに宝の山といえるでしょう。
東京オリンピック・パラリンピックでは、この都市鉱山から発掘された金・銀・銅を材料にメダルを製作するプロジェクトが進められました。
自治体や公共機関などが電子機器の回収に協力し、集められた携帯電話は約620万台、家電やガジェット類は8万t近くにもなりました。電子機器から金32㎏、銀3,500㎏、銅2,200㎏を取り出すことに成功し、東京大会のメダル約5,000個に使用されたメダルの100%が都市鉱山から回収されたものなのです。
<関連記事>日本は資源の宝庫「都市鉱山」とは!?
金の供給量と金相場の関係
ここからは金相場が変動する要因と供給量との関係を解説します。
供給量だけでは決まらない金の価格
金の供給量は金の相場に影響を与える要因の一つです。では、近年よく耳にする「金の価格が高騰中」というニュースの背景には、金の供給量の減少が影響しているのでしょうか。
実際はその逆で、金の供給量は年々増加傾向にあります。にもかかわらず、近年の金相場は高騰し続けています。金の供給量が金相場に影響を与えることは間違いありませんが、一概に金の供給量だけでは決まらないといえるでしょう。
金の価格高騰の理由とは?

一般的に、供給量が増えると物の価格は下がりますが、前項でも述べたとおり金は供給量が増えているにもかかわらず、金相場は上昇し続けています。2025年06月16日に金の買取価格が史上初めて17,508円を記録しました。金の相場が上昇している背景には、供給量の増加以上に金需要が増加していることがあります。
金は、装飾・資産投資・精密機器の製造といったさまざまな用途を持ちますが、特に近年影響しているのは投資としての価値です。
リーマンショック後、その影響を跳ね返しながら世界経済が力強く回復した頃には金融資産としての金の価値が見直され、有事に備えて金を保有する投資家が増加しました。また、2020年の新型コロナウイルス感染症の流行、2022年のロシアによるウクライナ侵攻などによる世界経済への不安も需要の後押しをしています。
資産としての安定性や信頼性が高い金は、投資先として有力であると多くの人に認識されているのです。
<関連記事>【2025年最新】金価格が高騰している理由とは?金相場の今後の見通しも解説
さらに高まる金の資産価値
金が安全資産である理由は、経済が不安定な状況でも金の価値がなくなる可能性が低い点にあります。株式などの場合、企業の倒産によって資産的価値がゼロになるリスクがありますが、金は急激にその価値が下落する可能性は低いものです。
紙である証券類は、国や会社の信用という価値を上乗せしているからこそ価値が生まれます。一方、金はそのものに価値があるため、資産としての安定性が高い点が強みです。
金は、好景気のときには装飾品としての売買が増えるなど、実体経済における需要が高まり、不景気になると投資需要が高まります。つまり金は、好景気にせよ不景気にせよ需要が高くなりやすい性質があります。
もちろん、さまざまな要因によって金相場は変動するため、一概に言えるものではありませんが、基本的には今後も金の価値は高まると考えられます。
<関連記事>金が守りの資産といわれる理由とは?おすすめの金投資方法も解説
日本人の金に対する意識の変化
世界的に見れば金の需要は高まりを見せていますが、日本人の金に対する意識は、世界とは少し異なっています。経済産業省資源エネルギー庁「貴金属流通統計調査」をもとに、2013年から2020年における、日本人の金に対する意識の変化を見ていきましょう。
2013年から2020年の日本国内での金供給量は、以下のとおりです。
日本国内における金の供給量
| 金供給量 | |
|---|---|
| 2013年 | 約127.0 |
| 2014年 | 約122.1 |
| 2015年 | 約188.7 |
| 2016年 | 約299.5 |
| 2017年 | 約337.1 |
| 2018年 | 約195.6 |
| 2019年 | 約145.0 |
| 2020年 | 約129.6 |

表とグラフを見ると、2018年に金の供給量が急増していることがわかります。一方、需要の変化を消費者需要(機械部品など)と準消費退蔵(宝飾品など)の2点で見てみると、以下のとおりとなっています。
日本国内における金の消費者需要量・消費者退蔵量
| 消費者需要 | 消費者退蔵 | |
|---|---|---|
| 2013年 | 約48.1t | 約18.5t |
| 2014年 | 約45.5t | 約13.1t |
| 2015年 | 約45.0t | 約9.1t |
| 2016年 | 約45.9t | 約12.5t |
| 2017年 | 約45.4t | 約14.1t |
| 2018年 | 約53.9t | 約17.0t |
| 2019年 | 約53.6t | 約30.2t |
| 2020年 | 約50.1t | 約27.2t |

金の供給量がここ数年で大きく変化しているのに対し、日本に限定すれば、金の需要にはそれほど変化がありません。バブル崩壊以来の長期にわたる景気低迷の影響もあり、実体経済における日本での金の需要は高くないのが現状といえます。
実体経済における金の需要が低迷する一方で、注目すべきは資産として取引きされた金の量の推移です。同期間における現物購入・現物売却された金の総量は以下のとおりとなっています。
日本国内における金の現物購入量・現物売却量
| 現物購入 | 現物売却 | |
|---|---|---|
| 2013年 | 約55.0t | 約56.5t |
| 2014年 | 約41.9t | 約35.6t |
| 2015年 | 約29.1t | 約40.7t |
| 2016年 | 約22.6t | 約36.3t |
| 2017年 | 約28.7t | 約22.3t |
| 2018年 | 約23.2t | 約30.2t |
| 2019年 | 約44.3t | 約24.4t |
| 2020年 | 約40.9t | 約37.2t |

現物購入量と現物売却量は期間はじめから徐々に数量を減らし、2018年頃から上昇に転じています。長引く不況やリーマンショック、東日本大震災などの経済危機の経験から「金は売買するものではなく資産として長期保有するもの」という意識が日本人の間で高まっているといえるでしょう。
日本経済を論評する人のなかには「今後インフレにより日本経済が破綻する」と予測する人もいます。現実にそうなるかはわかりませんが、資産として金を保有することはインフレ対策としても非常に有効です。
インフレになれば、貨幣価値が下がってしまいます。しかし、金の価値はインフレになったとしても大きな影響を受けません。証券類と異なり、金そのものに価値があるためです。
インフレになる前に、現金を金に換えておけば、インフレの影響を最小限に抑えることができ、資産の目減りを防ぎやすくなるでしょう。このような考えに基づき「金を売り買いするのでなく保有し続けるべきだ」と考える人が増えていると考えられます。
<関連記事>インフレヘッジと金の市場価格との関係
近い将来、金はなくなる?
気になる金の埋蔵量とは
今後の金相場を予想する場合、生産量だけでなく埋蔵量にも注目する必要があります。今ある金を採掘しつくしてしまえば、金は枯渇してしまうためです。
世界各国の金資源埋蔵量
| 国名 | 金資源埋蔵量 |
|---|---|
| オーストラリア | 8,400t |
| ロシア | 6,800t |
| 南アフリカ共和国 | 5,000t |
| アメリカ合衆国 | 3,000t |
| ペルー | 2,900t |
| インドネシア | 2,600t |
| ブラジル | 2,400t |
| カナダ | 2,300t |
| 中華人民共和国 | 1,900t |
| ウズベキスタン | 1,800t |
| メキシコ | 1,400t |
| パプアニューギニア | 1,100t |
| ガーナ | 1,000t |
| カザフスタン | 1,000t |
| マリ | 800t |
| その他 | 9,200t |
| 合計 | 約52,000t |
出典:U.S. Geological Survey「Mineral Commodity Summaries 2023」
地質学者のなかには、「人間が過去に採掘した金の総量は18万t。残っているのは6~7万t」と言う人もいます。現在、世界中で年3,000t程度の金が採掘されているため、およそ20年で金を掘りつくすことになるでしょう。
地球深部にはまだ多くの金が眠っている可能性があります。ですが、地球奥深くの金を採掘するには、それに応じた技術と費用が必要です。採算が合わず現実的には採掘が難しいと考えられます。
人工的な金の生産技術がない以上、金はいずれ枯渇すると予想されます。掘りつくされた後、金相場はどのように変化するのか、今後の相場に注目が集まっています。
<関連記事>金の埋蔵量は?産出量や枯渇するタイミングについて解説
金の埋蔵量世界一は日本?
日本には廃棄された電子機器が大量にあり、「都市鉱山」という点での金の埋蔵量は、世界的に見ても多いといえます。
都市鉱山にはおよそ6,800tもの金が眠っているといわれています。これらの金を回収できれば、日本は金埋蔵量世界第1位になれる可能性があるでしょう。金を回収するシステムの構築と、リサイクル技術の発達が待たれます。
まとめ
2022年の金の産出量は中国、オーストラリア、ロシアが上位を占めていますが、各国の産出量は毎年変化しています。また、金の産出量は金相場にも影響を与えています。金への投資を検討されるなら、今後どのようなペースで金が産出されていくのか注目していく必要があるでしょう。
近年、コロナショックやウクライナショックなどにより、経済への不安が高まるなか、資産としての金の価値が見直されています。実際により安定的で信頼性の高い資産を保有しようと世界的に金への需要が高まり、金はここ数年で高騰しています。2025年06月16日に金の買取価格が史上初めて17,508円を記録しました。
金が高騰している状況は、金売却の好機といえます。金を保有している方は、ぜひこの機会に金の売却を検討してみてはいかがでしょうか。
金を高く売るためのコツは、「金の価格が高いときに売ること」と「高値で買い取ってくれる専門店に売ること」です。金の価格は現在非常に高騰しているため、売却にはベストなタイミングといえます。
金の高価買取はおたからやにお任せください。
関連記事
タグ一覧
- #4℃
- #A.ランゲ&ゾーネ
- #GMTマスター
- #IWC
- #K10(10金)
- #K14(14金)
- #K22(22金)
- #K24(純金)
- #MCM
- #Van Cleef & Arpels
- #アクアノート
- #アクアマリン
- #アメジスト
- #アルハンブラ
- #アルマーニ
- #アンティーク時計
- #イエローゴールド
- #インカローズ
- #ヴァシュロンコンスタンタン
- #ヴァンクリーフ&アーペル
- #エクスプローラー
- #エメラルド
- #エルメス
- #エルメス(時計)
- #オーデマ ピゲ
- #オパール
- #オメガ
- #ガーネット
- #カイヤナイト
- #カルティエ
- #カルティエ(時計)
- #グッチ
- #グリーンゴールド
- #クロエ
- #クロムハーツ
- #クンツァイト
- #ケイトスペード
- #ケリー
- #コーチ
- #ゴヤール
- #サファイア
- #サブマリーナー
- #サマンサタバサ
- #サンローラン
- #シードゥエラー
- #シチズン
- #シトリン
- #ジバンシィ
- #ジミーチュウ
- #シャネル
- #シャネル(時計)
- #ジュエリー
- #ジュエリー買取
- #ショパール(時計)
- #スカイドゥエラー
- #スピネル
- #スフェーン
- #セイコー
- #ゼニス
- #セリーヌ
- #ターコイズ
- #ターノグラフ
- #ダイヤモンド
- #タグ・ホイヤー
- #タンザナイト
- #チェリーニ
- #チューダー
- #ディオール
- #デイデイト
- #デイトジャスト
- #デイトナ
- #ティファニー
- #ティファニー
- #トリーバーチ
- #トルマリン
- #ノーチラス
- #バーキン
- #バーバリー
- #パテック フィリップ
- #パネライ
- #ハミルトン
- #ハリーウィンストン
- #バレンシアガ
- #ピーカブー
- #ピアジェ
- #ピコタン
- #ピンクゴールド
- #フェンディ
- #ブライトリング
- #プラダ
- #プラチナ
- #フランクミュラー
- #ブランド品
- #ブランド品買取
- #ブランド時計
- #ブランパン
- #ブルガリ
- #ブルガリ(時計)
- #ブレゲ
- #ペリドット
- #ボッテガヴェネタ
- #ホワイトゴールド
- #マークジェイコブス
- #マトラッセ
- #ミュウミュウ
- #ミルガウス
- #メイプルリーフ金貨
- #モーブッサン
- #ヨットマスター
- #リシャールミル
- #ルイ・ヴィトン
- #ルビー
- #レッドゴールド
- #ロエベ
- #ロレックス
- #ロンシャン
- #出張買取
- #地金
- #宝石・ジュエリー
- #宝石買取
- #時計
- #珊瑚(サンゴ)
- #真珠・パール
- #色石
- #財布
- #金
- #金・プラチナ・貴金属
- #金アクセサリー
- #金インゴット
- #金の純度
- #金価格・相場
- #金歯
- #金縁メガネ
- #金貨
- #金買取
- #銀
- #銀貨
- #香水
お持ちの金・貴金属のお値段、知りたくありませんか?
高価買取のプロ「おたからや」が
無料でお答えします!


-

店頭買取
-
査定だけでもOK!
買取店舗数は業界最多の
約1,450店舗以上!おたからやの店舗数は全国 約1,450店舗以上(待機店舗を含む)。これは、数ある買取店の中で最多を誇ります。日本全国津々浦々にて、地域密着でお買取りを承っております。
-

出張買取
-
査定だけでもOK!
買取専門店おたからやの
無料出張買取。買取専門店おたからやの無料出張買取です。出張料・査定料・買取手数料は全て無料、査定は最短5分です。随時キャンペーンを実施をしております!まずはお気軽にご相談ください!































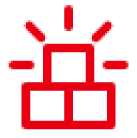

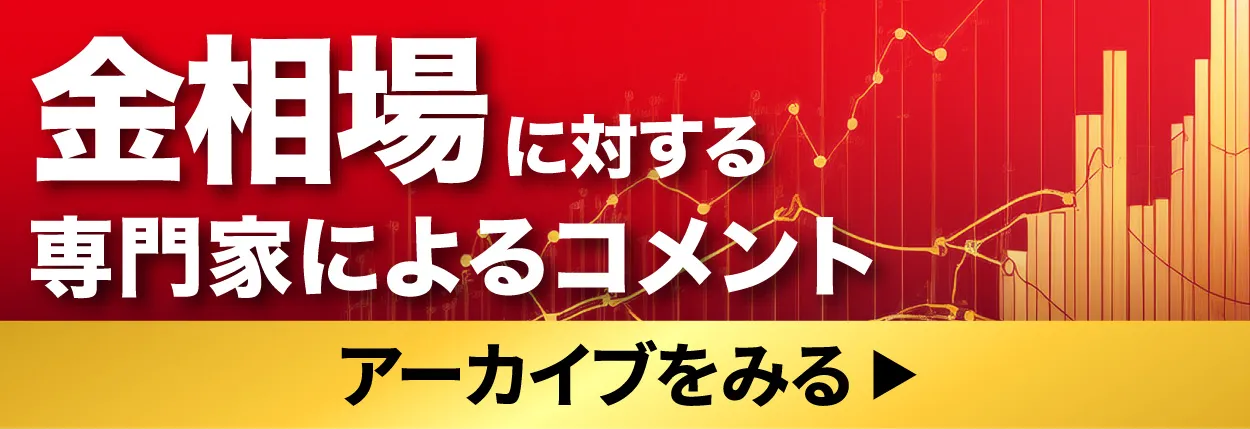
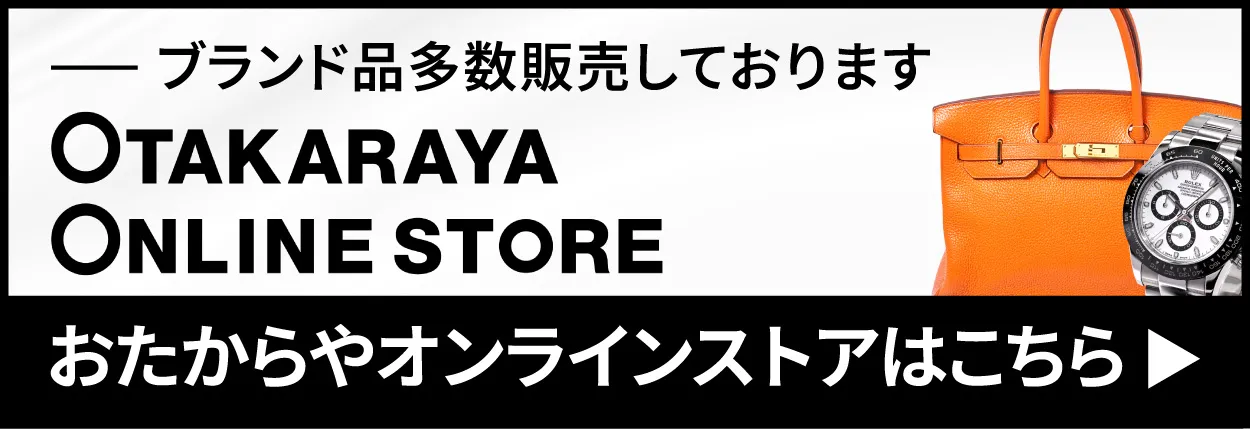
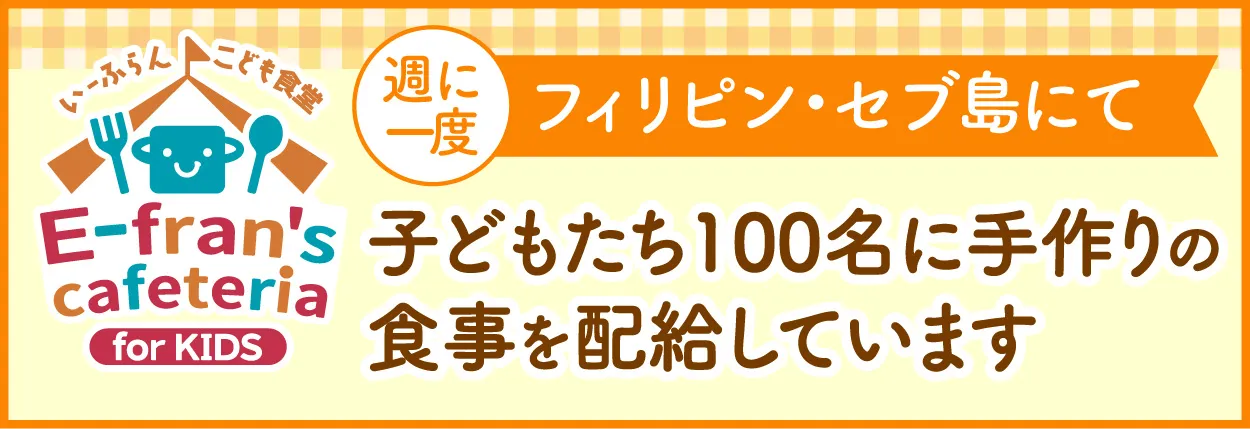


 金・インゴット買取
金・インゴット買取 プラチナ買取
プラチナ買取 金のインゴット買取
金のインゴット買取 24K(24金)買取
24K(24金)買取 18金(18K)買取
18金(18K)買取 バッグ・ブランド品買取
バッグ・ブランド品買取 時計買取
時計買取 宝石・ジュエリー買取
宝石・ジュエリー買取 ダイヤモンド買取
ダイヤモンド買取 サファイア買取
サファイア買取 エメラルド買取
エメラルド買取 ルビー買取
ルビー買取 喜平買取
喜平買取 メイプルリーフ金貨買取
メイプルリーフ金貨買取 シルバー買取
シルバー買取 金貨・銀貨買取
金貨・銀貨買取 大判・小判買取
大判・小判買取 硬貨・紙幣買取
硬貨・紙幣買取 切手買取
切手買取 カメラ買取
カメラ買取 着物買取
着物買取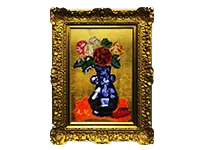 絵画・掛け軸・美術品買取
絵画・掛け軸・美術品買取 香木買取
香木買取 車買取
車買取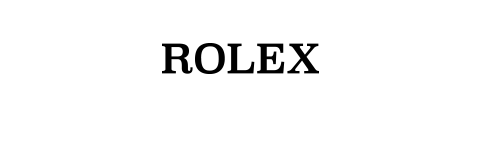 ロレックス買取
ロレックス買取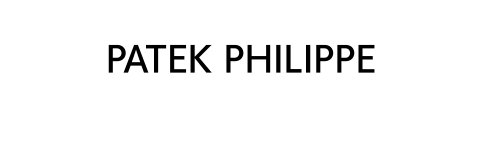 パテックフィリップ買取
パテックフィリップ買取 オーデマピゲ買取
オーデマピゲ買取 ヴァシュロン コンスタンタン買取
ヴァシュロン コンスタンタン買取 オメガ買取
オメガ買取 ブレゲ買取
ブレゲ買取 エルメス買取
エルメス買取 ルイ・ヴィトン買取
ルイ・ヴィトン買取 シャネル買取
シャネル買取 セリーヌ買取
セリーヌ買取 カルティエ買取
カルティエ買取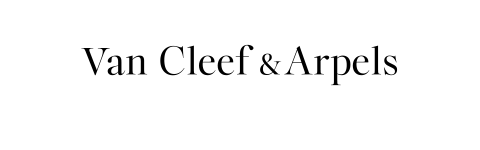 ヴァンクリーフ&アーペル買取
ヴァンクリーフ&アーペル買取 ティファニー買取
ティファニー買取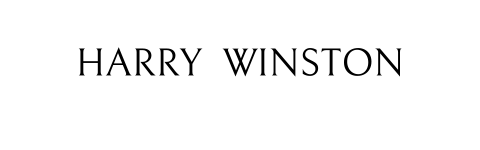 ハリー・ウィンストン買取
ハリー・ウィンストン買取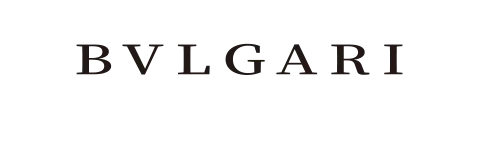 ブルガリ買取
ブルガリ買取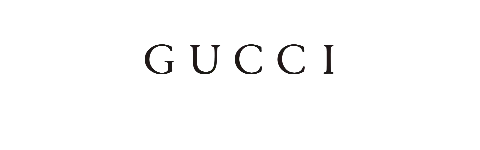 グッチ買取
グッチ買取
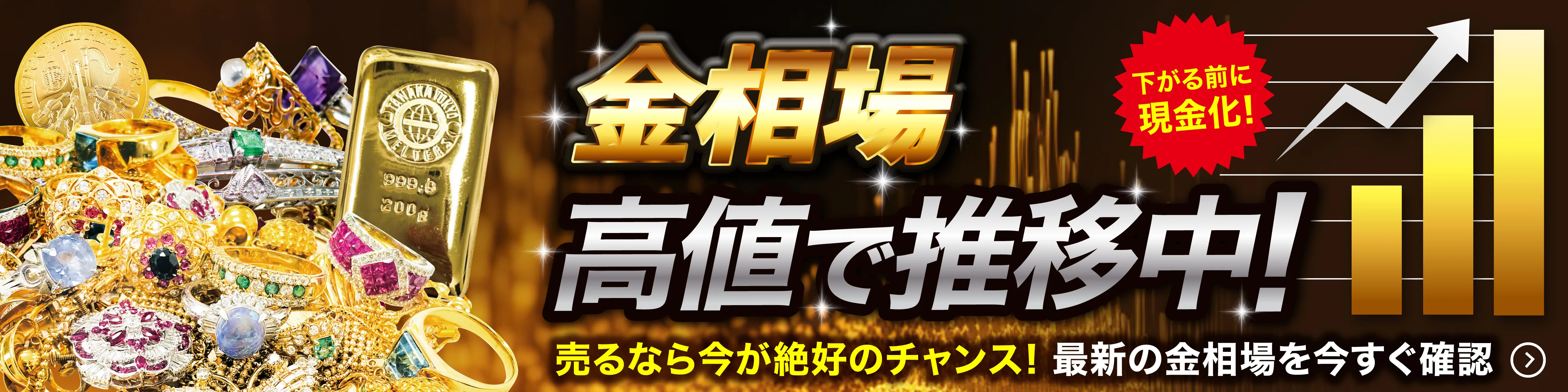

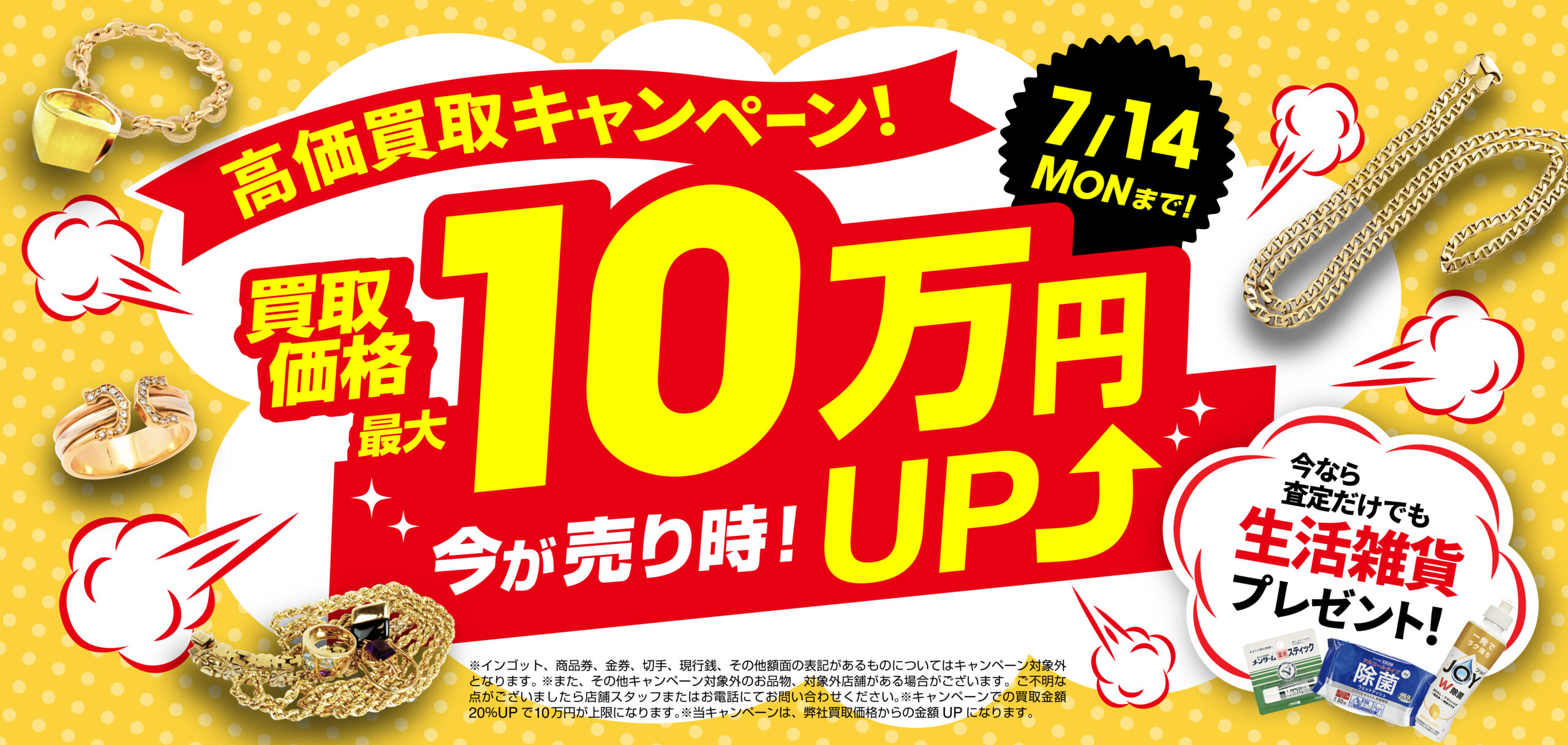

 ご相談・お申込みはこちら
ご相談・お申込みはこちら
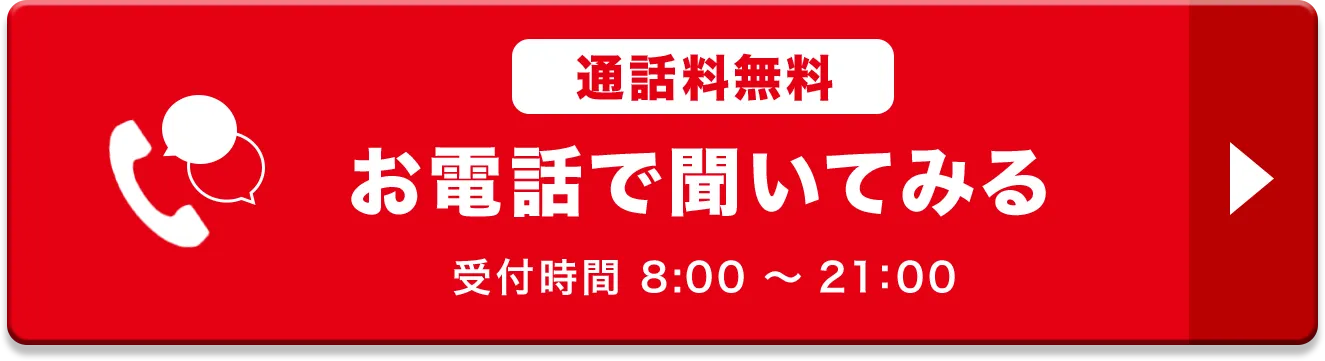
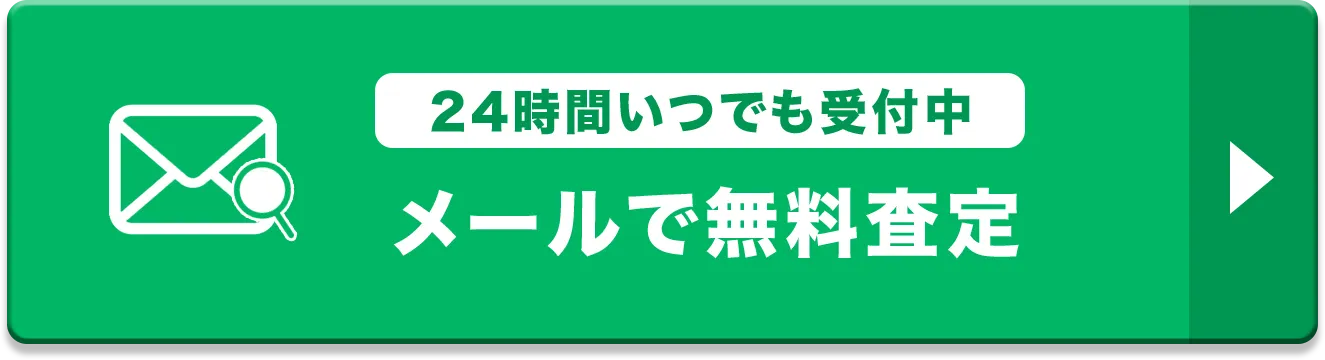

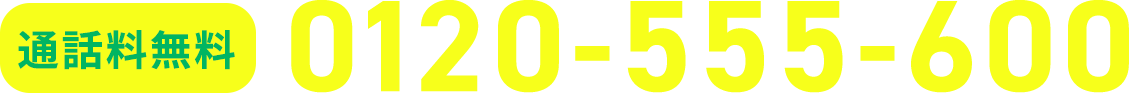
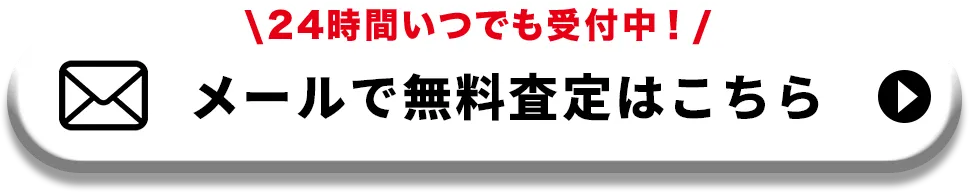
![【[current_year]最新】貴金属買取業者おすすめランキング17選!高く売るコツと選び方のポイントもご紹介](https://www.otakaraya.jp/app/wp-content/uploads/2025/06/0-Photoroom-7.webp)