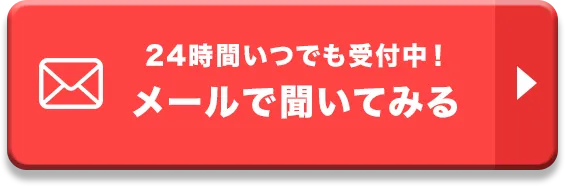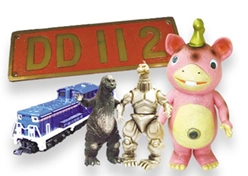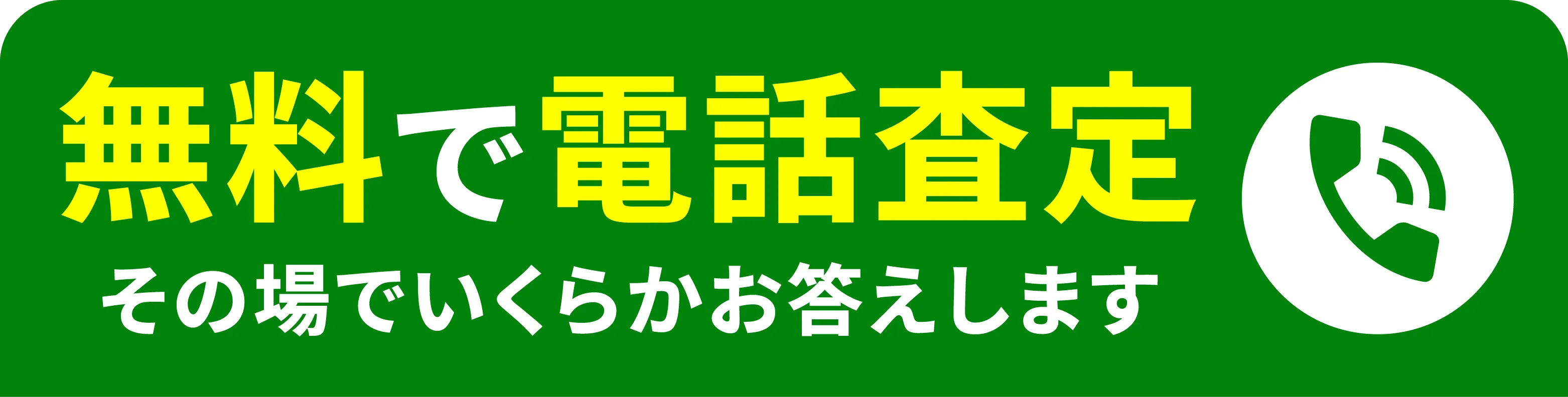東洋のクロンダイク
と呼ばれた北見枝幸砂金地

※下記の画像は全てイメージです
空前のゴールドラッシュで
沸いた東洋のクロンダイク
日本は古来より金を身近に感じて生活してきました。通貨はもちろんですが、歴史ある文化財に金があしらってあるものもとても多いです。そんな日本でも、ゴールドラッシュが沸き起こったことがあります。
東洋のクロンダイクとは?
明治30年代に北海道にあるウソタンナイ川の上流で砂金が発見され、「枝幸砂金」と呼ばれたのを皮切りにゴールドラッシュが沸き、北見枝幸地方は「東洋のクロンダイク」と呼ばれました。
これはカナダにあるユーコン河の支流の地域であるクロンダイクにて、1896年(明治29年)に砂金が発見され、ゴールドラッシュが起こったことに由来しています。カナダだけでなくアメリカからもたくさんの人が一攫千金を夢見てクロンダイクに押し寄せましたが、このゴールドラッシュで町ができたほどの賑わいでした。それにちなんで時期が重なったこともあり、ウソタンナイ川のある枝幸地域が「東洋のクロンダイク」と呼ばれたというわけです。
北見枝幸では大きな金塊も発見!
空前のゴールドラッシュが沸き起こり、漁業の不振で困っていた地元の漁師だけではなく、明治30年代には本州からもたくさんの人が押し掛けた東洋のクロンダイクですが、1900年(明治33年)に北見枝幸(えさし)砂金地で769gの金塊がウソタンナン川の支流であるナン川で発見されます。
ゴールドラッシュによって、ウソタンナイ川だけではなくパンケナイ川、ペーチャン川付近でも砂金は発見されます。同時に砂金採集所でもいくつかの集落ができました。たくさんの店が立ち並び、賑わいを見せていましたが、限られた資源は採りつくせばなくなります。一攫千金を夢見て、旅費をはたいて寒さ厳しい枝幸までやってきた人々も、夢破れて故郷に帰る人も少なくありませんでした。
まとめ
東洋のクロンダイクは、本州からも人が押し寄せる大変な騒ぎでした。それくらい金は人々の心を奪いますし、価値の高い資産となります。現代はなかなか大きな金塊を見つけるのは難しいですが、趣味で砂金を楽しむことも可能です。
金を高く売るためのコツは、「金の価格が高いときに売ること」と「高値で買い取ってくれる専門店に売ること」です。金の価格は現在非常に高騰しているため、売却にはベストなタイミングといえます。
金の高価買取はおたからやにお任せください。
関連記事
タグ一覧
- #出張買取
- #香水
- #4℃
- #A.ランゲ&ゾーネ
- #GMTマスター
- #ノーチラス
- #IWC
- #K10(10金)
- #K14(14金)
- #K22(22金)
- #K24(純金)
- #MCM
- #Van Cleef & Arpels
- #アクアノート
- #アクアマリン
- #アメジスト
- #アルハンブラ
- #アルマーニ
- #アンティーク時計
- #イエローゴールド
- #ピンクゴールド
- #インカローズ
- #ヴァシュロンコンスタンタン
- #ヴァンクリーフ&アーペル
- #エクスプローラー
- #エメラルド
- #エルメス
- #プラチナ
- #エルメス(時計)
- #オーデマ ピゲ
- #オパール
- #オメガ
- #ガーネット
- #カイヤナイト
- #カルティエ
- #カルティエ(時計)
- #ルビー
- #グッチ
- #グリーンゴールド
- #珊瑚(サンゴ)
- #クロエ
- #真珠・パール
- #ハリーウィンストン
- #クロムハーツ
- #クンツァイト
- #ケイトスペード
- #ケリー
- #ブルガリ
- #コーチ
- #モーブッサン
- #ゴヤール
- #サファイア
- #サブマリーナー
- #サマンサタバサ
- #ブランド品
- #サンローラン
- #ブランド品買取
- #シードゥエラー
- #財布
- #シチズン
- #シトリン
- #バーキン
- #ジバンシィ
- #ジミーチュウ
- #マトラッセ
- #ピーカブー
- #ルイ・ヴィトン
- #ピコタン
- #シャネル
- #バレンシアガ
- #シャネル(時計)
- #バーバリー
- #ボッテガヴェネタ
- #ジュエリー
- #ジュエリー買取
- #ショパール(時計)
- #スカイドゥエラー
- #スピネル
- #スフェーン
- #セイコー
- #ゼニス
- #ペリドット
- #ロエベ
- #セリーヌ
- #フェンディ
- #ターコイズ
- #ホワイトゴールド
- #ターノグラフ
- #ダイヤモンド
- #タグ・ホイヤー
- #マークジェイコブス
- #タンザナイト
- #チェリーニ
- #メイプルリーフ金貨
- #ロンシャン
- #チューダー
- #ディオール
- #リシャールミル
- #プラダ
- #デイデイト
- #レッドゴールド
- #ミュウミュウ
- #デイトジャスト
- #デイトナ
- #ティファニー
- #ティファニー
- #地金
- #トリーバーチ
- #宝石・ジュエリー
- #ブランド時計
- #宝石買取
- #トルマリン
- #時計
- #ロレックス
- #ヨットマスター
- #色石
- #ミルガウス
- #パテック フィリップ
- #金
- #ブレゲ
- #金・プラチナ・貴金属
- #ハミルトン
- #金アクセサリー
- #ブルガリ(時計)
- #金インゴット
- #ブライトリング
- #金の純度
- #フランクミュラー
- #金価格・相場
- #金歯
- #金縁メガネ
- #パネライ
- #金貨
- #ピアジェ
- #金買取
- #銀
- #ブランパン
- #銀貨
お持ちの金・貴金属のお値段、知りたくありませんか?
高価買取のプロ「おたからや」が
無料でお答えします!


-

店頭買取
-
査定だけでもOK!
買取店舗数は業界最多の
約1,450店舗以上!おたからやの店舗数は全国 約1,450店舗以上(待機店舗を含む)。これは、数ある買取店の中で最多を誇ります。日本全国津々浦々にて、地域密着でお買取りを承っております。
-

出張買取
-
査定だけでもOK!
買取専門店おたからやの
無料出張買取。買取専門店おたからやの無料出張買取です。出張料・査定料・買取手数料は全て無料、査定は最短5分です。随時キャンペーンを実施をしております!まずはお気軽にご相談ください!































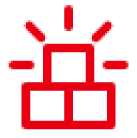

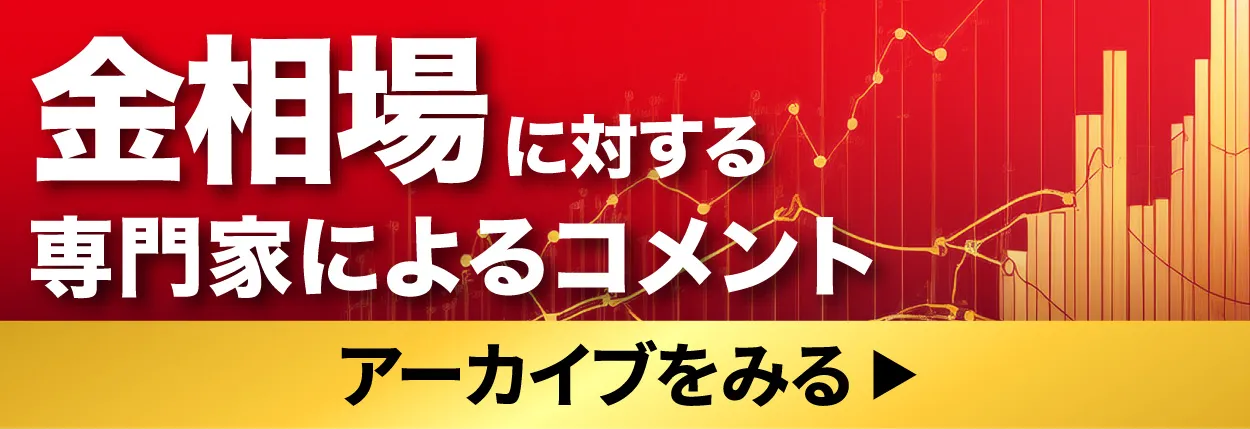
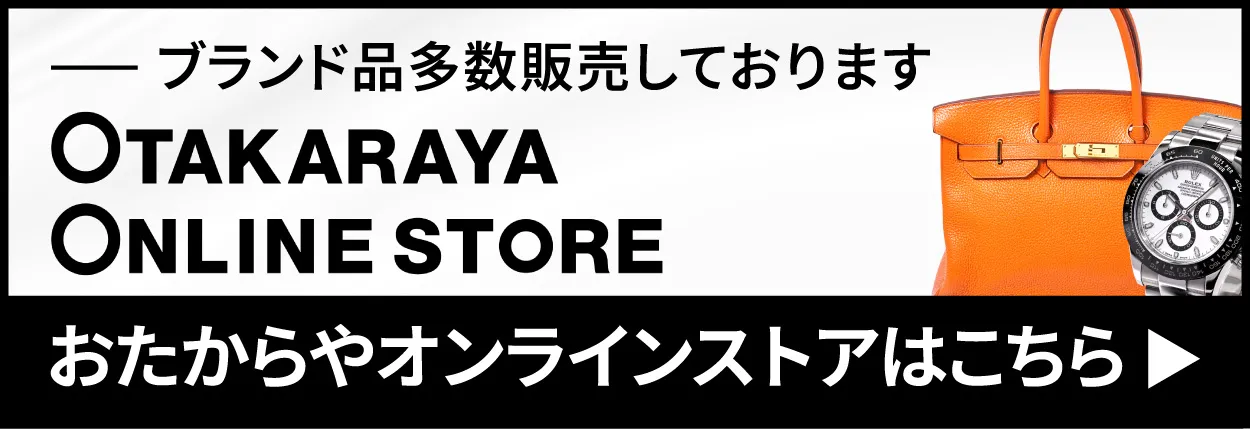
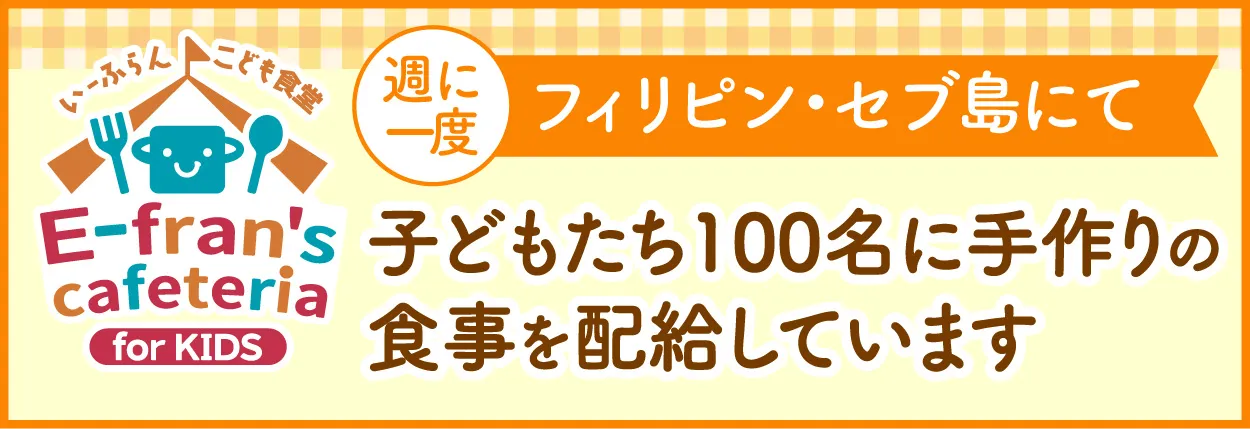


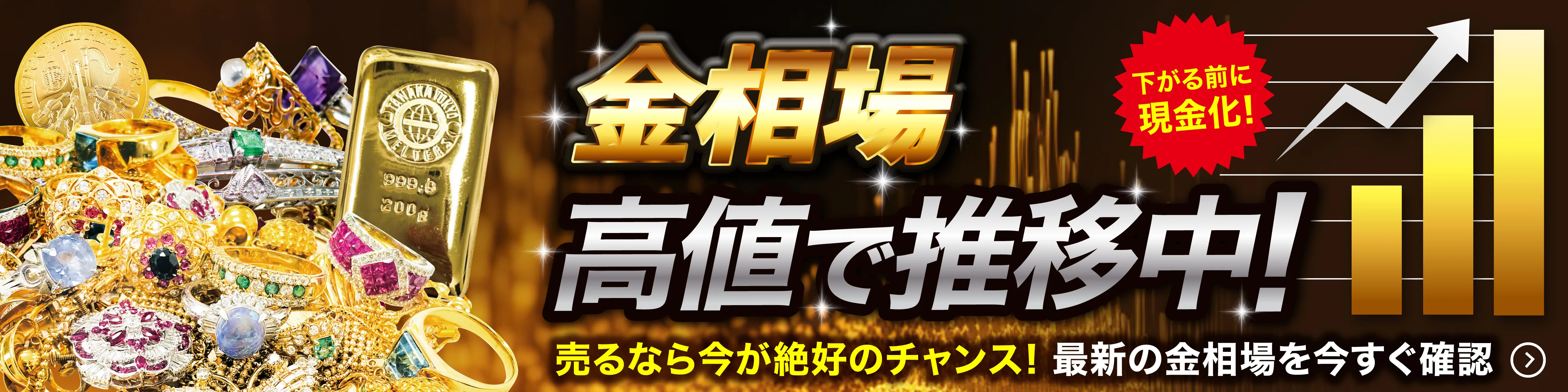



 ご相談・お申込みはこちら
ご相談・お申込みはこちら
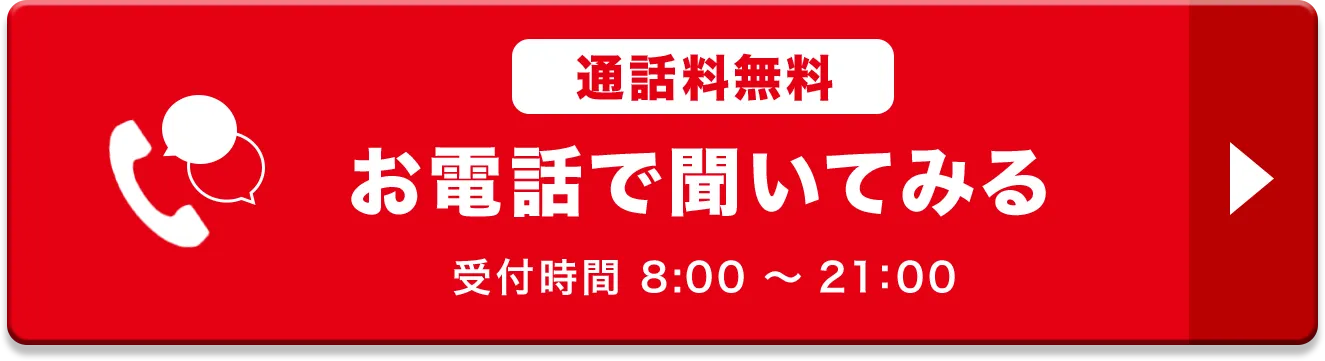
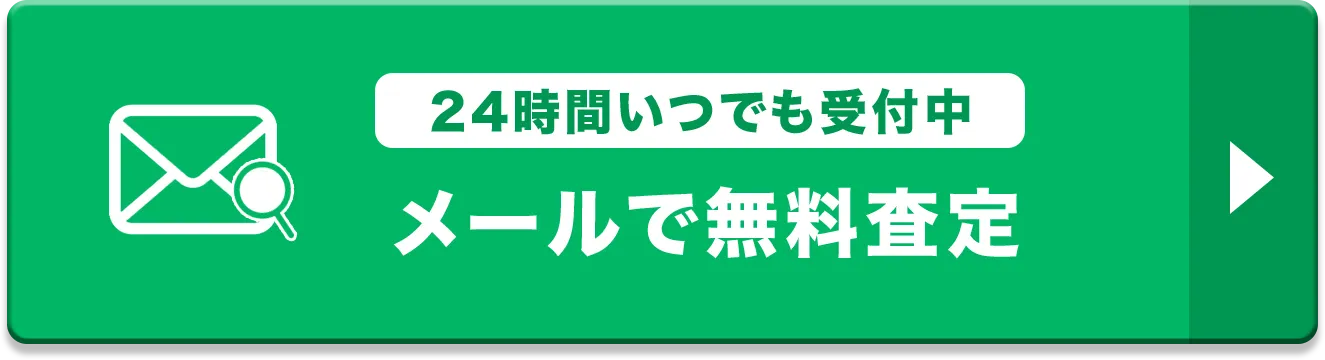

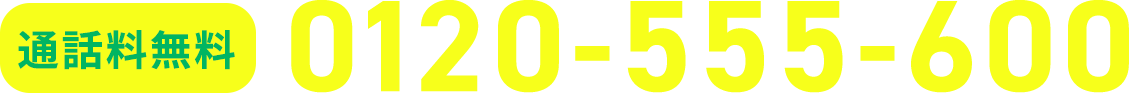
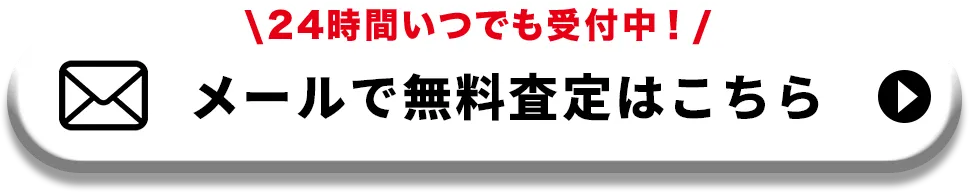
![【[current_year]最新】貴金属買取業者おすすめランキング17選!高く売るコツと選び方のポイントもご紹介](https://www.otakaraya.jp/app/wp-content/uploads/2025/06/0-Photoroom-7.webp)