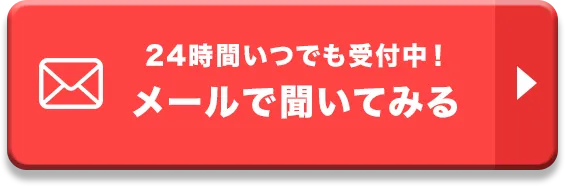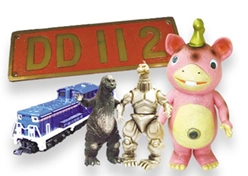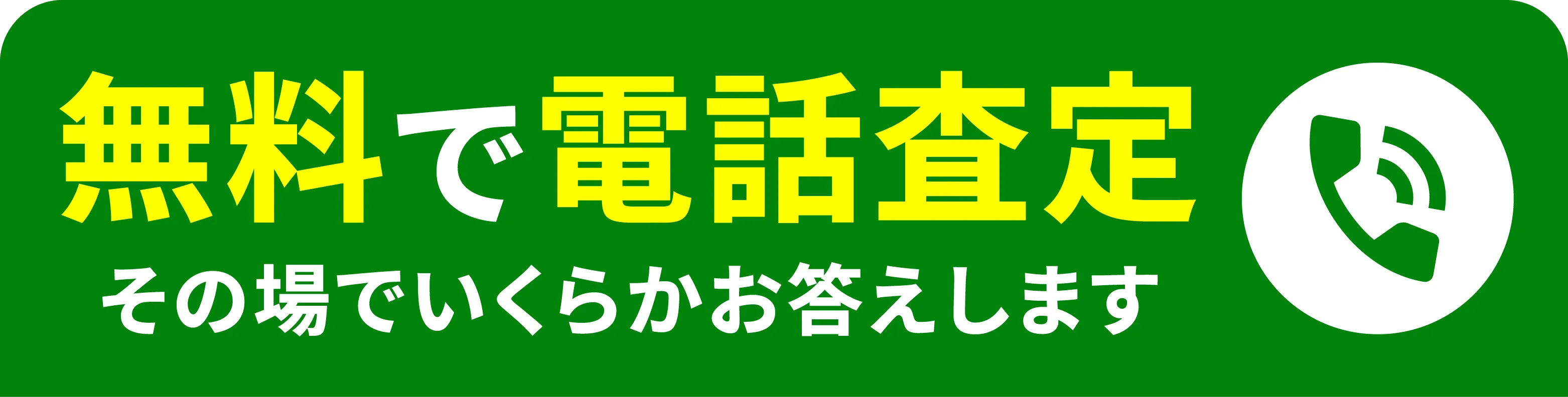江戸時代に制定された
三貨制度とは?

Contents
江戸時代に
制定された三貨制度
江戸時代の通貨は今よりも種類が多く、金が小判・一分判・大判の3種類が使用されており、銀が丁銀・小玉銀の2種類、銭として寛永通宝の3種類が基本的に使用されていました。これだけ多くの種類のお金がある理由は、場面や身分に応じて使用する通貨が違うからです。
三貨制度は
3つの種類を使っているわけではない
3種類すべてのお金を使用して人々は生活していたわけではありませんでした。買い物する際に商品の対価として、お客が金貨や銀貨を使って支払っていたことはなかったようです。身分が高い武士などは金貨を使用し支払いをおこない、庶民は銭を使用して支払うなど、それぞれの身分によって使用していた通貨は違いました。
価値が最も高かった金貨の大判は、物やサービスに対しての対価を支払う目的で使用するというより、人への贈り物や報酬といった場合に使用されています。江戸時代における貨幣の使い方は、現在の日本円のように1万円や100円硬貨といった貨幣ごとに価値が決まっているのではなく、使用できる身分階層や使用する時と場合があり、今とは違う感覚で使用されていました。
三貨制度ができた背景と
江戸時代の通貨
江戸時代にできた三貨制度の歴史はどのようなものだったのでしょうか。1601年に初代将軍徳川家康が慶長金銀貨を発行し、三代将軍徳川家光が寛永通宝を発行しました。
そして1670年に海外から伝わっていた渡来銭の使用を幕府は禁じ、3種類の通貨が基本的な通貨として使用されるようになります。3種類の違う種類のお金を立場や場面に応じて使用しているのが三貨制度です。
また、日本には1700年代初頭頃から伊勢山田地方の商人を信頼に基づいた紙幣が登場しました。紙幣はやがて各藩の藩札として発行されるようになり、分散発行という今現在でたとえると日本銀行が各藩にあった状態になります。
三貨制度の通貨単位と
江戸時代初頭に起こった
外国との比価の違い
三貨制度の通貨単位と役割は、各通貨の種類により単位がことなり、また地域によって使用していた通貨も違いました。さらには、買いたい人と売りたい人が発生しての比価のバランスが悪くなり、外国との通貨関係性で思わぬ盲点があったのです。
三貨制度の通貨単位と役割
1601年に鋳造された慶長金銀貨が作られました。金が使われた小判は、両・分・朱と3つに分けられた単位を定めます。両が最も大きな単位として基本として、両より4分1の単位が分、分より4分1の単位が朱として、発行されてからしばらく経って広まったようです。
銀貨は江戸よりも関西地方で利用されていました。理由は西日本に銀山が多くあり、銀の採掘量が多かったからです。銀貨は、貫・匁・分と金と同じで3種類の単位に分けられて、貫が基準単位となります。1貫が1000匁、1匁が10分と単位が決められていていました。金貨が日本中で使用されるようになってからは、補助的な役割として銀貨が果たすようになります。
三貨制度で最も多くの使用量があったのが寛永通宝です。一般的に使用されていた寛永通宝は、全国の経済発展に応じて発行されていきました。見た目は真ん中に穴が空いており、寛永通宝と刻まれています。
外国との
金銀の価値の違いが生んだ問題点
現在の金や銀の相場は、買いたい人と売りたい人により価格が決まっていました。しかし、三貨制度により、日本と海外の金と銀の相場が違い、問題が生じてしまいます。
当時の日本の金と銀の比価は1:12と定められていました。しかし、外国では1:10と定められており、ずれが生じてしまっています。このずれにより、海外の貿易に携わる人が外国から銀貨を金貨に変えて日本に持ち込み、日本の両替所で金貨から銀貨に変えてまた海外に持ち出す転売が多くなりました。
海外に持ち出した商人により大量の銀が流出してしまい、異変に気づいた幕府関係者はレートを1:10へと戻し、以降は安定します。
まとめ
金貨をはじめとして3種類の通貨があった三貨制度は、使う人の位や用途によって使う種類が違うなど、今とは違う感覚でお金を扱っていました。
海外の情勢によって価値が決まることを学んだ幕府関係者は、金や銀の価値を改めて海外基準に合わせて設定し、差額を埋めて流出しないようにした、現在でも意識するレートを考えて行動していることがわかります。
金を高く売るためのコツは、「金の価格が高いときに売ること」と「高値で買い取ってくれる専門店に売ること」です。金の価格は現在非常に高騰しているため、売却にはベストなタイミングといえます。
金の高価買取はおたからやにお任せください。
関連記事
タグ一覧
- #出張買取
- #香水
- #4℃
- #A.ランゲ&ゾーネ
- #GMTマスター
- #ノーチラス
- #IWC
- #K10(10金)
- #K14(14金)
- #K22(22金)
- #K24(純金)
- #MCM
- #Van Cleef & Arpels
- #アクアノート
- #アクアマリン
- #アメジスト
- #アルハンブラ
- #アルマーニ
- #アンティーク時計
- #イエローゴールド
- #ピンクゴールド
- #インカローズ
- #ヴァシュロンコンスタンタン
- #ヴァンクリーフ&アーペル
- #エアキング
- #エクスプローラー
- #エメラルド
- #エルメス
- #プラチナ
- #エルメス(時計)
- #オーデマ ピゲ
- #オパール
- #オメガ
- #ガーネット
- #カイヤナイト
- #カルティエ
- #カルティエ(時計)
- #ルビー
- #グッチ
- #グリーンゴールド
- #珊瑚(サンゴ)
- #クロエ
- #真珠・パール
- #ハリーウィンストン
- #クロムハーツ
- #クンツァイト
- #ケイトスペード
- #ケリー
- #ブルガリ
- #コーチ
- #モーブッサン
- #ゴヤール
- #サファイア
- #サブマリーナー
- #サマンサタバサ
- #ブランド品
- #サンローラン
- #ブランド品買取
- #シードゥエラー
- #財布
- #シチズン
- #シトリン
- #バーキン
- #ジバンシィ
- #ジミーチュウ
- #マトラッセ
- #ピーカブー
- #ルイ・ヴィトン
- #ピコタン
- #シャネル
- #バレンシアガ
- #シャネル(時計)
- #バーバリー
- #ボッテガヴェネタ
- #ジュエリー
- #ジュエリー買取
- #ショパール(時計)
- #スカイドゥエラー
- #スピネル
- #スフェーン
- #セイコー
- #ゼニス
- #ペリドット
- #ロエベ
- #セリーヌ
- #フェンディ
- #ターコイズ
- #ホワイトゴールド
- #ターノグラフ
- #ダイヤモンド
- #タグ・ホイヤー
- #マークジェイコブス
- #タンザナイト
- #チェリーニ
- #メイプルリーフ金貨
- #ロンシャン
- #チューダー
- #ディオール
- #リシャールミル
- #プラダ
- #デイデイト
- #レッドゴールド
- #ミュウミュウ
- #デイトジャスト
- #デイトナ
- #ティファニー
- #ティファニー
- #地金
- #トリーバーチ
- #宝石・ジュエリー
- #ブランド時計
- #宝石買取
- #トルマリン
- #時計
- #ロレックス
- #ヨットマスター
- #色石
- #ミルガウス
- #パテック フィリップ
- #金
- #ブレゲ
- #金・プラチナ・貴金属
- #ハミルトン
- #金アクセサリー
- #ブルガリ(時計)
- #金インゴット
- #ブライトリング
- #金の純度
- #フランクミュラー
- #金価格・相場
- #金歯
- #金縁メガネ
- #パネライ
- #金貨
- #ピアジェ
- #金買取
- #銀
- #ブランパン
- #銀貨
お持ちの金・貴金属のお値段、知りたくありませんか?
高価買取のプロ「おたからや」が
無料でお答えします!


-

店頭買取
-
査定だけでもOK!
買取店舗数は業界最多の
約1,400店舗以上!おたからやの店舗数は全国 約1,400店舗以上(待機店舗を含む)。これは、数ある買取店の中で最多を誇ります。日本全国津々浦々にて、地域密着でお買取りを承っております。
-

出張買取
-
査定だけでもOK!
買取専門店おたからやの
無料出張買取。買取専門店おたからやの無料出張買取です。出張料・査定料・買取手数料は全て無料、査定は最短5分です。随時キャンペーンを実施をしております!まずはお気軽にご相談ください!






























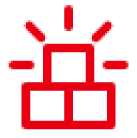

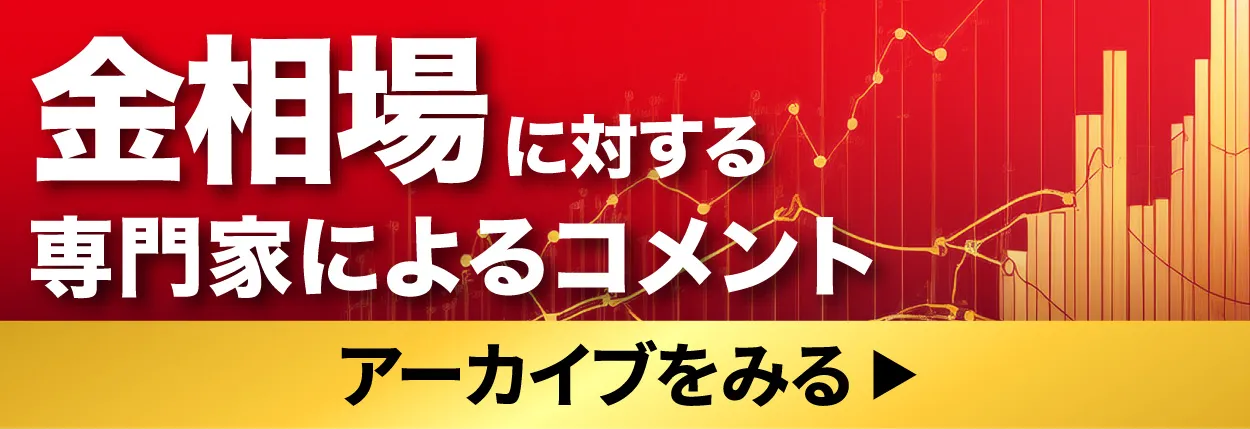
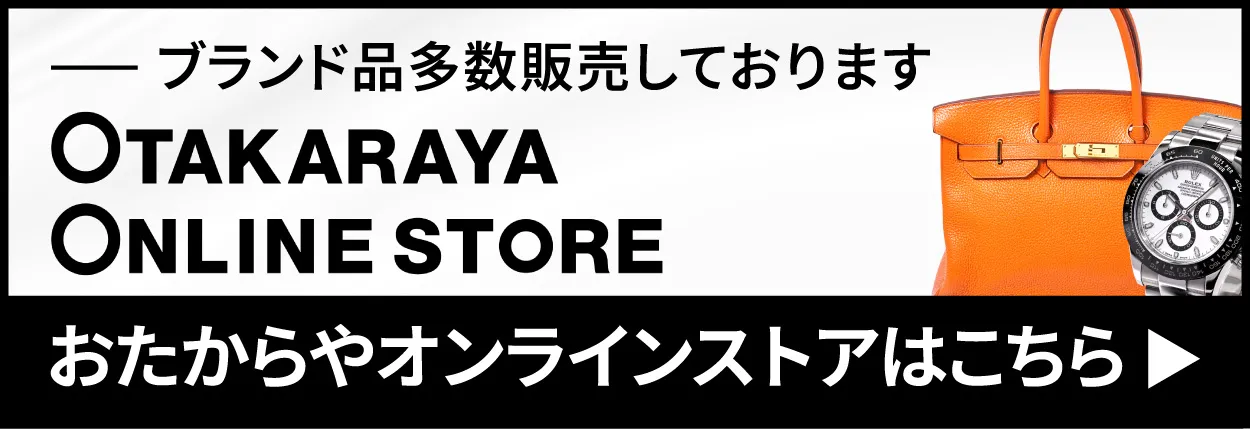
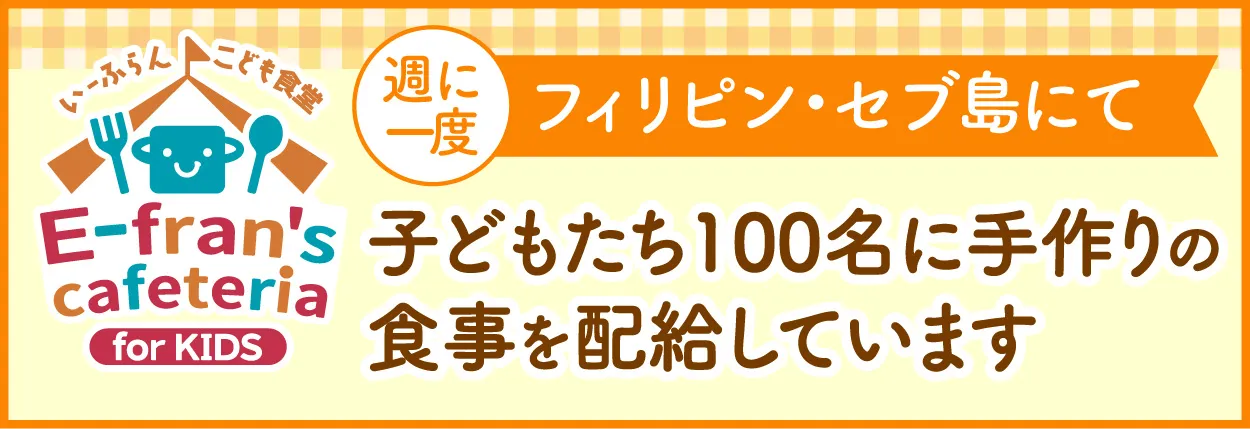


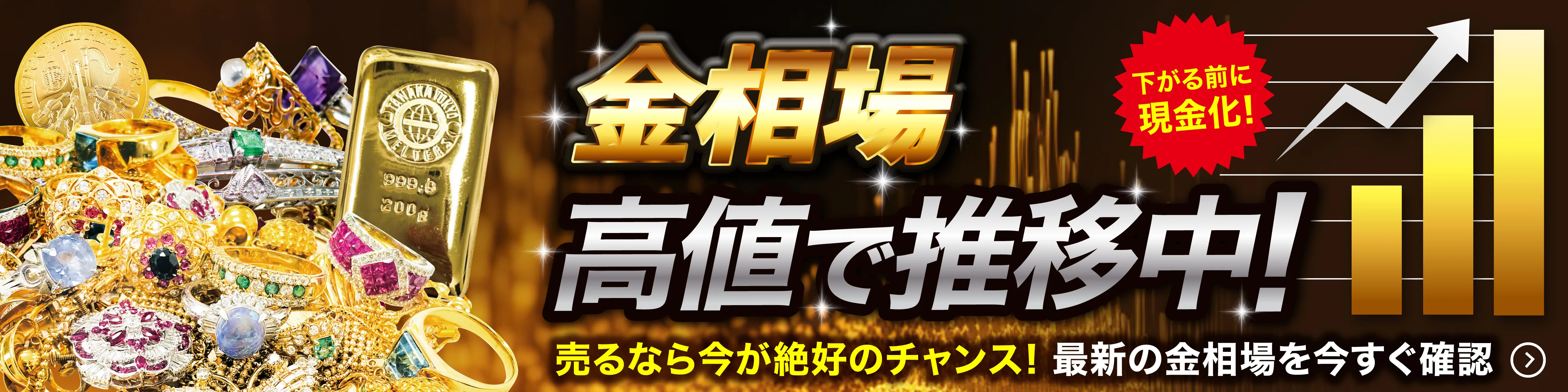



 ご相談・お申込みはこちら
ご相談・お申込みはこちら
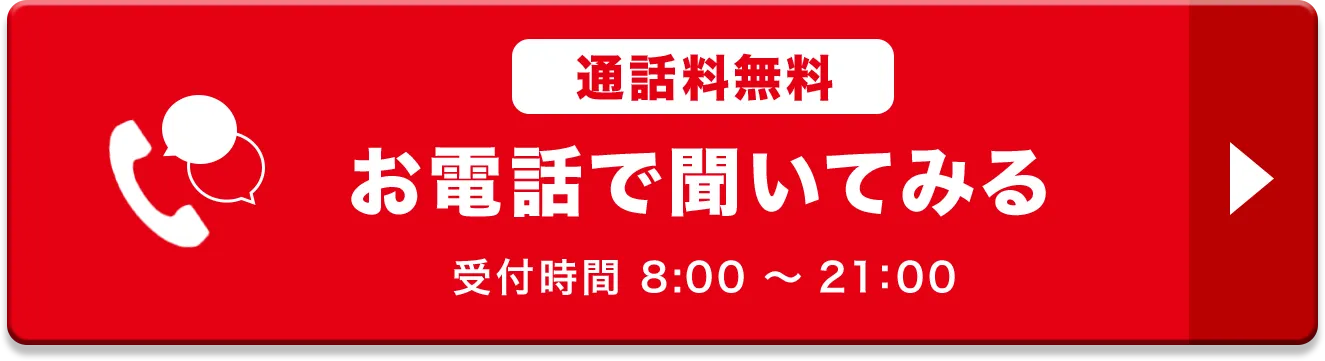
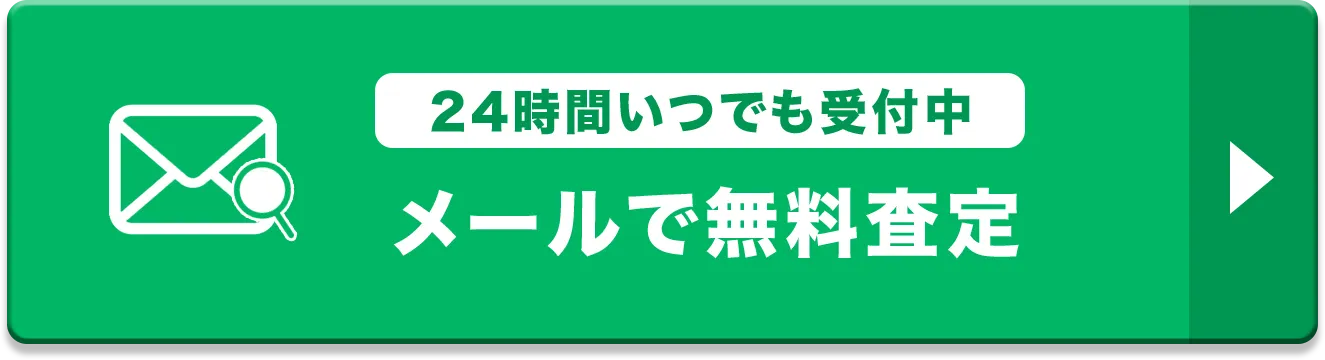

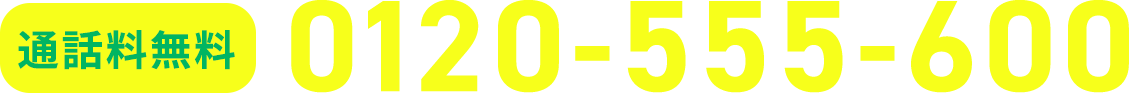
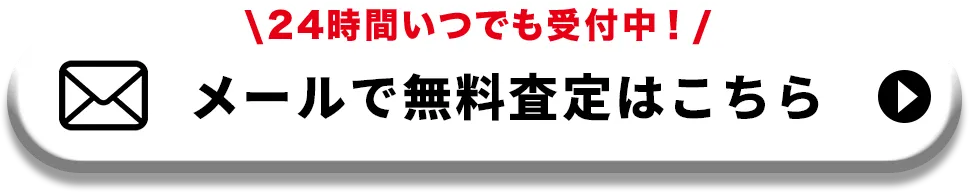
![【[current_year]最新】貴金属買取業者おすすめランキング17選!高く売るコツと選び方のポイントもご紹介](https://www.otakaraya.jp/app/wp-content/uploads/2025/06/0-Photoroom-7.webp)