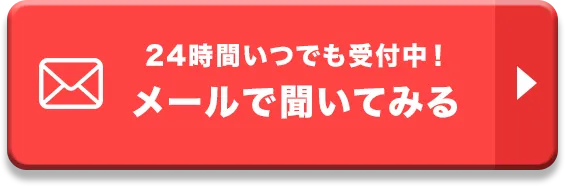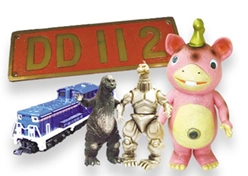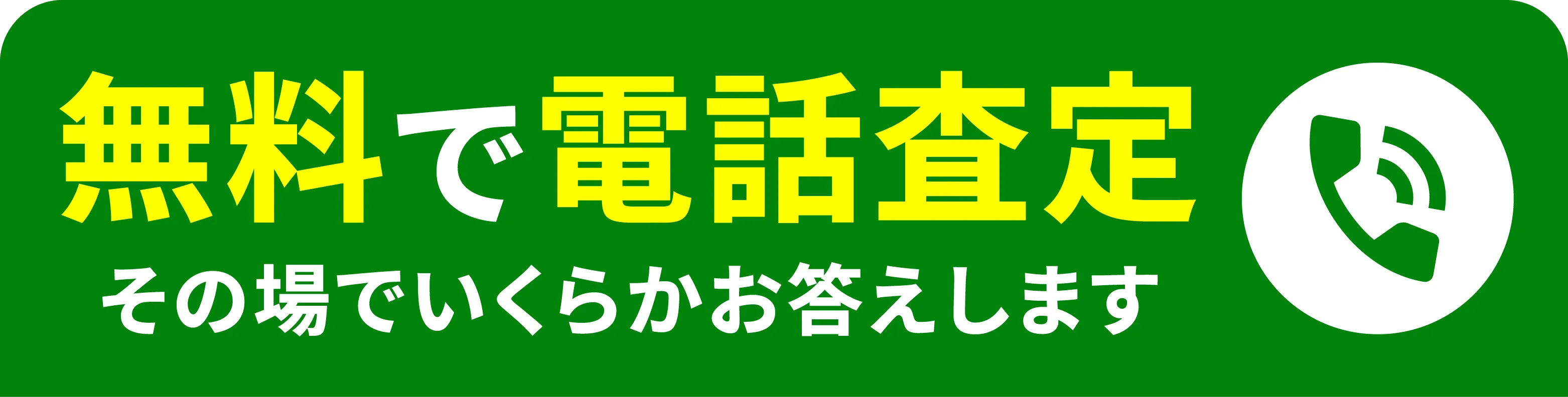歴史的なインフレと
物価上昇に関わる国民心理

※下記の画像は全てイメージです
そもそもインフレとは何か
インフレ(インフレーション)とは物価が上がり続ける現象のことですが、言い換えると紙幣価値が下がる現象でもあります。日本でインフレ現象が起こると円安と呼ばれ、輸出業や海外観光客が増加し観光業が潤うなどと一般的には言われているのです。また物の需要が供給量を上回ることで、企業収益が高まり賃金の上昇や消費が活性化するため好景気となりやすく、金利も上昇していきます。
またインフレが進み過ぎるとハイパーインフレと呼ばれる現象が起き、この状態の場合は3年で物価が約2倍以上にもなります。広く知られた事例では敗戦後のドイツや、ロシアの経済改革などが挙げられます。
歴史的なインフレ現象と、インフレとは
異なる物価上昇
日本でも敗戦直後、高度経済成長期とされる1960~70年代などでインフレ現象が起き、消費者物価指数が大きく上昇しました。その背景には、国民の豊かになりたいといった世間の雰囲気や景気の過熱があるとされています。
またこれら以外にもインフレに似た現象は起こりましたが、大半は世界的な原材料の高騰が起因なためコストプッシュ型と呼ばれる物価上昇を招き、賃金の上昇はなく消費も停滞し景気の悪循環となりました。現在の日本はこの状況が続いているとされており、金利の水準からも国民の心理的にも将来への不安が強いと言えます。この日本の低インフレ・低成長の状況はどうなっていくのかを様々な議論がなされていますが、世界的にも所得の倍増・雇用の安定などが課題の先進国も多く各国ともインフレ水準を適正値にしたい思惑は強くあると言えるのです。
今後の日本ではインフレとは異なる物価上昇に対する国民の不安解消が非常に重要で、賃金の上昇・雇用の安定化を急ピッチで図る必要があるでしょう。更に消費を促進させるためにも出世率の向上など、次の好循環となる適正なインフレ現象が起こるように次世代までを見据えた世間の高揚感が必須になってくると考えられます。
まとめ
インフレは日本においても戦後起きていた現象で、この状況下の国民心理は非常に高揚感に溢れていました。一般的にはインフレの定義を物価上昇が続く状態と習った方が多く、専門性が無い方などには物価が上昇する背景によって引き起こされる不均衡な状況の要因まで深く把握されておらず、賃金が上昇されれば嬉しいと感じておられた方も多いのではないでしょうか。
実社会に生きる私たちの何気なく感じるこの感覚は非常に重要で、生活状況が変わらないのに物価の上昇を感じることは不健全な経済状況とも言えるでしょう。歴史的なインフレ現象と大きく異なっている現状の国民心理を、今後は日本全体で盛り上げられるようにする必要がありそうです。
金を高く売るためのコツは、「金の価格が高いときに売ること」と「高値で買い取ってくれる専門店に売ること」です。金の価格は現在非常に高騰しているため、売却にはベストなタイミングといえます。
金の高価買取はおたからやにお任せください。
関連記事
タグ一覧
- #出張買取
- #香水
- #4℃
- #A.ランゲ&ゾーネ
- #GMTマスター
- #ノーチラス
- #IWC
- #K10(10金)
- #K14(14金)
- #K22(22金)
- #K24(純金)
- #MCM
- #Van Cleef & Arpels
- #アクアノート
- #アクアマリン
- #アメジスト
- #アルハンブラ
- #アルマーニ
- #アンティーク時計
- #イエローゴールド
- #ピンクゴールド
- #インカローズ
- #ヴァシュロンコンスタンタン
- #ヴァンクリーフ&アーペル
- #エクスプローラー
- #エメラルド
- #エルメス
- #プラチナ
- #エルメス(時計)
- #オーデマ ピゲ
- #オパール
- #オメガ
- #ガーネット
- #カイヤナイト
- #カルティエ
- #カルティエ(時計)
- #ルビー
- #グッチ
- #グリーンゴールド
- #珊瑚(サンゴ)
- #クロエ
- #真珠・パール
- #ハリーウィンストン
- #クロムハーツ
- #クンツァイト
- #ケイトスペード
- #ケリー
- #ブルガリ
- #コーチ
- #モーブッサン
- #ゴヤール
- #サファイア
- #サブマリーナー
- #サマンサタバサ
- #ブランド品
- #サンローラン
- #ブランド品買取
- #シードゥエラー
- #財布
- #シチズン
- #シトリン
- #バーキン
- #ジバンシィ
- #ジミーチュウ
- #マトラッセ
- #ピーカブー
- #ルイ・ヴィトン
- #ピコタン
- #シャネル
- #バレンシアガ
- #シャネル(時計)
- #バーバリー
- #ボッテガヴェネタ
- #ジュエリー
- #ジュエリー買取
- #ショパール(時計)
- #スカイドゥエラー
- #スピネル
- #スフェーン
- #セイコー
- #ゼニス
- #ペリドット
- #ロエベ
- #セリーヌ
- #フェンディ
- #ターコイズ
- #ホワイトゴールド
- #ターノグラフ
- #ダイヤモンド
- #タグ・ホイヤー
- #マークジェイコブス
- #タンザナイト
- #チェリーニ
- #メイプルリーフ金貨
- #ロンシャン
- #チューダー
- #ディオール
- #リシャールミル
- #プラダ
- #デイデイト
- #レッドゴールド
- #ミュウミュウ
- #デイトジャスト
- #デイトナ
- #ティファニー
- #ティファニー
- #地金
- #トリーバーチ
- #宝石・ジュエリー
- #ブランド時計
- #宝石買取
- #トルマリン
- #時計
- #ロレックス
- #ヨットマスター
- #色石
- #ミルガウス
- #パテック フィリップ
- #金
- #ブレゲ
- #金・プラチナ・貴金属
- #ハミルトン
- #金アクセサリー
- #ブルガリ(時計)
- #金インゴット
- #ブライトリング
- #金の純度
- #フランクミュラー
- #金価格・相場
- #金歯
- #金縁メガネ
- #パネライ
- #金貨
- #ピアジェ
- #金買取
- #銀
- #ブランパン
- #銀貨
お持ちの金・貴金属のお値段、知りたくありませんか?
高価買取のプロ「おたからや」が
無料でお答えします!


-

店頭買取
-
査定だけでもOK!
買取店舗数は業界最多の
約1,450店舗以上!おたからやの店舗数は全国 約1,450店舗以上(待機店舗を含む)。これは、数ある買取店の中で最多を誇ります。日本全国津々浦々にて、地域密着でお買取りを承っております。
-

出張買取
-
査定だけでもOK!
買取専門店おたからやの
無料出張買取。買取専門店おたからやの無料出張買取です。出張料・査定料・買取手数料は全て無料、査定は最短5分です。随時キャンペーンを実施をしております!まずはお気軽にご相談ください!






























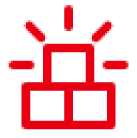

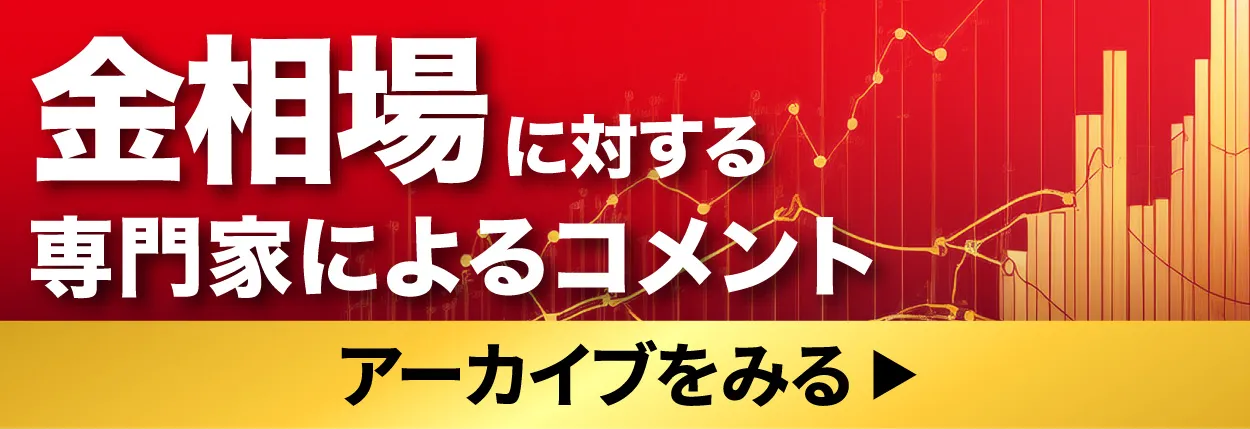
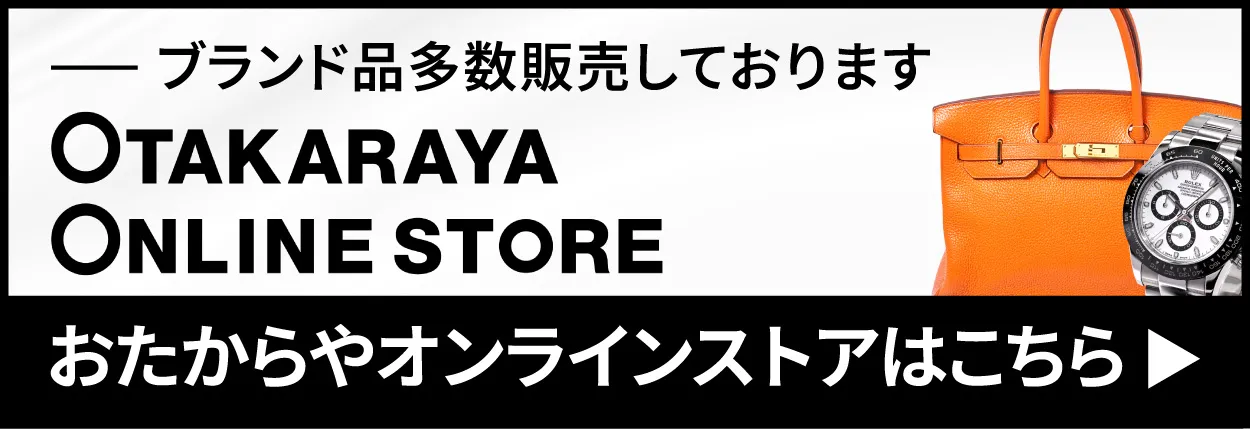
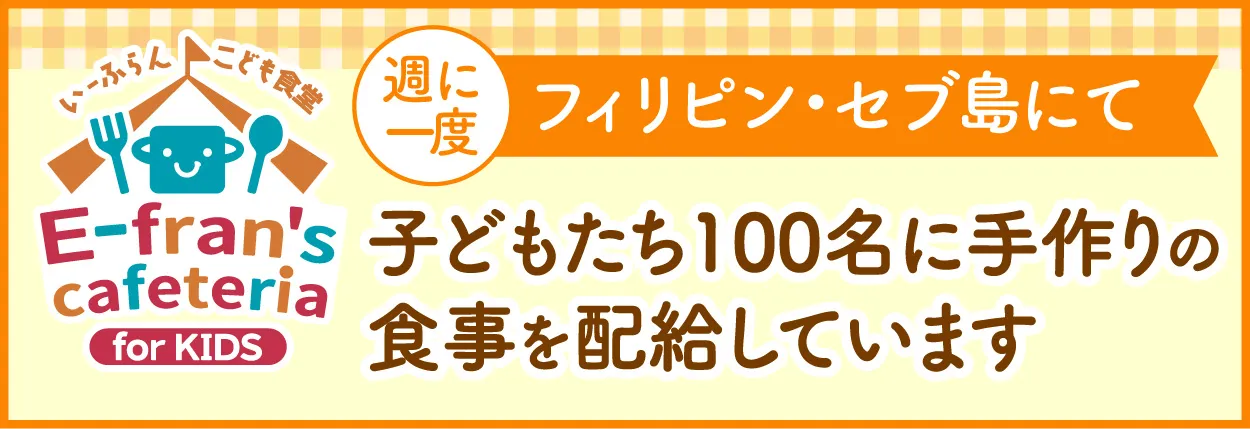


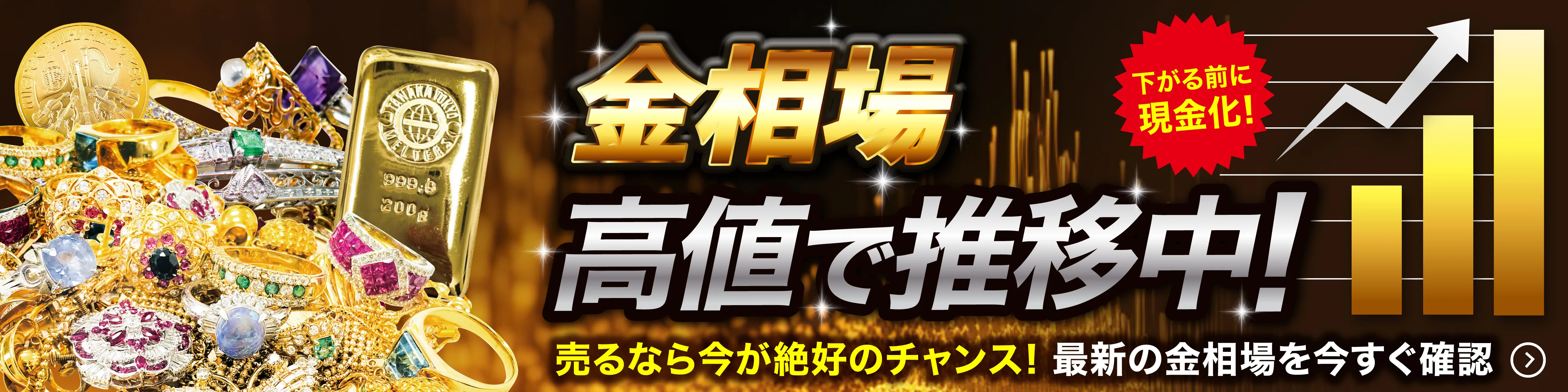



 ご相談・お申込みはこちら
ご相談・お申込みはこちら
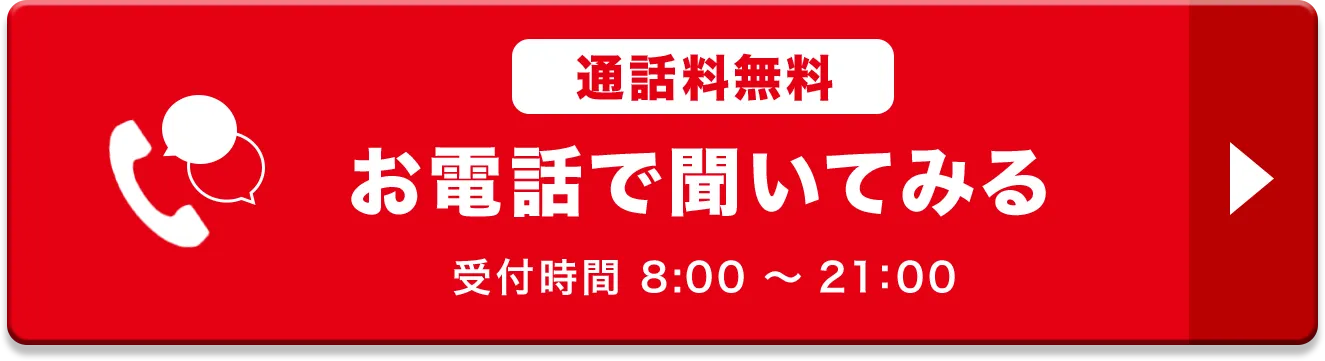
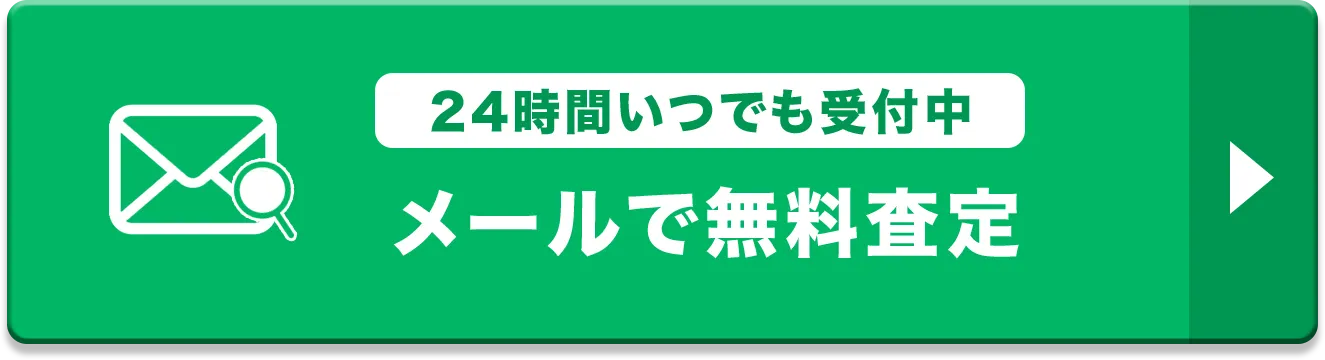

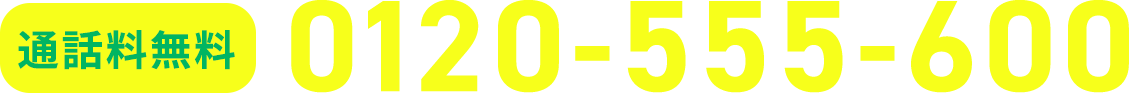
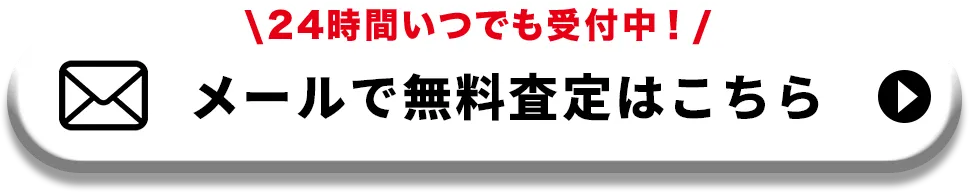
![【[current_year]最新】貴金属買取業者おすすめランキング17選!高く売るコツと選び方のポイントもご紹介](https://www.otakaraya.jp/app/wp-content/uploads/2025/06/0-Photoroom-7.webp)